【社内報担当者のキホン】トップメッセージの伝え方

社内報としての第一歩である経営方針やトップメッセージ。今回の記事では、読んでもらえる経営方針とトップメッセージのポイントをご紹介します。経営方針やトップメッセージの掲載について、問題意識やお悩みをお持ちの方のお役にも立てる情報としてお伝えしてまいります。
目次
こんな経営方針やトップメッセージの記事は読まれない
まず、読まれない経営方針やトップメッセージの典型的な例は
・毎回文型がバラバラ
・別のツールからの焼き直し
・表や図の多用
ほかにも色々とあるとは思いますが、これらの3つについては絶対にやってはいけないこととして考えておくことをおすすめします。
そして、裏を返すと、伝わりやすい経営方針・トップメッセージのポイントはこの3つです。
POINT
伝わるトップメッセージ(経営方針のポイント)
- 毎回の文型を共通化する
- 社内報オリジナルの切り口で掲載する
- 表や図の多用を控える
1.毎回の文型を共通化する
ひとつ目の「毎回の文型を共通化する」という点は最も重要なポイントです。
基本は「SVOC」。学生の頃に学んだ英語の文型ですが覚えていらっしゃるでしょうか。S:主語、V:述語、O:目的語、C:補語です。
SVOC:「SはOがCであるのをVする」「SはOがCするのをVする」
Sは、もちろん経営者です。そしてOが社員の皆さまとなります。
経営者である「私」が社員の皆さまに対してCであることを望んだり期待したり、経営者である「私」は社員の皆さまがCすることを望んだり期待したりするという文章です。
経営者は、社員の皆さまに何らかの望みや期待を持っており、社員の皆さまは、社内報のメッセージから何を望まれたり期待されているのかを読み取ります。
「私は、社員の皆さまが○○をすることを期待しています」という文型を基本形することで、読者である社員の皆さまは受け身ではなく、主体的に何に取り組むべきかを認識したり判断できるようになるわけです。
そして、その基本文型を元にさまざまな要素を加えて記事にします。
1)前号を発行した時期から現在までの動きと、重点テーマに関する結果や評価
2)その間で起こった、経営者として認識している事業環境の変化
3)長期ビジョンや中期経営計画、その他の課題との関係の経営者としての認識
4)それらをもとに対応すべき課題についてポイントを絞って明確に伝え、その課題に向けて社員一人ひとりがどのような姿勢で取り組むべきか、あるいはどのような考え方や意識を持って取り組むべきか
5)最後に社員に対する期待
この流れで記事を作成すると、発行頻度にあわせて四半期ごとや毎月の変化を全社員の共通認識として持つことができ、どのような姿勢でどのように取り組んでいけば良いかを、確認しながら日々の業務に取り組んでいけるようになります。
2.社内報オリジナルの切り口で掲載する
他のツールで掲載したトップメッセージを社内報用にリライトしたことが明らかな表現にすると、非常に危険な結果につながる可能性があります。つまり、経営者の言葉を理解できたとしても、読者である社員の皆さまにとっては自分たちに向けて語られているようには感じられず、心には届かない空虚なメッセージとして捉えられる可能性があるのです。
他のツールから転用する場合の解決方法は、「Q&A」
どうしても他のツールからの転用をせざるを得ない場合は、社内報らしい表現として「Q&A」方式にするという手法があります。
社員が経営者に対して質問するという企画にして、元の文章を再構成すると、経営者と社員の距離が縮まり、経営方針やトップメッセージが社員の皆さまに届きやすくなります。質問者は、架空の社員でかまいません。さらに、この社員を、キャラクターに置き換えると見た目にも親しみやすくなります。
経営者にインタビューしたり原稿執筆を依頼することができない場合は、こういった手法を検討することをおすすめします。
3.図や表の多用を避ける
図や表は重要なポイントに目線を誘導するために1〜3点程度を、重要度をもとに大きさの差をつけて掲載してください。誌面が図や表だらけだと、逆に非常に読みづらく、わかりづらい記事になってしまいますので気を付けましょう。
また、図や表の中が文字だらけだと、非常に読みづらくまた理解しづらくなります。伝えるべきが伝わらないという逆効果につながる可能性がありますので、図表内の情報も重要なポイントのみとなるように編集が必要です。
トップ対談の実践のポイントについてはこちらへ

何より大切なことは、対象に合わせて情報を絞ること
経営方針やトップメッセージはすべての情報が重要なために、限りある誌面にすべての情報、またはできるだけ多くの情報を掲載しようとして、ギュウギュウに詰まった誌面にしてしまいがちです。ですが、その誌面では誰も読んで理解しようとは思いません。
社内報担当者という情報の編集を担う立場として、重要な情報をしっかり読み取り、咀嚼します。何を伝えるべきかではなく「何が伝われば良いのか」という視点で、その他の情報や表現はザクザク切り捨てて、本当に必要な情報だけに絞ってください。そして、その情報を引き立てる役割、つまり伝わるために必要な情報や要素を汲み上げて、誌面を設計するという流れで記事を作成することをおすすめめします。
ご興味やご参考になると感じていただけた方は、ぜひご活用ください。

関連記事
-
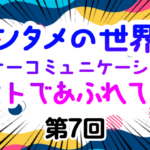
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
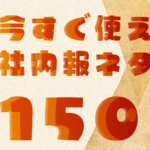
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
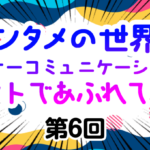
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

