【はじめての社内報制作】 第4回社内報づくりの正しい進め方
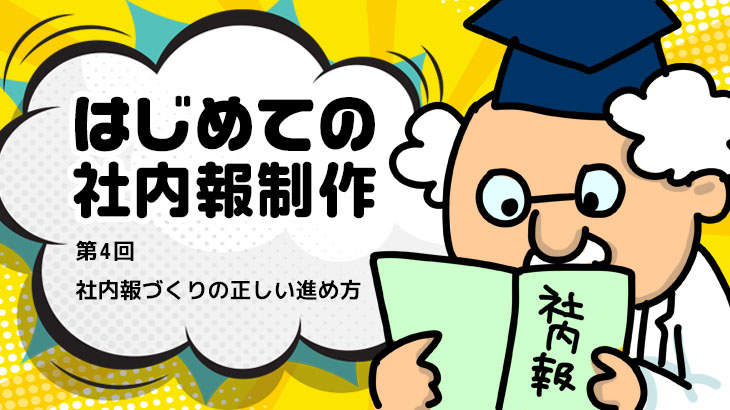
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。
シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが楽しく自信を持って社内報制作に取り組めるようサポートすることを目的に、社内報制作の基本から、読まれる社内報にする秘訣までを、できる限りわかりやすく解説してまいります。
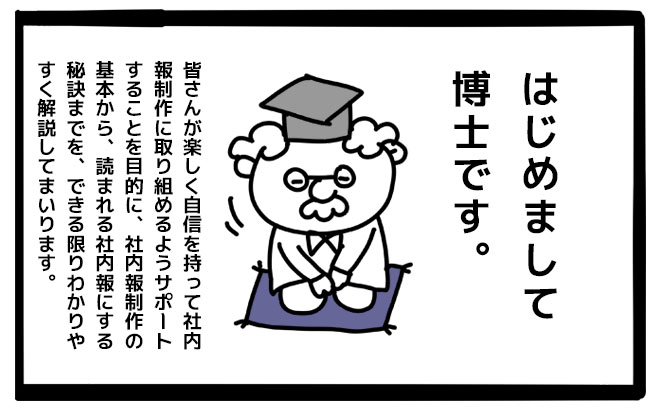
フロントローディングを考える
社内報づくりの効率化の最大のポイントの一つは、デザインをフロントローディングすることです。
<上司>昨日も遅かったようだけど大丈夫か?
<山田>ええ、まあ・・・(今日も帰れないかも・・・)
<博士>朝から疲れておるが、昨日は飲み歩いておったのかい?
<山田>ああ、博士でしたか?
ずっと残業が続いていて、もう驚く力も残っていませんよ・・・
<博士>なぜそんなに残業が続いておるんじゃ?
<山田>仕事が全然終わらなくて。
社内報の校了日が近づくと、毎回こんな感じなんです・・・。社内報を効率的に作る進め方ってないんでしょうか?
<博士>もちろんある。君はフロントローディングという言葉を知っておるかね?
<山田>聞いたことはあります。製品の開発や建築といった、モノづくりの仕事の業務効率を高めるために、前倒しが可能な業務を初期工程に集中させることで、後工程の作業をスムーズに進める手法ですよね?
<博士>その通りじゃ。
社内報もモノづくりの仕事なので、後工程で負荷がかかっている業務で前倒しが可能なものを初期工程に集中させると、後工程の負荷軽減はもちろん、全工程の平準化を進めることにもなるんじゃよ。

<山田>そうですね。
理屈はよくわかります。でも、後工程で負荷がかかっているのは主にデザインなんですけど、デザインは流石にフロントローディングすることはできないですよね?
<博士>いやいや、デザインはフロントローディングできるんじゃ。
後工程の業務負担はデザインに関する誤解が原因?
<山田>え?!
デザインを前工程に持ってくることができるんですか?
<博士>そうじゃ。
と言うよりも、そもそもデザインは初期工程から取り組むべき工程なんじゃよ。
<山田>え!そうなんですか?
でも、原稿がないとデザインは作れないじゃないですか?
<博士>確かにそう思ってしまうこともわからなくはない。
ただ、それはデザインの意味や役割に対する大きな勘違いが原因なんじゃ。
デザインをフロントローディングすることで、後工程の業務負荷を軽減したり、全体を通して業務を平準化させるにも、この勘違いについて誤解を解いておく必要があるので、まずはこの点について説明をしていこうかのう。
<山田>勘違い?
<博士>そうじゃ。
多くの人がデザインは見た目や見栄えを良くすることじゃと考えがちじゃが、それだと確かに原稿がないとデザインは作れん。
けれども、見た目や見栄えを良くするというのは、実はデコレーションといって、デザインする際の一つの手法のことなんじゃよ。
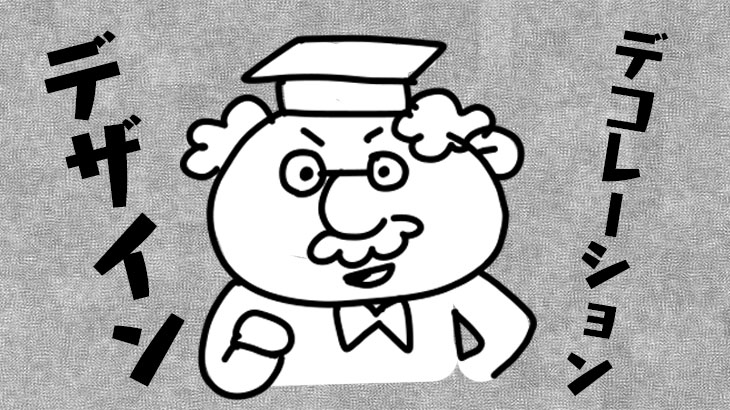
<山田>デコレーション。飾り付けということですね?
<博士>そうじゃ。
もちろん読まれる誌面にするためには、必要に応じて飾り付けをすることも重要なんじゃが、本来のデザインの役割は、見栄えを良くしたり、誌面を飾り付けることではなく、情報やメッセージを見やすく、正しく伝えたりすることに加えて、速く、わかりやすく、興味深く伝えるための、コミュニケーションの設計をすることなんじゃよ。
デザインとはコミュニケーションの設計のこと
<山田>コミュニケーションの設計ですか。
そう考えると、確かにデザインは初期段階に取り組まないと変ですよね?
<博士>理解が速くてよろしい!
実際にその通りで、例えばさっき言っておった製品開発や建築で設計図を描かずに製造を始めたり、建物を建てたりしないのと同じで、社内報も設計図を持たずに進めるのはおかしいと思わんか?
しかも設計図がなければ、価値や品質も後から考えることになるわけじゃが、これはおかしいじゃろ?
<山田>確かに、それはおかしいですね。
家でいうと、こんな暮らしができる家を建てたいという考えや想いだけで建材を集めて、建て始めるときや建てながら、どんな間取りや外観、内装の家にするのかを考えるといったようなことですよね?
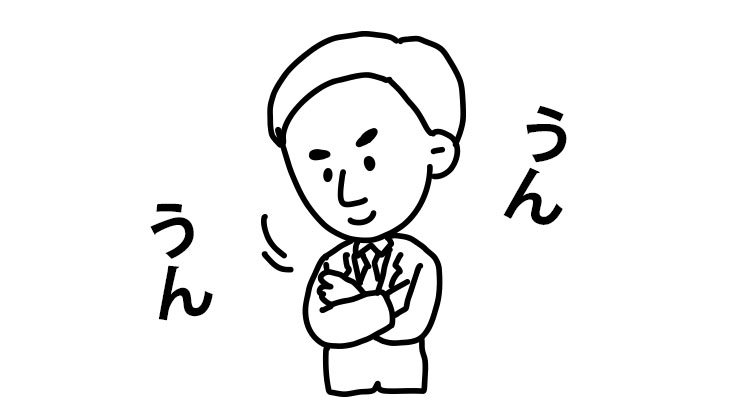
<博士>その通りじゃ。
しかも、建てている途中で何度も「何かイメージと違う」といって、組み立てた建材を解体して組み立てる。そしてまた何か違うと感じて解体し、最初から組み直すといった作り方をしておったら、それは時間がどれだけあっても足りんわな。
<山田>そんなやり方だと、そもそも用意した建材がムダになったり、その建材を集めるための時間や労力もムダになりますね。
と言うか、そんな建て方は最初からムリですよね?
<博士>そうなんじゃよ。
ところで今、ちょうどムダやムリという話が出たので、業務の効率化を考える際に欠かせない「ECRSの原則」というフレームワークがあるので、業務負荷を減らすためには、ついでにそれも覚えておくと良いぞ。
業務の効率化を考える「ECRSの原則」
<山田>ECRSの原則。初耳です。

<博士>要は、工程や業務に隠れているムリ・ムラ・ムダを見つけて…
それらをなくせないか(Eliminate:排除)
複数の工程を並行(Combine:結合)したり
順序を入れ替える(Rearrange:交換)ことで
ムリ・ムラ・ムダを減らせないかを考える。
そして最後に単純化する(Simplify:簡素化)ことができないかを考えるという、
仕事の効率化を検討する際の原則のことじゃよ。
<山田>フロントローディングは3番目の、工程を入れ替えることで業務のムリ・ムラ・ムダを減らすということですね?
<博士>社内報づくりでよく起こりがちな、校了が近づけば近づくほど忙しくなっていくという傾向はつまり、コミュニケーションの設計が不十分だったが故に起こっていた、後工程のムリ・ムラ・ムダによるものだったということなんじゃな。

初期段階のデザインは社内報づくりの仕様書
<山田>なるほど。
ところで、デザインはコミュニケーションの設計ということですが、まだ原稿ができていない初期段階のタイミングで、デザインをどの程度まで具体化しておくと、後工程の負担を減らすことができるようになるんですか?
<博士>まずはどんな第一印象、つまりファーストインプレッションと、あとは読み終わった後に残る感覚である読後感をどのようなものにするかといったことを考えることがスタートラインとなる。
<山田>ファーストインプレッションと読後感ですか。
確かにコミュニケーションの設計ですので、読者が誌面を見た瞬間から読み終えるまでに、その誌面からどういった印象や、言葉では言い表すことができないようなメッセージを感じるかという点は、デザインと大きく関係していますよね。
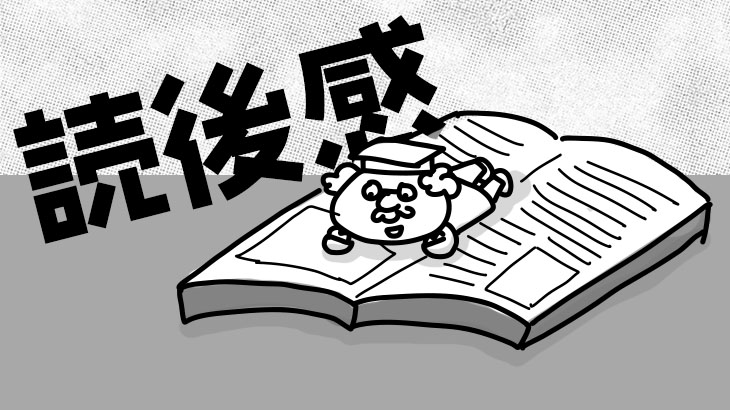
<博士>そうじゃ。
それらの方向性が決まると、あとは企画の内容と照らし合わせながら、伝えたい情報やメッセージを、いかに見やすく、正しく、速く、わかりやすく、興味深く伝えるために最適な文字量や配色、写真、図やイラストなどと、あとは余白も重要な要素なので、それらを言葉でしっかり書き出していくんじゃよ。
<山田>それはどうやって書いていけば良いんですか?
<博士>目指すファーストインプレッションや読後感を実現できそうだと感じるデザインを、雑誌やフリーペーパーなどを参考にして探すのが最も効果的で効率的じゃよ。
そして、目指す印象や雰囲気を醸し出せるデザインが見つかれば、それを参考にサムネイルというデザインのアイデアのメモ書きに、企画や必要な原稿の要素と合わせて、どんなファーストインプレッションや読後感を生み出したいのかといったことを、一つひとつしたためていくんじゃよ。
<山田>サムネイルというデザインのアイデアのメモ書き?
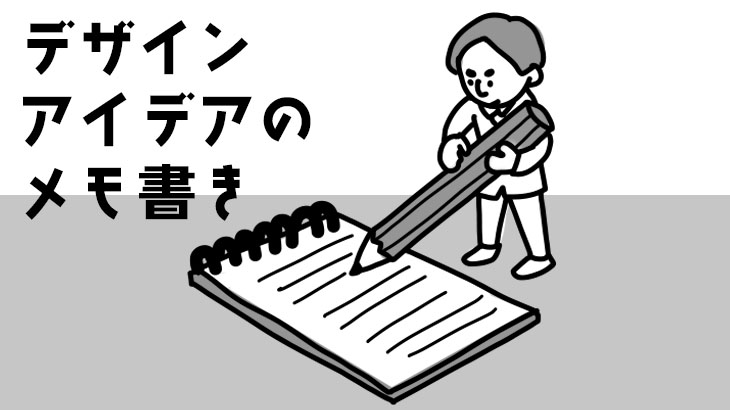
<博士>そうじゃ。
サムネイルとはつまり、親指の爪のことなんじゃが、親指の爪程度の小さなものに書き出すかのような感じで、イメージを見えるようにするんじゃよ。
そのあと、そのイメージの横に文字で必要なことを書きをしていくといった方法で取り組めば良いんじゃ。
<山田>イメージしたことを細かく説明したり、実際にデザインを作ったりするのではなく、イメージしたことを見えるようにするレベル感で、簡単な図面のように誌面のイメージを絵にして、その内容や意図を文字で補足するといった感じですね?
<博士>まさにそんな感じで十分じゃ。
最初に詳細まで決めたとしても、後の工程で対応できなくなったり、そもそも初期工程に時間と労力がかかり過ぎてしまうため、業務効率という点では本末転倒となってしまうからのう。
<山田>確かにそうですね。
具体的にはどの程度まで記せばOKという基準のようなものがあれば教えていただけないですか?
<博士>そうじゃな。
言ってみれば、社内報のその号を作る仕様書といったくらいまでが理想じゃな。
<山田>よくわかりました。
まだ気持ち的にも余裕のある初期工程のタイミングだと、企画と合わせてデザインというコミュニケーションの設計に、しっかり時間を割いて取り組むことができそうですので、一度やってみます!


関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
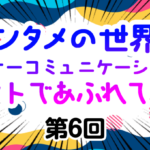
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
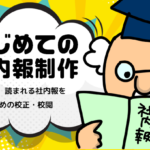
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
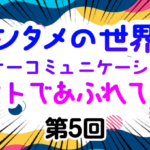
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

