【はじめての社内報制作】 第7回 読まれる社内報の「見出し」の作り方
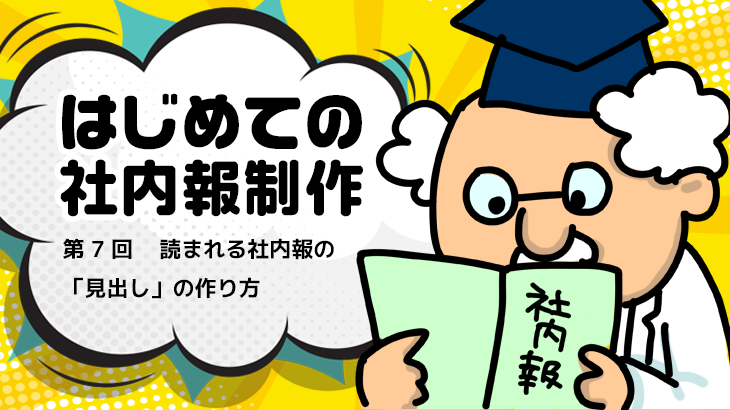
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。
シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが楽しく自信を持って社内報制作に取り組めるようサポートすることを目的に、社内報制作の基本から、読まれる社内報にする秘訣までを、できる限りわかりやすく解説してまいります。
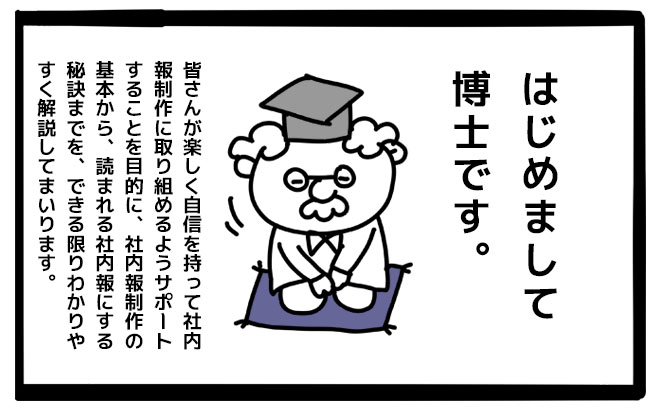
目次
読まれる社内報は見出しとリード文が8割
<上司>原稿の中身は良くなったな。
ただ、見出しがちょっと弱い気がする。
<山田>見出しはまだ博士に教えてもらえていないので・・・
<上司>博士?
<山田>あ、いや、何でもないです・・・


見出しとリード文は、読まれるかどうかの最初の関門
<博士>今度はどうしたのじゃ?
<山田>前回、原稿の作り方についてお話を聞かせてくれた最後に、今度は見出しのことを教えてくれるっておっしゃっていましたよね?
<博士>おお、そうじゃったのう。
確かに、記事が読まれるかどうかは、見出しとリード文で8割決まると言われておるから、そこにはしっかり力を入れて臨むべきポイントなんじゃよ。
<山田>そんなに大切なんですね?!
見出しもまだまだなんですけど、実はリード文も、つい内容を説明しようとして、堅くなったり、当たり障りないことを書いちゃったりするんですよね。

<博士>それでは読者の心はつかめないわな。
まずは見出しじゃが、見出しは読者の興味を一気に高める要素なんじゃ。
リード文は見出しで一気に高めた読者の興味を、さらにたたみかけるようにして、「読むメリット」を感じ取らせる要素と言えるんじゃよ。
<山田>見出しで高まった興味に、リード文でたたみかける。
面白そうですね!
構造を理解して「目の動き」を設計する
<博士>そのためにも知っておくべきこととして、見出しには種類や構造があるんじゃ。
<山田>えっ、構造? 見出しってタイトルのことじゃ……。
<博士>そうじゃな。
見出しには「記事のタイトル」としての役割もあるが、それだけじゃないんじゃ。
本文の構成を整理したり、流れをつくったりする「小見出し」なども含めて、見出しは記事全体の看板や道案内みたいなものなんじゃよ。
<山田>そうなんですね。
てっきり、本文の内容をまとめるものが見出しだと思っていました。
<博士>まとめるだけでも興味を惹くことができれば、それでも構わないんじゃが、忙しい社員に読んでもらうためには、やっぱり「読もう」といった気持ちを高めることが、読まれる記事にするためには欠かせないんじゃよ。
<山田>なるほど。
まずは見出しの構造から教えてもらえますか?

<博士>そうじゃな。
これが見出しの構造じゃよ。
肩見出し:記事のジャンルやテーマを示す補足的な見出し
大見出し(主見出し):読者の目を引き、本文へ誘う見出し
袖見出し:大見出しを補足する見出し
中見出し:テーマごとに章立てして、内容の構成を整理する見出し
小見出し:章の中で情報を分けて、読者の理解を助ける見出し
リード文:記事の概要や「読む価値」を伝える導入文
<山田>こうやって分けて考えると、読者の「読みやすさ」って、見出しの構造で設計されているように感じますね!
<博士>その通りじゃ。
<山田>確かに、新聞の記事もそれぞれ、大見出しだけじゃなく、肩見出しや袖見出しがあって、長い記事の場合は、本文に中見出しや小見出し、リード文をつけていますね。
読者の「目の動き」をデザインする
<博士>そうなんじゃ。
おさらいをすると、読者の視線はまず肩見出しや大見出しに行き、そこで気持ちが高まる。
そして、その気持ちを袖見出しでフォローする。
最後にリード文で興味を深められれば、読者は「読むかどうか」を無意識に判断して、目線を本文へ向かわせるんじゃ。
<山田>まずは、大見出しで目を引いて、「お?」と思わせる。
そして肩見出しや袖見出しで大見出しを補足する。
リード文では、具体的に「読む価値がありそう」と感じさせる。
中見出しや小見出しは記事をリズミカルに整えて、目線を引っ張っていくということですね?
<博士>そうじゃ。
この流れを意識するだけで、読者の「つまずき」をグンと減らせるぞ。
読まれる見出し&リード文のつくり方
<山田>じゃあ、見出しとリード文って、どういう考え方で書けばいいのかを教えてもらえないですか?

<博士>それは次の3ステップで考えるのがコツじゃ。
ステップ①:誰に届けたいかを明確にする
誰のための記事か。読者像がはっきりすれば言葉が定まる。
ステップ②:読後にどう思ってほしいかを想像する
読み終えた後の「感情のゴール」である読後感から逆算する。
ステップ③:お得感や意外性の「匂い」を醸し出す
匂いとは「読み進めたくなる予感」のこと。
そのポイントは、言葉にワクワク感を忍ばせることじゃよ。
<山田>読者を惹きつけるための見出しづくりって、要は読者と記事とのコミュニケーションを想像しながら考えるといった感じですね?
<博士>良いことに気づいたのう!
全くその通りじゃ。
実例で見る!NGと改善のポイント
<山田>すごくやる気が湧いてきました!
ちなみに、良くない見出しと良い見出しの違いがわかる例はありますか?
<博士>例えばこんな記事があったとしよう。
×見出し:「制度紹介」
×リード文:「このたび、〇〇制度が新設されました。社員の能力向上を目指して……」
これだと、伝えたいことが何なのかはわかるが、読む時間と労力を使ってまで読みたいとは思わんじゃろ?
<山田>確かにそうですね。
<博士>じゃあ、これだとどうじゃ?
◎ 見出し:「もっと早く知りたかった!大反響の〇〇制度」
◎ リード文:「いよいよスタートした新制度。注目を集める〇〇制度を、社員の声とともにお届けします。」
<山田>一気に興味がそそられて、読みたい気持ちになりました。
<博士>これは「知りたかった」という感情の動きと、「大反響」という期待感を合わせた見出しなんじゃよ。
<山田>まさに、読む前に一気に期待値が高くなりますね!
リード文は書き過ぎに注意!

<博士>ちなみにリード文には気をつけるポイントもあるぞ。
書きすぎない:本文の内容を匂わせながら、ネタバレしない程度に留める
話を散らかさない:あれもこれもと欲張らずに期待値づくりに絞り込む
一文目に「引き」を作る:起承転結ではなく、読者の興味から入る
<山田>見出しで読者の目線を惹きつけて、リード文で本文へ引っ張っていくといったイメージですね!
見出しとリードも「育てる」もの
<博士>あと、見出しは作って終わりにするのではなく、良い見出し作りに欠かせないことがもう一つあるじゃ。
<山田>なんですか?
<博士>社内報を発行したり、記事を公開した後、その反響をしっかりリサーチして、PDCAを回すんじゃよ。
<山田>記事の反響ではなく、見出しの反響ですか?
<博士>そうじゃ。
最初に、記事が読まれるかどうかは、見出しとリード文が8割といったじゃろ?
<山田>そうでした。
つまり、どの記事が読まれたかを見るときに、記事のテーマや見せ方だけではなくって、どんな見出しにしたのかも、読まれたポイントとして整理しておくということですね?
<博士>その通りじゃ。
見出しは記事の中身やデザインとは違って、数少ない言葉で読者の興味を惹く要素なので、見出しの振り返りをする際には、
・どんな言葉に反応があったか
・どんな表現が効果的だったのか
・再現できるポイントは何か?
の3つを整理して、それを次回の参考にしたり、技として取り溜めておくと、社内報の質はどんどん高まっていくんじゃよ。
<山田>見出しって言葉や表現を使い回したりすることができるので、作って終わりじゃなくて、しっかり振り返って、ストックしていくということですね?
<博士>そうじゃ。
同じものばかりじゃと飽きられてしまうし、手抜きに見えてしまうので、いろいろな言葉や手法を雑誌などから学んで、それを試すことも大切なことじゃよ。
<山田>博士、今日も本当に勉強になりました。
<博士>うむ。見出しは記事の入り口であり、記事の看板だと心得るんじゃぞ。
あと、リード文や小見出しはお店の導線のようなものと考えると、よりイメージしやすくなるんじゃないかのう?

<山田>お客さんをお店に引き込むための看板と導線。
お客さんがたどり着いた先にある商品棚、つまり本文が期待に応えてくれる内容なら、読者は次もまた来たくなる。
これが「また読みたい」と思わせる社内報の流れや作り方ということですね?
<博士>よく理解しておる!
その勢いで頑張るんじゃぞ。

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
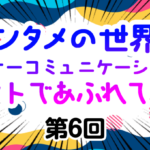
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
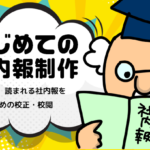
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
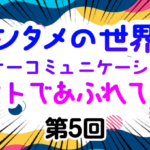
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

