【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第2回 編集の思想は、スーパーにある?
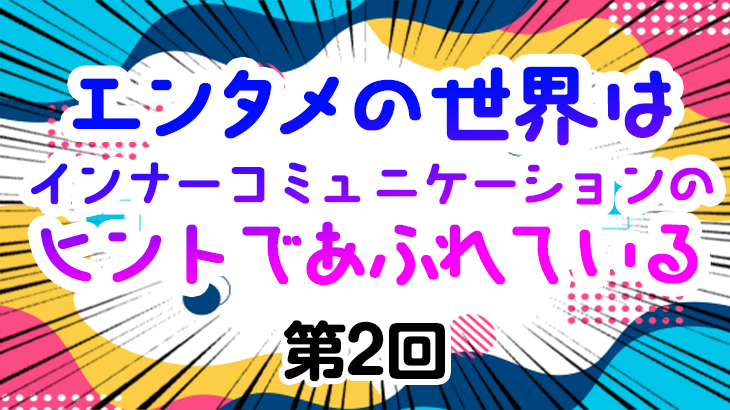
目次
映画『スーパーの女』を改めて観て、見えてきたもの
皆さんは、日常的な買い物にスーパーを利用しますか? それともコンビニで済ませてしまうことが多いでしょうか?
もしくはEC系サイトの通販?
私はスーパーが好きで、よく利用します。今週の晩酌のアテは、どんな流れにしようか、といったことを考えながら、食べたいものを決めこんでから行くか、飲みたいお酒から食材を考えて決めこんでから行くか、その日の売り場を眺めながら決めるようにするか・・・その時の気分や、売り場のテンションに振り回されながら買い物をするのは、けっこう楽しいものです。
ところが、気分次第などと思いつつも、ほぼ毎回といってもいいほど真っ先に買い物かごに入れる食材は決まっています。
それは、野菜類です。皆さんは、なぜだと思いますか?
売り場のレイアウトから見えてくるもの?
ところで、皆さんは伊丹十三監督作品『スーパーの女』(伊丹プロダクション製作、1996年公開)を観たことがあるでしょうか?
先の質問の答えが、この作品にあります。もちろん、この作品を観なくても答えに気づいている方もいらっしゃると思いますが、ほとんどのスーパーの売り場のスタート地点は、野菜売り場になっているから真っ先に買い物かごに入れる食材は野菜なのです。

ではなぜ、ほとんどのスーパーは野菜売り場から始まっているのでしょうか?
ここで、『スーパの女』の主人公、井上花子のセリフに注目してみましょう。
買い物にやってきた、とある主婦がまだ何を買うか決めてないという前提で、花子は話します。
「まず、彼女は台所で切れてるものを補充する。じゃがいも、キャベツ、トマト、キュウリ・・・だからまず、スーパーの売り場は野菜から始まってるわけだよ」
そう、そういうことなのです。そして、花子の話は大事なポイントへと展開していきます。
「とりあえず、毎日の野菜を買い物かごに放り込むうちに、だんだん彼女の買い物気分は盛り上がってくるんだよ。(中略)盛り上がったところで生きのいい鯛が目に飛び込んでくる。今夜は鯛チリにしようかな。あ、おでんも美味しそうだ。それとも久しぶりにすき焼きでもやるかぁ。」
そして、話を聞いていたスーパーの専務・小林五郎は感心します。
「なるほど〜。売り場に触発されて、一家団欒のメニューが決まってくる!」
この流れ、まるで雑誌の台割のようではありませんか?
読者の目を引き手を止めさせる、インパクトのある表紙(旬の野菜や目玉商品)から始まり、目的の記事(その日のメインとなる商品)にたどり着きやすく、かつ、関連記事(ついで買い)への関心を促し、読者の興味を連鎖させ、雑誌全体を回遊させるような、戦略的な配置が求められる点は、雑誌の台割と共通点だらけと言っても過言ではないでしょう。
『スーパの女』を改めて観て、そんなことが見えてきました。
ちなみに、この作品の面白さはそれだけではなく、もっと色々なところに言及できるのですが、当コラムの本筋から枝葉が広がりすぎるので割愛します。
編集の思想は、固定台割一択ではない
さて、少し目先を変えてみましょう。
実は、野菜売り場から始まるスーパーについて、“ほとんどの”と述べ、“全ての”と述べていないのにはワケがあります。
実際に、私の住まいの近所にはスーパーが3軒ありますが、そのうちの1軒は、お弁当・お惣菜売り場から始まっているのです。野菜売り場には、入ってから2回右折しないと辿り着きません。
このスーパーが、お弁当・お惣菜売り場から始まっているのはなぜでしょうか?
答えは立地にありました。このスーパーは、地下鉄駅改札に直結したビルの地下1階にあるのです。そして、地下鉄駅改札は地下2階にあります。つまり、このスーパーは仕事帰りの人々が「夕飯は何か買って帰って、サクッと済ませたい」と考えている人々がメインターゲットなのです。
では、日中は? と言いますと、このビルの2階から上のテナントはほぼほぼオフィスなのです。どこかのお店にランチしに行く方々もいるでしょうが、お弁当でランチを済ませようと考える方々も、当然それなりにいるはずです。
つまり、このスーパーは一般的な読者よりも、メイン特集のターゲットを考慮し、特殊な構成にした雑誌の台割と例えることができるのです。
ここで、社内報というメディアの特性を考えてみましょう。最大の特性は“商業誌ではない”というところにあります。
つまり、台割は固定でなくても構わないのです。広告も入らないことがほとんどですし、メイン特集の内容によっては、表紙からメイン特集、連載企画まで、極端に言ってしまえば一冊まるごと連動させることも可能なのです。そして、連動させる構成を取り入れることによって、思い切った台割にすることも可能なのです。
よりインパクトのある、読者の記憶に残る社内報を考える際に、固定化された構成(台割)の上だけで考えずに、メイン特集に合わせて柔軟な思想で作り上げていくことを念頭に置いてみても面白いのではないでしょうか。
それにより作り手側も、より楽しんで社内報を作ることができますし、何より作り手が楽しんでいれば、自ずと読者に楽しんでもらえることにもつながります。
久しぶりに『スーパーの女』を観て、ここまで述べてきたような思いを馳せてきましたが、それだけでなく、この作品は本当に面白い作品であることは間違いありません。

「運命と冒険。そして、異形の物語の交錯」の回で述べた、さまざまな作品を別の角度から再見してみるということを意識してみると面白いかもしれません。何らかのヒントが見つかることがあるかもしれない、という一例でもあったのが『スーパーの女』でした。

関連記事
-
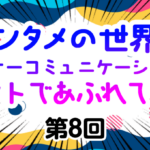
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第8回 “静かなる革命”の予感
皆さんは、藤原ヒロシ氏が2024年12月にスタートさせた『QUIET』というYouTube ...
-
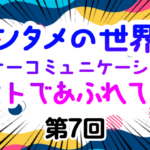
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
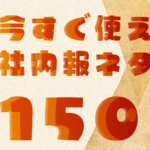
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...

