【コロナ時代の社内報】正しい企画作りの方法とは
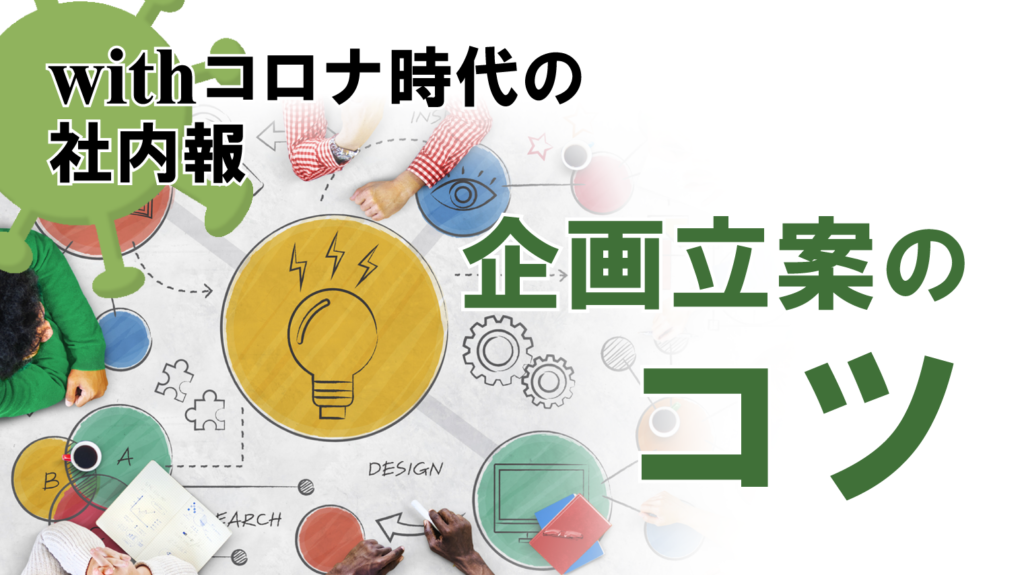
新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着きを見せるなか、withコロナの考え方が主流になりつつあります。そうした状況の中、今後の社内報の企画について、どのようなテーマを取り扱うべきか、どのような点を意識し何に注意を払うべきかなどなど、さまざまなお悩みをお持ちのご担当者が増えてきています。
そこで今回の記事では、社内報の企画を立てるためのプロセスとそのコツを、具体的な例でお伝えしていきます。
目次
今、社内報ができることは「社員に安心を届けること」だけ?
りえぞん企画で、お仕事をさせていただいている会社の社内報のご担当者から、最近特に多くなってきているのが今後の社内報の企画に関するお悩みです。なかでも「社員に安心を届けたい」という思いのもと、「社員の不安払拭」を当面の課題とした社内報の企画や内容の相談をいただくことが急増しています。
ただ、ちょっと待ってください。
社員の皆さんは今、本当に不安なのでしょうか?
もちろん、世界経済の大幅縮小をはじめ、さまざまな業界で事業環境が急激に悪化し、その回復についても予断を許さない状況が予測されるなど、先行きに対する不透明感や不確実性は計り知れない状況ということに間違いはありません。
けれどもその一方で、ある統計では、新型コロナウイルスの感染抑制に向けた、在宅勤務やリモートワークについて「良かった」という回答が75%にのぼるとの結果が出ています。
そこで改めて、このような状況だからこそ、「社員の不安の払拭」だけに絞って社内報の企画を考えるのではなく、このほかにも考えるべき課題を掘り起こすための手順や考え方についてお伝えします。
企画立案のプロセス
企画を立てる流れは以下のとおりです。
- 実現したい望ましい状況や状態を定める【目標の設定(発行目的)】
- 望ましい状況や状態に対する現在の状況や状態を探る【現状の把握】
- その状況や状態に対して考慮や対処すべき点をピックアップする【問題の整理】
- それらに対して望ましい状況や状態へ向かうためにすべきことを探る【課題の設定】
- それらをもとに、社内報として何をするかを考える【企画の立案】
今回は、この流れにもとづいて、先ほどの「社員は不安をもっているだろう」という認識を例にあげて、手順5の企画の立案に向けた準備のための手順2~4を説明していきます。
大切なことは現状に「正しい疑問を持つ」こと
まずは、手順1の「望ましい状況や状態に対する現在の状況や状態を探る(現状の把握)」についてですが、まずこのステップですべきことは以下2点です。
【現状の把握】のために
- 会社の今後の動きをとらえる
- 社員の状況や状態をとらえる
「会社の今後の動きをとらえる」のは、会社から示される内容をしっかり理解し、その伝え方を検討するという工程です。今回、特に重要なのは「社員の状況や状態をとらえる」ことです。
「現状把握」のためにやるべきこと
それは、なんとなくしか認識していない社員の状況や状態に対して「正しい疑問を持つ」ことです。
「正しい疑問を持つ」とは、たとえば「社員はきっと今後に向けていろいろな不安を持っているのだろう」という認識に対して、本当に正しいのか?という疑問です。
次に、この「本当に正しいのか」という疑問を解消するために、事実や実態を知るための行動が必要になります。そしてその結果、「社員はきっと不安を抱えている」ではなく、「社員は今、一人で仕事をしているときに、漠然とではあるものの、これまでと同じようなやり方で仕事をしていても良いのかという不安を感じている可能性がある」というレベルで現状を把握することができます。
この疑問によって得た、より具体性のある答えは、さらに次の疑問を抱くことによって、その精度が高まっていきます。
疑問をもつ
先ほどの答えに対して、「すべての社員がその答えに該当するのか」という新たな疑問をもつと、「特に不安を感じているのは新入社員で、主な不安は会社や職場、仕事に馴染めるかどうかについてだった」「若手社員も不安の度合いが大きく、これらは業務スキルや時間管理などが大半だった」など、解決すべき新たな問題につながります。
疑問の幅を広げる
また、「不安に感じている人ばかりではないが、それはなぜか?」と、疑問の幅を広げれば、たとえば「自分は大丈夫」という正常性バイアスにとらわれている社員が少なくなく、不安の払拭よりも重要な問題を発見することにもつながったりもします。
ポジティブな側面にも着目する
さらに、疑問の向きを変えると、「ポジティブな状況や状態はないのか?」といった疑問が生まれます。そうすると、在宅勤務やリモートワークをやってみて良かったと回答した方が75%にのぼるという外部データにたどり着きます。
これにより、「これまでとは異なる環境や状況の中で、むしろ新しい経験によって新しい価値観や可能性に気づいたのではないか?」という疑問につながります。
こうして、「社員の多くは不安を感じながらも、それに対して受け身になって行動がとれないことはなく、むしろこの状況を自分ごと化して、主体的かつ積極的に行動している」という可能性に気づくことができます。
このように、正しい疑問を芋づる式に出し、疑問の幅や向きを変えると、現状についてより詳しい実態や新たな問題点に気づくことができ、企画として取り上げる対象や課題の幅が広がっていきます。
問題を整理して課題を設定する
ここまで来ると、あとはスムーズです。
次はプロセスの3番目「問題の整理」です。ここで、社員の皆さまの現状を、実態や問題としてリスト化します。
withコロナに対する実態と問題
- 社員が現状に対して不安を持っている
- 不安の要因は主に現在の仕事のやり方についてと会社の今後について
- 不安の度合いは大半の社員はそれほど大きくない
- ただし若手や新入社員は不安の度合いが大きく対処が必要
- 若手にはスキルや時間管理に関する対処が必要
- 新入社員に対しては会社や職場、仕事への距離感を埋めることが必要
- 不安への対処だけではなく「正常性バイアス」にも対処が必要
- 社員の新しい経験や価値観には社内法に対しても可能性を感じる
- 大半の社員は現状や今後に対して主体的かつ積極的
次に、この実態と問題への対処の方向性を考えることが、4つ目「課題の設定」となります。
上記の実態と問題から、課題を以下のように設定しました。
課題の設定
- チャレンジの方向性や指針の提供
- 間違った正常性バイアスの是正や打破
- 若手や新入社員の不安の払拭とモチベーションアップ
こうして、課題が設定できれば、最後は5番目のプロセスの「企画の立案」です。課題からの企画立案については、また別の記事でご紹介します。
まとめ
社内報の企画を立てるためには、このようなプロセスを参考に「正しい疑問」を繰り返すことで現在の状況や状態を幅広く多面的な視点で把握し、問題や課題を整理します。そうすると、これからの社内報づくりにおいて、何をすれば良いのか、何を企画のテーマとして取り上げるべきかといったお悩みは、ほとんど解消されると思います。
また、今回お伝えしたプロセスで、企画づくりの可能性が広がると感じていただけたのではないでしょうか。誰もが確かな答えを持ち得ない状況に入ったことで、これまでできなかった企画にチャレンジする機会とも考えられます。
そこで、どのような企画が考えられるか、社内報ラボでも継続的にご紹介してまいりますので、ぜひご期待ください。

関連記事
-
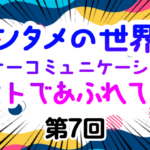
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
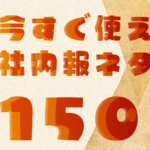
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
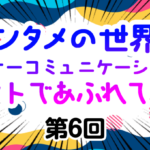
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

