【はじめての社内報制作】 第5回 読まれる社内報の企画の立て方
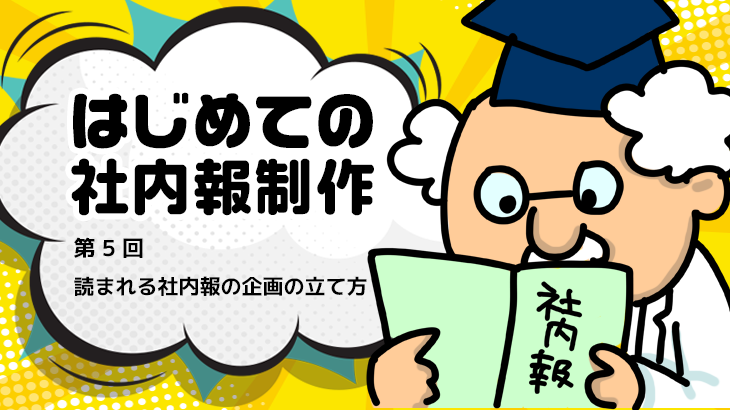
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。
シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが楽しく自信を持って社内報制作に取り組めるようサポートすることを目的に、社内報制作の基本から、読まれる社内報にする秘訣までを、できる限りわかりやすく解説してまいります。
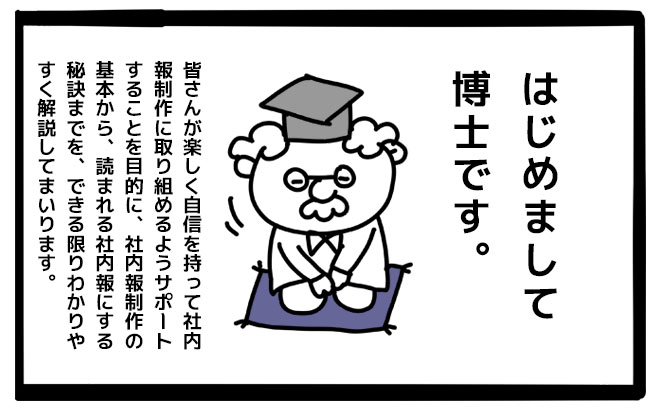
社内報の企画を立てるスタートラインは自分に問いかけること

<上司>今日は社内報の企画セミナーに参加してきたんだったな。どうだった?
<山田>はい、たくさんの事例を見ることができました。
(事例の紹介ばっかりで、知りたかった企画の立て方までは教えてくれなかった・・・)
企画とは、より良い変化を創造すること
<博士>また憂鬱な顔をしておるのぉ?
<山田>ああ、博士。
社内報の企画の立て方のセミナーに参加したんですけど、事例の紹介ばっかりで、企画の立て方はほとんど教えてくれなかったんですよ。
<博士>そうか。それは残念じゃったな。
ところで君は、企画とは何をすることだと考えておるんじゃ?
<山田>
そうですね。
あくまでも社内報の企画ですけど、例えば、会社のビジョンに向けて、社員が行動変容するために、経営方針やビジョンを社員に理解させたり、浸透させたりすることですね。
あとは、社員がそれに向けて行動変容したり、モチベーションを高めたりするようにすることだと考えています。
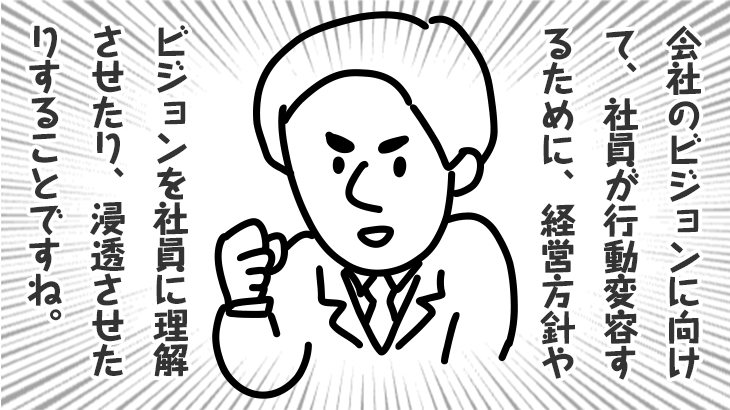
<博士>つまり企画とは、社員の行動や意識、意欲を変えることだと考えておるんじゃな?
<山田>はい。そうだと思います。
<博士>そうか。
では聞くが、その考え方で立てられた企画の先にある社内報の記事は、どんなものになりそうじゃ?
<山田>そうですね。
何というか、ウチの社員ならこうあるべきだといった、教科書のようなものができあがりそうです。
<博士>そのようなコンテンツや記事が続く社内報は、君が目指している社内報なのかい?
<山田>いえ。
実はそんな企画しか考えられなくて悩んでいたんです。
どうやったら、もっとみんなに「読んで良かった」と思ってもらえる企画を立てられるようになるんですかね?
<博士>それで社内報の企画のセミナーに参加してきたんじゃな?
<山田>はい。博士、教えてください!企画ってそもそも、何をすることなんですか?
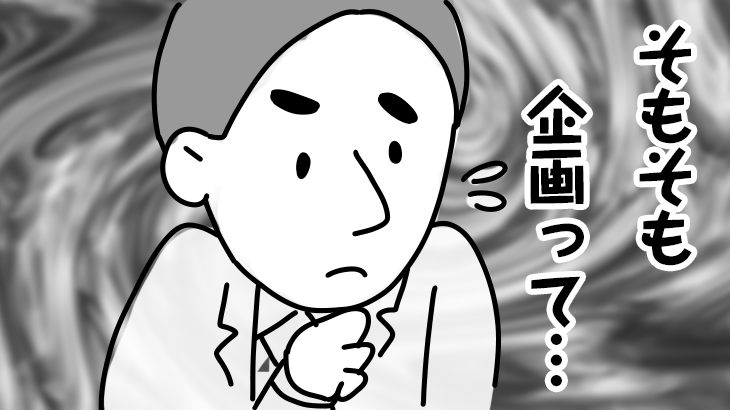
<博士>そうじゃな。
いろいろな考え方や言い方があると思うが、企画とは「より良い変化を創造すること」だとわしは考えておる。
タテ・ヨコ・ナナメの関係性をより良くしていくこと
<山田>より良い変化を創造することですか?
なんかすごく前向きな感じがします。
<博士>そうじゃな。
企画はよく、何らかの問題や課題を解決策を考えることだといったような言われ方をするが、それだと良くないものを正すことが企画だと考えてしまい、良いものをさらに良くするといった企画が立てられなくなるんじゃよ。
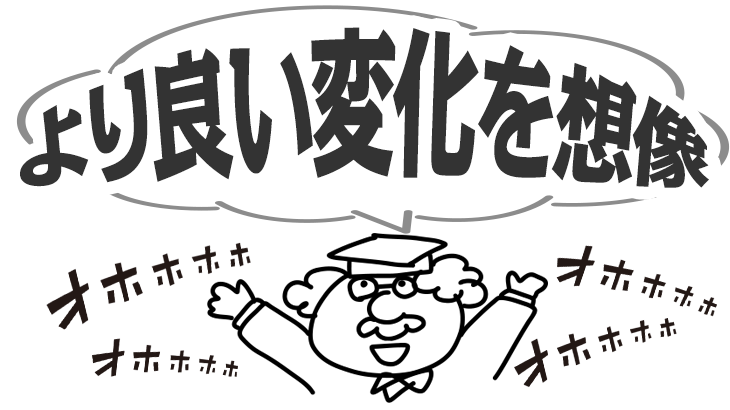
<山田>確かに。
<博士>けれども、企画とは「より良い変化を創造すること」だと考えると、問題や課題だけに目が向くのではなく、良いことをもっと良くするために、何ができるか、どうすれば良いかと考えることができたり、そもそも、全社に広めるべき良いことは何かといったことに着目する余地ができて、企画の幅が広がるんじゃよ。
<山田>しかも、そんな社内報だと読んでみたいという気持ちになりそうです。
<博士>社内報の企画を考えるときは、その感覚がものすごく大切なんじゃよ。
<山田>ところで、より良い変化って何ですか?
<博士>そうじゃ。
君は、社内報はタテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションを促すツールだと聞いたことはないかい?
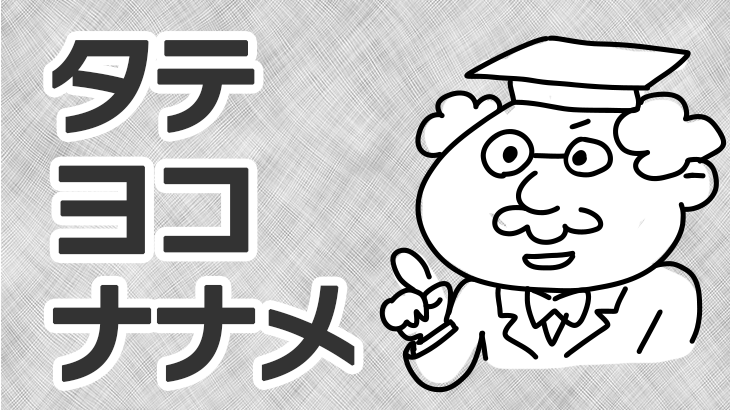
<山田>あります。
つまり社内報の企画を立てるためには、タテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーションにより良い変化を創造することを考えるということですか?
<博士>その通りじゃ。
例えばさっき言っておった、社員の行動や意識、意欲も、社内報による情報によって変わるものではなく、その社員を取り巻くさまざまな関係性によって変わるものだと考えておるんじゃ。
<山田>関係性ですか?
<博士>そうじゃ。
社員を起点において、その社員のタテ・ヨコ・ナナメの関係性により良い変化を生み出すことで、その社員の行動や意識、意欲をより良い方向に変えるといった感じじゃ。
<山田>なるほど!
ところで、タテは経営と社員、ヨコは社員と社員だとわかるんですが、ナナメとはどんな関係ですか?
<博士>これは抽象的な表現なんじゃが、ナナメは一般的に、部署を越える関係や、あるいは社会との関係など、タテの関係やヨコの関係以外のすべての関係と考えておけば問題ない。
<山田>そうなんですね。
社員の関係性に対してより良い変化を創造する。なんだか、すごくやる気が湧いてきました!
<博士>それは良かった。では、その気持ちを大切にがんばるんじゃぞ。
企画を立てるスタートラインは自分へ問いかけること
<山田>ちょっと待ってください!
社員の関係性により良い変化をつくるためには、いろいろな社員のタテ・ヨコ・ナナメの関係性を知らないといけないということですよね?
<博士>おぉ!良いことに気づいたのう。まさにその通りじゃ。
<山田>いやいやいやいや、何となくやる気が湧いてきていましたが、そう考えると今のままでは、とてもじゃないけど良い企画なんて立てられないってことですよね?
<博士>まさにその通りじゃ!
企画は足と目と耳で考えるもので、社内報の場合もあらゆる職場や現場に足を運んで、目で見て、耳を使っていろいろな人の話を聞くといったことを繰り返すことで、社内報としてのより良い企画が立てられるようになるんじゃよ。
<山田>それは無理ですよ!
だって、それをやるには時間がかかりますし、今で言うと、私はほとんどの社員の関係性がどういったものなのかを知らないんですよ!!
<博士>まあ、そう慌てなくても大丈夫じゃよ。
少なくとも、自分自身や自分の周りの人の関係性なら、凡そはわかるじゃろ?
<山田>恥ずかしながら、周りのこともあまりわからないのですが・・・
まあ、自分のことなら何となくわかります。
<博士>まずはそこから始めれば良いんじゃよ。
上司との関係や、同僚との関係、他部署との関係、そのほかにもいろいろとあるじゃろ?
そうした関係性をイメージすることが企画のスタートラインなんじゃ。
<山田>つまり自分に問いかけることが企画のスタートラインということですね?

<博士>その通りじゃ。
例えば、中期経営計画の理解を目的とする企画を立てるとなった場合、自分にとって、どの関係の何により良い変化を生み出すことが、中期事業計画の理解を進めることに効果的かを考えるんじゃよ。
<山田>それだと中計と自分との仕事の関係や意義を上司や先輩たちと話す機会を増やすことですかね?
<博士>そうじゃな。
もちろん、タテの関係という視点に立つと、経営の意志である中計の内容や意義を、会社の成長や発展と、社員の幸せを願う経営者の立場に立って、社員一人ひとりに伝えるためには何をすれば良いのかを考えることになる。
けれども、伝えられる情報量に限りがある社内報で、それをあらゆる社員に対して行うことは容易ではないわな。
<山田>むしろ中計の内容や意義を社員一人ひとりに伝えることは、社内報ではなくマネジメントの役割のような気がします。
<博士>そうじゃ。
一方で、君がさっき言ったように、中計と自分との仕事の関係や意義について、上司や先輩たちと話す機会を増やす効果や方法は、マネジメントよりも、さまざまな切り口で伝えることができる社内報に分があると思わんかい?
<山田>確かにそうですね。
それに、そういった内容だと、一般の社員にも、その上司や先輩にも役立つ企画になりそうな気がします。
<博士>そうじゃな。
<山田>ありがとうございました!
良い企画が立てられないのは、テクニックがないからとか、センスがないからと思っていましたが、企画とは何かをちゃんと理解していないことが原因だということがわかりました。
あとは、良い企画を立てられるようになるために大切なことは、社内のいろいろな場所に足を運んで、目で見て、話を聞くことですね?
<博士>その通りじゃ。
<山田>その考え方とスタンスでがんばってみます!


関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
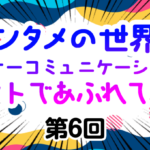
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
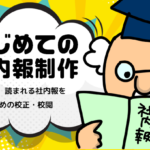
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
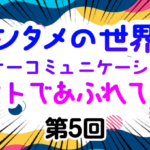
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

