社内報づくりの基本【前編】

社内報は、社内のさまざまな「関係性」をより良い方向に導くためのツールです。
ここで言う「関係性」とは、たとえば経営と社員、社員と社員、社員と社会、社員と仕事など、さまざまなものを含んでいます。
そのための主な役割としては、経営の想いを届けたり、社員同士をつなげたり、働く意欲が高まるような情報を提供したりといったことが挙げられます。
社内報はこのように、関係性をより良い方向へ導くことを大きな目的として、さまざまな役割を持たせて運用する、会社にとってかけがえのないメディアだと言えます。
今回の記事では具体的にどんな目的で社内報が発行されているのか前編、後編にてお伝えします。
目次
なぜ社内報を発行するの?
経営の想いをみんなに届けるため
会社が目指している未来や大切にしている価値観を社員一人ひとりに伝えていくことは、組織運営において欠かせない取り組みです。
ただ、経営方針などを文章で伝えるのは簡単ではありません。内容が難しくなったり、受け手に「自分ごと」として伝わらなかったりすることもあります。
そういったコミュニケーションに関する問題に対して、社内報というツールは非常に有効です。
と言うのも、たとえば、経営メッセージをインタビュー形式にしたり、ビジョンを現場の取り組みとセットで紹介したりするなど、伝え方を工夫することができます。
このように、硬いテーマも、読みやすく・わかりやすく届けられるのが社内報の強みの一つです。
この強みを活かして、多くの企業では社内報というツールを用いて、経営理念や中長期ビジョン、戦略の浸透を図っています。
社員同士が互いのことをもっと知るために
「社内にどんな仲間がいるのか」がわかることは、組織の信頼関係を築くうえでとても大切です。
けれども、部署や拠点が違うと、どこで、どんな人が、どんな仕事をしているのか、どんな想いを持って働いているのかといったことを知る機会がありません。
そういった点を踏まえて社内報では、社員紹介やチームの取り組み、仕事の裏側などを特集することで、普段は関わりがない人たちに対しても、仲間としての関心や「こんな仕事で頑張っている人がいるんだ」「その工夫、真似してみたいな」といった共感を生み出していきます。
これにより、社内にポジティブな感情を広げながら、会社としての一体感を醸成したり、社員同士の絆や仲間意識を育んでいきます。
このように、社内の「ヨコ」の関係や、社外も含めた「ナナメ」のつながりをつくるきっかけを生み出すことも、社内報の大切な役割の一つです。
働く人のやる気や自信を後押しするために
社内報で社員の声や取り組みが取り上げられると、多くの人が自然とモチベーションを高め、「またがんばろう」と思えるようになります。
これは単なる情報の共有にとどまらず、「働くこと」そのものの意味や意義を再認識できる機会にもなります。
また、他の社員の取り組みを知ることで、相互に刺激し合う関係性も育まれていきます。
さらに、社内報に出ることがきっかけとなって、「自分の仕事が見てもらえている」といった気持ちや、自分の仕事が「誰かに伝わっている」と感じる社員が増えると、従業員エンゲージメントの向上にもつながるため、たくさんの人が社内報に出られるように工夫することが重要です。
会社の動きを伝えて距離感を縮める
働き方が多様になるほど、「会社と社員」や「社員と社員」との間に物理的・心理的な距離感が生まれやすくなります。
そのような中で、「会社全体で今こんな動きがあるんだ」、「他拠点でも同じように頑張ってるんだ」といった情報は、会社への帰属意識や一体感を育むために欠かせません。
社内報ではこの点についても大きな役割として、日常の業務では見えにくい「全体のつながり」を感じられるようにするといったことを果たしていきます。
社内報を発行する目的は時代とともに変わる?
社内報を発行する目的をここでは、社内のさまざまな「関係性」をより良い方向に導くこととして、それをさまざまな角度で噛み砕いてお伝えしてきました。
このような、社内報を発行する目的は「時代とともに変わるのか」といった疑問が生まれるかも知れないのですが、基本的には変わらないと考えていただいて大丈夫です。
ただ、社会の変化や働く人の価値観の変化によって、「関係性」のあり方は変わっていきます。
社内報はその点をしっかりキャッチして、社内の関係性について、今はどんな点を押さえておくべきかといったことを考えながら取り組む必要があります。
この点については、なんとなく変わっていっていると感じても、それを具体的に認識したり、その状況を上司や社内報制作に関わるメンバーに説明しようとしても、実感していることを上手に伝えられないこともあるかと思います。
そこで、そういった変化に対して、社内報をどのように対応させていけば良いかについて、アドバイスしてくれているサイトをご紹介します。
https://www.kkc.or.jp/plaza/index.html
ご紹介した企業広報プラザは「一般社団法人 日本経済団体連合会(経団連)」の関連組織である経済広報センターが運営する、企業広報の実務に役立つ情報を発信しているWebサイトです。そこでは、社内報やグループ報を取り巻く状況など、社内広報の担当者にとって必要なことが紹介されています。
紹介されている内容も、数年に一度のペースですが、社会の大きな変化に合わせて、内容が少しずつ変わっていっていますので、ぜひ定期的にチェックしてみてはいかがでしょうか?
社内報で何を伝えれば良いの?
社内報をつくる上で、担当者の多くが最初に悩むのは「何をテーマにすればいいのか?」ということではないでしょうか。
実際、テーマは無限にあるようでいて、「これが本当に必要な情報なのか?」と考え始めると、手が止まってしまうこともあると思います。
そんなときにおすすめしたいのが、「タテ・ヨコ・ナナメのコミュニケーション」という視点。
この3つの方向から社内のつながりを見つめることで、伝えるべきこと・伝えたいことが自然と見えてくるようになります。
タテのコミュニケーションで会社の方針や想いを、社員一人ひとりへつなぐ
「タテのコミュニケーション」とは、経営層と社員のあいだの情報の流れを指します。
経営トップの方針や会社としての方向性は、多くの社員にとっては「遠い存在」に感じられがちです。
そこで社内報では、経営層のメッセージを丁寧に届けたり、経営戦略を現場視点でかみ砕いて紹介したりする工夫が重要になります。
たとえば、経営方針を「どう実践しているか」を特集する記事や、役員の素顔に迫るインタビューなどは、経営と現場を近づける役割を果たします。
ヨコのコミュニケーションで部署や職種を超えるつながりを生む
次に「ヨコのコミュニケーション」。
これは主に、部署間や拠点間といった、組織の横のつながりのこと。
たとえば、ある部署でうまくいった取り組みが、他部署にもヒントを与えることがあります。
そうした「成功の共有」のほか、「悩みの共感」ができるのも、社内報の魅力のひとつです。
日常ではなかなか交流のない部署同士でも、他部門の仕事やチャレンジを記事で知ることで、お互いへの理解や尊重が深まる。
これは、組織の一体感を育てるうえでも、とても大切な役割です。
ナナメのコミュニケーションで幅広い関係性への「気づき」を届ける
最後に「ナナメのコミュニケーション」。
これは、上下関係などの縦の関係や、組織や部署といった横の関係などのほか、お客さまや社会など、多種多様なステークホルダーを含めた、より大きな枠組みや関係性における、さまざまな垣根を越えたつながりのことを指します。
社内報では、こうした多様な声を拾い上げることで、「自分とは違う立場の人の想い」や「会社の一員として知っておくべき、さまざまな関係者の意向」などに触れる機会を提供することができます。
これは、お互いを理解し合うきっかけになるだけでなく、社員一人ひとりが仕事や役割の見方に新たな「気づき」を与えてくれるものにもなります。
「つながり」を起点にしてテーマを選ぶ
この「タテ・ヨコ・ナナメ」の視点は、コンテンツづくりにおける道しるべになります。
たとえば、タテの関係で主なものとしては、経営者インタビューが挙げられます。
その他にも、経営者や役員の想いや気づきを伝えるコンテンツや、会社のビジョンや戦略、方針を噛み砕いて伝えるコンテンツなどが挙げられます。
続いてヨコの関係では主に、部署紹介が挙げられます。そのほか、各部門の方針や取り組み、部署連携の事例、組織の枠を超えるプロジェクトの取り組みといった、さまざまな部門、部署の取り組みの紹介、社員の仕事やプライベートの紹介などがヨコの関係づくりのコンテンツとなります。
最後にナナメのコミュニケーションについて。
ナナメのコミュニケーションに関するコンテンツは最も多彩で、たとえばステークホルダーインタビューや、お客さまの声を届けるコンテンツ、社内のさまざまな課題をテーマに他社の取り組みを紹介したり、有識者などから知見をいただいたりする、外部取材を取り入れたコンテンツなどがあります。
このように、タテ・ヨコ・ナナメの3つの視点を持つことで、どの視点で誰に何を届けたいのかを考えると、テーマに幅を持たせることができて、充実した社内報を作ることができるようになります。

社内報はどのツールが効果的?
社内報をつくるうえで、もうひとつ悩ましいのが「どんな媒体で発信すべきか?」という点。
コミュニケーションツールの選択肢が増え、それらが一般的に定着してきたことで、社内報のツールの選択肢も年々広がっています。
紙、Web、動画、社内報は結局どれが良いの?
これらのツールには、社内コミュニケーションツールとして、それぞれに良さや便利さがありますが、どのツールを活用するのかを検討する際に大切なことは、「誰に」「どんな内容を」「どう届けたいか」といった軸を持って、目的に合った手段を選ぶことです。
ここからは、その観点をもとに、社内報で用いられている主なツールの特徴や使い分けのポイントをご紹介します。
紙の社内報は「じっくり読める」「手に取れる安心感がある」ツール
紙の社内報は、昔ながらのスタイルですが、今も根強い人気があります。
その主な理由は「手に取って読める」ことの親しみやすさがあることや、「じっくり読ませる」ことができるといった点。
特に製造業などで「現場にパソコンがない」「デジタル環境が整っていない」ことが少なくなく、紙の方が確実に情報を届けることができます。
また、表紙のデザインや紙の質感など、「モノ」としての魅力や保存性もあり、読み手の記憶にも残りやすいという特長があります。
その一方で、制作や印刷・配送にコストや時間、手間がかかるため、発行頻度は季刊や隔月刊が主流となっています。
Web社内報はタイムリー性や柔軟性と双方向性に強み
Web社内報は2010年頃から活用する会社が増え、働き方改革や働き方の多様化の進展のほか、コロナ禍以来、在宅勤務が一般化したことなどを受けて、その活用が急速に広がってきています。
Web社内報は、更新性の高さのほか、スマホやPCがあれば、どこからでもアクセスできる利便性が大きな魅力です。
さらに、紙の社内報ではアンケートを行わなければ閲読や閲覧傾向を知ることができなかったのですが、Web社内報はそれらを瞬時に得られるといった点から、双方向性の高い運用が可能。
このようなWebならではの強みのもと、速報的なニュースや日常のちょっとした話題も気軽に発信したり、動画や社員参加型のコンテンツを取り入れるなど、「動き」や「双方向性」のある社内報にしていく動きが活発になってきています。
ただ、Web社内報の進展や活用頻度の高まりに伴って、さまざまな問題も出てきています。
たとえば、記事の作成や公開、更新が紙よりも容易に行えるため、数多くの記事を載せることによって、過去の情報が比較的短期間に目に留まらなくなったり、情報の重要度の違いがわかりづらいといったことが起こりやすくなります。
さらに、紙のように手元に届く「プッシュツール」ではなく、社員が自ら見ようという意識や気持ちにならないと見てもらえない「プルツール」という点も、Web社内報の弱点と言えます。
そのため、「この情報は重要だ」といったことがわかる工夫や、見てもらうための工夫、継続的に見にきてもらうための「習慣づくり」といった、記事づくりだけではなく、社内報と社員との関係づくりといった施策や仕掛けが必要となります。
動画は感情に届きやすく印象に残りやすい
近年、社内報でも動画を活用する企業が増えてきました。
動画には、「言葉だけでは伝わりにくいこと」を感情とともに届けられるという強みがあります。
たとえば、経営トップのメッセージを動画で伝えると、メッセージの内容だけではなく、メッセージを語る「表情」「声色」「速度」「息づかい」「しぐさ」など、文字では表すことができないことも伝えることができるため、メッセージの重みや温度感がダイレクトに感じられるコミュニケーションが可能となります。
工場や店舗の紹介、社員インタビューなども、現場の空気感ごと伝えられるのが映像の魅力です。
ただ、動画は一方で、撮影や編集に一定の技術や労力、時間が必要。
また、見る側の視点で考えると、ある程度まとまった時間がないと見ようと思わなかったり、文字を読むだけではなく、音声を聞くといったことも必要になるため、職場で動画を見る雰囲気や文化が求められます。
そのため、動画の活用は「視聴時間」への配慮を行なったり、音声を聞かなくても見られるように、メッセージやコメントをテロップで流すといった工夫が必要となります。
社内SNSはダイレクトなコミュニケーションに有効
近年では、社内SNSの活用も進んできています。
こうしたツールは、スピード感のある発信や、チャットのような双方向のダイレクトなコミュニケーションができる点が強みです。
ただし、社内報のように「しっかり読んで理解してもらう」ことには向かないといった点や、業務のつながりがない人とのコミュニケーションにはあまり活かされないといった実態もあり、さらにはツールを増やしすぎることによる管理コストの増大や、社内の情報流通を煩雑にするリスクもあるため、使いどころや使う目的をしっかり見極めることが大切です。
ツールの使い分けは「強み」と「目的」の二軸で検討する
ツールの使い分けで大切なことは、使い分けや今とは異なるツールを使うことを目的にするのではなく、ツールの強みを理解した上で、それを使うことで「どの問題の何をどう変えたいのか」、「何をどう良くしたいのか」といった目的を明確にすることが最初の一歩。
そして次に、それらに基づいて「連動」と「分割」で考えます。
連動はたとえば、ビジョンや経営方針など、深い理解と同時に感情に届けたいメッセージや情報は、速報的にWebで伝え、理解を深めるために紙を用いて、感情に届けるために動画を用いるといったような使い方。
一方で分割とは、日常の出来事や速報はWebや社内SNSで素早く発信し、人の想いなど、じっくりと読んでもらいたいテーマは紙で伝えるといったような、これはWebに掲載し、これは紙に掲載するといったような使い方を言います。
このように、ツールの強みと情報を伝える目的の二軸で、どのツールをどう使うのかを「メディアミックス」で考えるのが、それぞれのツールを有効に活用する方法です。

社内報の発行や更新の効果的な頻度は?
社内報の発行や更新の頻度に正解はありません。
それは、会社の規模、業種、発信手段、職種の比率、年齢層の割合などのほか、社内報の運用体制によって、「ちょうどよい頻度」が異なるからです。
この点を踏まえてここでは、考えるときのヒントになるいくつかの視点をご紹介します。
「業種」や「職種」、主な「働き方」によって変わる
たとえば製造業や建設業のように、現場業務が中心の職場では、勤務場所がバラバラだったり、PCを使う時間が限られていたりすることがあります。
こうした場合、毎週更新されるWeb社内報をチェックするのは困難なため、紙社内報を軸にした運用で、隔月刊や季刊といった頻度で発行するのが有効です。
一方で、全員にPCやスマホが支給されている営業や、オフィスで働く人が多い企業であれば、比較的容易に閲覧できる環境が整っているため、Web社内報を軸にして、更新頻度をやや高めにしても運用しやすいと言えます。
このようにまずは、社員の働く環境に合ったリズムを考えることが、最適な発行頻度や更新頻度を検討する第一歩です。
無理のない更新ペースを考える
社内報制作を少人数で行なっていたり、社内報制作の経験が浅いチームにとっては、更新が比較的容易なWeb社内報といっても、記事の制作を考慮すると、たとえ月1回の発行・更新でも大きな負担になります。
その結果、「継続できない」といった問題のみならず、「内容がマンネリ化してしまう」という問題に直面するケースは少なくありません。
そこで、「どのくらいのペースなら続けられるか」を見極めることが大切です。
そのため紙社内報なら、まずは隔月や季刊など、ゆとりあるスケジュールからスタートし、運用が安定したら回数を増やすといった考え方や、紙社内報の発行頻度を抑えて、Web社内報の運用を少しずつ進めていくといった方法もおすすめです。
読み手の状況や行動も意識してみる
発行頻度や更新頻度は、発行側の都合だけでなく、読む側のペースにも目を向けて考えることも大切です。
たとえば、年度末や四半期決算期は業務が忙しくなる職種が多いので、その時期とは異なるタイミングで紙社内報を発行したり、Web社内報の更新を集中させるといった考え方や、繁忙期は自ら見にいく必要があるWeb社内報よりも、自宅に持ち帰ることができる紙社内報が向いているといった考え方も有効です。
また、季節の変わり目や社内イベントと関連させることで、読みたくなる企画に発行時期を合わせたり、「毎月〇日配信!」と決めて、更新を定例化することで、「そろそろ社内報の時期だな」という習慣づくりをしたり、それに合わせて編集スケジュールやプロモーション計画を立てたりすることができ、運用の安定化や平準化にもつなぐことができます。
量より「質」と「リズム」を大切にする
社内報は情報の種類や量よりも、社内報に信頼や期待、効果の実感を持っていただきながら「読まれ続ける」ことが大切です。
そのため、たとえ更新頻度が少なくても、毎回の内容に意図やメッセージがある、読者が自分ごととして読める構成になっている、前向きな話題や会話につながっている、その結果、社内の関係性が良くなっていっているといった状態を維持したり、向上することができれば、それは発行や更新の頻度以上に大きな効果を発揮します。
逆に、ただ発行や更新の回数をこなしたり、多くのコンテンツ量をさばくだけになってしまうと、情報の質や精度が落ち、読み手の興味が薄れ、せっかくの社内報が掲示物や回覧板のような「通知」の一つになってしまうこともあります。
このように、社内報の発行や更新の頻度は「質」を担保できるように計画することが前提ですが、同時に読み手が社内報に触れる「リズム」を作るといった観点も大切です。
たとえば、読み応えのある特集記事を紙で季刊、日常のニュースはWebで週1回、動画は動画が有効なコンテンツに絞って、それぞれの公開の時期を定期化して運用するといったように、情報の特性や読み方に合わせて発信リズムを設計することで、読み手の負担も軽減され、発信側もメリハリのある運用ができます。
ここまでを整理すると、発行や更新の頻度を考える上で大事なことは、受け手である社員にとっても、送り手である編集サイドにとっても、そしてもちろん会社の動きとしても「ちょうどいいテンポ」を見つけて、「無理せず」「皆にとってほどよく」「きちんと届ける」を念頭に、Webのアナリティクスの情報や、読者アンケートなどを活用しながら、担当者と読者が一緒になって考えるといった姿勢で臨むことが大切だと考えます。

社内報の効果的なコンテンツって?
続いて、読まれる社内報にするために「どんな企画を載せれば良いの?」という、社内報ならではのコンテンツ企画についてお伝えします。
社内報だからこそできるコンテンツを作る視点
社内報を発行する目的や、掲載する情報、ツールの選定方法、発行や更新の頻度について理解して、最適な答えを見つけることができるけれども、読まれるためのコンテンツを考えようとすると、何を糸口にして考えれば良いのかがわからないことは少なくないと思います。
そんなときにおすすめしたいのが、「社会と会社」の二つの視点を掛け合わせて考える方法。
社会とは「今、世の中で起きていること」、会社とは「自社の中で起きていること」で、それぞれ掛け合わせた発想を起点にしてテーマを探すという考え方です。
「社会×会社」の視点で読まれるコンテンツを作る
企画のテーマを考えるとき、「うちの会社の話題」だけを探してしまうと、どうしてもネタが尽きてしまいます。
けれど、「社会」というレンズを一つ加えるだけで、読まれるコンテンツのテーマを探すフィールドは一気に広がります。
たとえば「社会の動き×自社の取り組み」という視点で考えると、人的資本経営や生成AIなど、世の中で注目されているテーマやトレンドを背景にして、自社はどんな動きをしているのか、数年前と今では何がどう変わったのかといった発想につながります。
また、「季節×社員」の視点で考えると、入社式、株主総会、年末調整、決算など、毎年行われているイベントなどとともに、それらに裏方として関わる社員の仕事の内容や想い、工夫を紹介する企画のアイデアにつながっていきます。
「社外の視点×自社らしさ」の視点で考えると、顧客や機関投資家、業界新聞の記者などを取材対象にした、自社の見え方を語っていただくようなコンテンツのアイデアにつながります。
「人の関心ごと×製品や社員」の視点で考えると、世の中のさまざまなトレンドやブームのほか、雑誌の特集で組まれるようなテーマなどをもとに、自社の製品や社員の行動から、何らかの側面を切り取って掛け合わせることで、社員に興味を持ってもらいやすいコンテンツを組むことも可能となります。
たとえば、アウトドアブームをヒントに、社内のアウトドアと料理が好きな人から、おすすめのレシピを紹介してもらうコンテンツや、ストリーミング配信やYouTubeの視聴頻度の高まりをもとに、おすすめ動画の紹介をしていただくコンテンツのほか、自社製品を使ってみたといったコンテンツや、街で見つけた自社の欠片といったような、写真投稿型コンテンツなどを考えたりすることができます。
このように、自社内だけにとらわれず、「社会×社内」の視点を持つことで、社員にとって親しみやすかったり、興味を持ってもらいやすい、社内報ならではと言ってもらえるコンテンツを考えることができるようになります。
おわりに
社内報は、社内の経営と社員、社員と社員、社員と社会、社員と仕事などの「関係性」をより良い方向に導くためのツールです。
今回の記事では具体的にどんな目的で社内報が発行されているのかについてお伝えしました。
次回【後編】では、どんな目的で社内報が発行されているのかを更にお届けいたします。

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
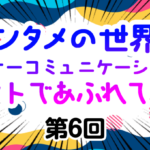
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
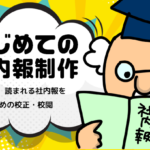
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
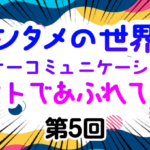
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

