はじめての動画社内報

社員とのつながりを深め、組織全体に温度感のあるメッセージを届けたい。
そんな思いから注目されている社内報での「動画」の活用。
本記事では、社内報に動画を取り入れることの意義や実際の活用方法、視聴されやすくする工夫、社内での運用のヒントまで、さまざまな角度から、社内報の動画の活用と、その方法についてご紹介します。
目次
なぜ今、社内報に「動画」が注目されているのか?
働き方の多様化や、情報伝達手段のデジタル化が進む中で、社内報も急速に変化し続けています。
特に紙からWebへのシフトは加速しており、その中でも現在は特に、「動画」の活用が、社内コミュニケーションの強化において注目を集めています。
これまでの社内報は、テキストと写真を中心に情報を届けることが主流でしたが、動画には「音」「表情」「声のトーン」といった、文字では伝えきれない非言語的な情報を届ける力があります。
社員の雰囲気や現場の空気感、言葉に込めた思いが、よりリアルに伝わることで、「伝える」から「伝わる」社内報へと進化させる可能性を秘めています。
特にリモートワークの定着等により、対面の機会が減った今、動画は「人の気配」を感じられる数少ない社内メディアとしても、その価値を高めています。
経営層のメッセージ、部署紹介、新人インタビューなども、文章だけでなく映像で届けることで、より多くの共感や理解を生むことが期待できます。
ここからは、そんな「社内報×動画」の活用について、
・動画を取り入れるメリット
・始め方と運用のポイント
・コンテンツのアイデア
などをお伝えします。
初めて動画に取り組むご担当者の方にもご活用いただけるよう、基礎から応用まで網羅しています。これからの社内報づくりのヒントとして、ぜひお役立てください。
社内報に動画を取り入れるメリット
文字だけでは伝わりづらい「現場の熱量」や「人の想い」を、よりリアルに、よりダイレクトに届けられるのが動画の魅力です。
たとえば、現場での会話の空気感や、社員の声のトーン、身ぶり手ぶり──。
それらは読み手の解釈に委ねられる文章と違い、ありのままを届けることができます。
そのような効果が期待できる動画は、社内報の目的の重要なポイントである「人と人とのつながりを生み出す」といった点に対して、これまでのような情報を「補完する」ツールとしての役割から、「加速させる」ツールへとシフトし、その可能性を模索する段階へと進んできています。
また、紙媒体ではカバーしきれなかった「音」や「動き」といった点についても非常に有効で、視覚と聴覚の両方から伝えることで、紙やWeb社内報の文字や写真、イラストといった情報よりもはるかに強く、視聴する社員の記憶に残るメッセージを発信することができることへの注目が高まっています。
さらに、重要なメッセージを多面的に伝えるといった、メディアミックスの考え方に基づく活用や、あるいは紙とWeb、そして動画の、それぞれの利点を活かしたクロスメディアの考え方に基づく活用を通して、社員と情報との関係の接点を、より多様にするといったことにも役立ちます。
また、紙面で社員の取り組みを紹介しつつ、QRコードを読み取ることでその取り組みの様子を動画で観るといった、閲覧や視聴の動線を取り入れることで、読者により深い共感と理解を促すことも可能になります。
このように、動画には表情の変化や声のトーンといった、文字や写真では伝えられないことが伝えられるだけではなく、新たに動画を取り入れることによって、情報をより立体的に伝えることができるといったメリットは極めて大きく、動画はこれからますます欠かせないツールとなっていくことが予想できます。
動画のメリットで見る活用イメージ
このような観点をもとに動画を取り入れるメリットと活用のイメージを簡単に整理します。
文字だけでは伝わらない「空気感」を届けることができる
その場の音や表情の動き、言葉にしにくい空気感といった、「人の存在感」や「現場の雰囲気」をそのまま届ける力があります。
たとえば部署紹介や現場リポートを動画で届けると、写真やテキストでは伝えきれない活気や、空間の雰囲気が自然と伝わり、「この部署って楽しそう」「現場はこんな風に動いているのか」と、読者の印象に強く残ります。
非言語情報で「人となり」を伝えることができる
動画の大きな特徴の一つが、『声』をそのまま伝えることができるという点。
文章や写真では表現しきれない、話し方のリズム・トーン・抑揚・間(ま)といった「非言語情報」によって、言葉の内容を超えて、その人の性格や想いまで、より深く印象づけることができます。
その効果について、例えば経営者のメッセージでみると、ただ文章で読むだけではなく、動画で本人の声や表情を合わせて見て、聞くことで、受け手が感じとることができる情報の量や幅は、格段に増えて広がります。
見る人の理解をより強力にフォローすることができる
動画は「視覚」と「聴覚」の両方から情報を届けるため、文字情報だけよりも記憶に残りやすいばかりでなく、見る人の理解をフォローするという点でも非常に有効です。
例えば、新しい制度や業務プロセスの解説では、パワーポイントのアニメーションのように、思考の流れを動的に見せることができます。
社員インタビューのような「感情」を伴って伝える情報は、文字や写真よりもリアルさを見せることができる動画を使うことにより、見る人に対して「読んで感じる」という負担やストレスをかけることを大幅に軽減できるため、情報の理解とともに、共感を生み出しやすくなります。
若手との親和性が高い
若手社員にとって、情報収集の手段は確実に、文字から動画へとシフトしています。
特にYouTubeやTikTokなどの短尺動画に慣れた世代は、じっくり文字を読むよりも、動画による「流し見」の方が、情報をより豊かに得ることができ、タイムパフォーマンスも圧倒的に高いということを、肌感覚で理解し、それに慣れ親しんでいます。
そこで、「新人紹介」「若手社員インタビュー」「趣味紹介」などのコンテンツは、動画を見るだけではなく、撮ることにも慣れている若手社員にとって、文字の原稿を記すよりもハードルが低く感じる場合も多く、そういった手法を取り入れることで、若手の社内報への参加意欲の向上や、見る習慣づくりにもつながる効果も期待することができます。
情報伝達をハイブリッド化しやすい
すべて動画にするのではなく、「テキスト+動画」といった、情報のハイブリッド化により、伝えるべきことをより幅広く、多面的にアプローチすることができます。
まず、幅広くという点について、動画では雰囲気やストーリーを伝え、テキストで補足情報や要点を整理する構成にすると、「時間がない人にはテキスト」「しっかり知りたい人には動画」と、読者のスタイルに合わせた情報提供が可能になります。
また、社内報内で「動画あり」アイコンや再生マーク付きのサムネイルを設けることで、視認性も高まり、アクセス率の向上にもつながります。

社内報で動画を使うときの代表的なコンテンツ例
ここからは、動画の導入効果や活用パターンをさらに詳しく紹介していきます。
経営者メッセージ
社長や経営層のメッセージを動画で届けることで、文字では伝えきれない「語り口」や「表情」を通して、より温度感のあるコミュニケーションが可能になります。
年度初めの方針発表、期末の振り返り、社員への感謝のメッセージなど、節目にあたるタイミングでの活用が特に効果的です。
社員にとって「直接語りかけられているような感覚」を与えることができ、組織全体の一体感の醸成にもつながります。
新人紹介、社員インタビュー
新人紹介では特に動画が有効です。
自己紹介を文字で掲載するだけでなく、動画で「声」や「笑顔」なども伝えることで、その人のキャラクターがより具体的に伝わり、社内での「顔が見える関係性づくり」に貢献します。
また、社員インタビューも人気コンテンツの一つ。
仕事のやりがいや仕事への想いを語っていただく背景の映像に、その方の職場での働きぶりや、職場の上司や同僚と談笑しているシーンなどを取り入れると、メッセージがより瑞々しく伝わり、その方がどんな環境で働いているのかを、言葉にすることなく伝えることが可能になります。
部署紹介、現場レポート
「部署紹介」や「現場ルポ」などの動画では、普段なかなか目にすることのない他部門の仕事ぶりや職場の雰囲気を「動き」と「音」で伝えることができます。
例えば工場を取り上げる場合は、現場の機械の稼働音や作業中の掛け声、社員同士の自然なやり取りなど、動画ならではの臨場感やリアルな業務風景を、見たまま伝えることができます。
とくに拠点数が多い企業では、拠点間の垣根を越えるコミュニケーションの促進は大きな課題ですが、動画を活用して「顔や場所を見て感じることができる社内報」にすることで、その課題の解決を図ることができます。
社内イベントレポート、ダイジェスト紹介
入社式や社内の表彰式などのイベント動画は、参加できなかった社員にもイベントの様子や空気感を届けられ、そのような社員の方々に貴重な体験を提供することができます。
また、そのような動画は記録といった観点でも、会社の未来にとって、非常に大きな資産にすることができます。
「1分で振り返る○○イベント」や「ダイジェスト版」といった短尺編集も、忙しい社員にとっては視聴しやすく、閲覧数アップにつながります。
Q&A形式、マニュアル動画
業務フローやツールの使い方、社内制度の説明など、ナレッジ共有系コンテンツは、図解やマニュアルを動画で補足すると、理解度が大きく向上します。
また、制度改定の際に「○分でわかる変更点」などの形式で配信することで、全社への認知拡大・理解促進にもつながります。

視聴される動画にするためのポイント
こんなにもたくさんのメリットがある動画ですが、どんなに思いを込めて作っても、「見てもらえない」ことには始まりません。
社内報における動画活用では、Web社内報に動画をただ埋め込むだけでは十分とは言えず、「見てもらうための仕掛け」が必要です。
そこで、ここからは見られる動画にするためにはどうすれば良いかをお伝えしてまいりますが、その前にまず、よくある「見られない」理由と、その具体的な解決策をセットで紹介していきます。
勤務中に動画を見ることへの心理的抵抗
動画社内報に関するアンケートをとると、
「オフィスで動画を見るのは周囲の目が気になる」
「音を出すのがはばかられる」
「集中して見る時間が取れない」
といった声が返ってきます。
この問題の解決としては、動画にフル字幕やテロップを付けることが効果的です。
こうすることで、文字情報と共に、現場の雰囲気、人の表情といった、動画のメリットの多くを残して、伝えたいことを伝えることができます。
また、1分以内の短尺動画で「スキマ時間視聴」へのニーズに応えることも効果的です。
そもそも動画の存在に気づかれていない
これも社内報アンケートでよく上がる声ですが
「動画があることを知らなかった」
「リンクが目立たなくて気づかなかった」
といったものがあります。
この問題に対して、Web社内報の記事に組み込む動画の場合は、その記事のタイトルに【動画あり】などのラベルを付けて、動画への導線をつくります。
そのほか、社内報をプロモーションする全社メールに、動画部分だけをピックアップした「今週の動画特集」を組むことも効果的。
長すぎて途中で離脱される
動画は視聴に一定の時間を要します。
そのため、
「時間がないので後回しにして見るのを忘れていた」
「3分超えるとちょっとしんどい」
といった問題が発生します。
そこで、最も基本的な対策としては、どの動画も基本は1分〜2分程度を目安にした短尺編集にすることがあります。
そのほか、動画の冒頭に5秒程度のイントロダクションを設け、「この動画で何が得られるか」を、ダイジェスト映像を背景において伝えることも有効です。
どうしても短くできない動画は、映像の切り替え頻度を高くしたりして、飽きない工夫を施したり、あるいはシリーズ化して小分けに配信し、何回かに分けて視聴できる方法をとるといった工夫をすることをおすすめします。
内容に魅力がなく興味がわかない
最後に、
「登場人物に共感できない」
「何の話かわかりづらい」
「自分に関係なさそう」
といった、最も本質的な問題についてお伝えします。
こういった意見に対しては、やはり「企画」で応えていくことが王道です。
例えば、社員の「あるある」を取り入れた動画や、「○○さんに5つの質問」「1分で分かる部署の裏側」など、数字を用いて全体像や視聴時間の目安を伝えた上で、内容を掘り下げていくといった、参加者目線で親しみやすい企画にするといった工夫で、読者を飽きさせずに引き込んでいきます。
見られる動画社内報づくりの始め方
スマートフォンや無料編集ツールを使うだけでも、十分に「伝わる動画」が制作可能となった現在、動画の制作は決して難しいものではなくなりました。
そこでここからは、社内で動画を制作するための基本を、5つのステップでご紹介します。
★ステップ1
「なぜ、誰に、何を、どのように」をしっかり定める
最初に行うことは基本的に、紙の社内報やWeb社内報と同じで、「なぜ動画にするのか」「誰に届けたいのか」「何を伝えるのか」「どのように見せるのか」、あるいは「どのように感じ取ってもらうのか」を明確にすることです。
ただ、動画の場合は撮り直しが難しく、制作中の途中で見せ方や伝え方を調整することが、紙やWebのコンテンツ制作よりも難しいといった特徴があります。
そのため、企画を立てる段階では、紙やWeb社内報よりもより入念に、動画の目的、ねらいとともに、「何を伝えるのか」「何を見せるのか」「どのように見せるのか」といったことを、しっかり検討しておく必要があります。
★ステップ2
構成案と台本を作成する
見られる動画にするためには、最後まで飽きさせないことが求められるため、「台本」よりも「構成」に注力する必要があります。
そのため、たとえ1分といった短い動画であっても、伝えたいメッセージとその伝え方を明確にするために、以下の要素を予め書き出します。
・イントロダクション:どんな動画かをひと目で伝える
・本編:伝えたい内容と流れを、シーンのイメージとともに簡潔に記す
・エンディング(クロージング):見た人に何を残すのかを定める
この際に押さえておくべき考え方は、動画は時間を追いながら膨大な情報を届けるツールだという点です。
見る人のモチベーションや姿勢は時間とともに落ちていくことを想定し、まず最初に何をどのくらい伝える動画なのかが感じ取れるようにするとともに、時間の流れのなかで変化をつけたり、波が感じられるようにしたりします。
また、「ピーク・エンドの法則」というものがありますが、その法則にもあるように、エンディングは見た人の中に何を残すのか、どんな印象を持って見終えてもらうのかといった点で、極めて重要なポイントとなります。
動画づくりでは、こういった点をしっかり認識して構成を考えていきます。
★ステップ3
撮影は光と音に注意する
最近のスマートフォンのカメラの画質は、Web等での視聴に十分耐えるため、撮影はスマートフォンのカメラでも十分対応可能です。
撮影の際に注意すべきは、画質より「光」と「音」です。
光は撮影対象の印象を大きく左右する要素です。
基本は、撮影対象となる人の顔が暗くならないよう、前方から光が当たる場所を選ぶこと。
ただ、真正面からの光は映像を単調な印象にしますので、斜めからの光を有効活用することができる場所、あるいはそのような撮影が可能となる時間を選んで撮影します。
続いて「音」についてですが、一番気をつけることは、動画に関係のない周辺の音を拾いすぎてしまうことに注意を払います。
インタビューのマイクはスマートフォンに内蔵されているものでも、概ねクリアですが、スマートフォンのマイクは周辺の音もクリアに拾ってしまいますので、できる限りそのような音が入らない場所で撮影、収録することが大切です。
★ステップ4
編集は使いやすいツールを用いる
撮影が終わったら、予定していた構成やシナリオをもとに編集していきます。
編集するツールについて、最近はスマホのアプリのような簡易的なものから、プロが使用する本格的なものまで、いつでも、誰でも簡単に、安価、あるいは無料で使用することができます。
そのなかで、プロが使用するツールは、高度な編集を可能とする多種多様な機能が多く備わっている一方で、それらの中から必要な機能を適切に選択して使うには、相当なスキルが必要となります。
動画社内報の編集では、それほど高度な機能を使用しませんので、容易に手に入る最小限の機能が備わったツールから使い始めることをおすすめします。
ちなみに、最小限の機能とは
・不要部分を簡単にカットできる機能
・字幕やテロップを入れることができる機能
・BGMや効果音を取り入れることができる機能
・簡単に映像ファイルにすることができる機能
などです。
★ステップ5
見やすい場所への配置とプロモーション
完成した動画は主にWeb社内報の記事の一部に組み込むか、1つのコンテンツとして掲載するのが一般的です。
最近ではWeb社内報のカテゴリーの一つとして、動画チャンネルを設けたり、あるいは動画社内報として、Web社内報から切り離して運用している会社もあります。
ただ、いずれの場合であっても、見られなければ作った意味や甲斐がありません。
動画もWeb社内報の他のコンテンツと同様に、作って載せれば終わりではなく、それをしっかり告知することも忘れないようにしてください。
このように、特別なスキルや機材がなくても、工夫次第で十分に効果的な動画は制作できますので、もしまだ社内報に動画を取り入れていない場合は、あまり肩に力を入れず、少しずつ始めてみることをおすすめします。

音声・BGMのチカラを活かす
社内報における動画において、その効果を最大化する極めて重要な要素の一つが音声・BGMです。
これまでにもお伝えしてきましたとおり、音声の持つ「表情や感情を伝える力」や、BGMによる「雰囲気や空気の演出」は、紙やWebの記事では不可能であり、加えて、情報の受け取り方に大きな影響を与えることができるため、音声とBGMを活かすことこそが、動画を取り入れる最大の効果だといっても過言ではありません。
そこで、ここからは改めて音声とBGMに注目し、もう少し深掘りをしながら、その活用ポイントを3つに分けて紹介します。
1.声のトーンや話し方で「人となり」を伝える
経営者メッセージや社員インタビューなどにおいて、話す内容だけでなく、声のトーンや間の取り方からもその人らしさがにじみ出ます。
たとえば、
柔らかく落ち着いた声:親しみやすさや安心感
明るくテンポの良い声:活気や前向きな印象
少し詰まりながらも丁寧に話す:誠実さや真剣さ
といったように、言葉にしていない情報も伝わるのが、動画の持つ力です。
特に社内報では、その人の人柄を伝えることで、より大きな共感を生みだすことが期待できます。
2.BGMで「雰囲気」や「感情の動き」を演出する
動画を見ているとき、何気なく流れているBGMですが、実はそれが、視聴体験の印象を大きく左右します。
明るく軽快な音楽:楽しさや親しみやすさ
ゆったり落ち着いたBGM:誠実さや安定感
ドラムやシンセの効いたリズム:期待感やスピード感
これらのBGMは、動画の目的や伝えたい印象にあわせて使い分けることで、より「伝わる動画」に仕上がります。
3.無音でも意味が伝わる工夫との両立
「声や音が伝えるものが大事」とはいえ、実際の視聴環境では音声をオフにして動画を見る方もたくさんいらっしゃいます。
社内での視聴は特にその傾向が強く、「音なしでも内容が分かる構成」が必要です。
そのためには、
・字幕・テロップで話している内容を補完する。
・BGMやSE(サウンド・エフェクト、効果音)がなくても「意味が伝わる流れ」を意識して構成する。
・音声があってもなくても満足度の高い動画に仕上げる。
音声は動画の最大の強みの一つですが、視聴のハードルを下げるという点で、字幕やテロップを取り入れることは、非常に重要な取り組みといえます。
このように、社内報における動画は、単に「動く」コンテンツである以上に、「声」や「音」によって、視聴者の感情に働きかけることができます。
そして、音声とBGMの工夫次第で、動画はただのお知らせから脱却し、「記憶に残る」ものへと進化していきます。
動画社内報を成功させるために
最後に、動画社内報を成功させるポイントをお伝えします。
まず、動画の社内報や動画のコンテンツづくりにおいて最も重要なことは、他のツールと変わらず、「読者」の視点に立って、視聴者である社員の反応や意見を取り入れて、適宜適切にPDCAを回し、動画の内容や見せ方のレベルアップを図るとともに、安定的に運用できる方法を模索し続けながら、社内に動画を見る風土や文化を築き上げていくことです。
そのためにも、以下のような姿勢で臨むことをおすすめします。
「作品」ではなく「機能」と捉える
動画を作り始めると、紙やWebとは違うワクワク感があります。
そのため、ついつい「かっこよく編集しなければ」といった考えや、「もっと見栄えの良い動画を作りたい」と考えてしまいがちです。
けれども社内報における動画の本質は、「魅せる」ことの前に「伝わる」ことが何よりも大切です。
特に社内報の場合は、お金や時間をかけて作ったように見えてしまうと、反感が出る可能性もあります。
そのため、「手づくり感」の残った動画の方が、社員の皆さまに親近感を抱きながら見ていただけることも少なくありません。
ですので、社内報の動画は個人の「作品」としてのクオリティを追求する前に、まずは伝えるべきことが「伝わる」といった、「機能」としての効果やクオリティを追求することが大切です。
成果を「視聴回数」だけで測らない
KPIや業務の評価指標として「再生数」に目が行きがちですが、社内報の動画では、数字だけでは測れない効果も多く存在します。
たとえば、
・「あの動画見ました」といった会話のきっかけが生まれた
・動画に登場した社員が他部署の人に声をかけられた
・経営者のメッセージに声のトーンや温度が加わり、反応が変わった
といったような、関係性の変化や共感の広がりこそが、動画を取り入れる本質的な成果です。
数値ももちろん大切ですが、数値だけに捉われず、動画を取り入れたことによって、社内にどんな変化が生まれたのか、これまでにはないような影響を社員に与えることができるようになったかといった点も、しっかり捉えていく姿勢と、それを把握するためのアンケート調査などの取り組みを推し進めることも、成果を正確に測る上で、極めて重要な視点と言えます。
社員参加型コンテンツで「当事者意識」を生む
動画視聴を定着化させ、社内の新しい風土や文化にしていくためには、動画を見てもらうだけでなく、「出演」していただくことも重要です。
そのために、たとえば数珠つなぎ型の企画で、さまざまな社員に登場していただいたり、部署紹介企画を「自撮り紹介」といった、参加型企画にするなど、企画としての工夫を行います。
「完璧さ」よりも大切な動画社内報の成功の鍵
動画を社内報に取り入れることは、あくまでも社内コミュニケーションの活性化や、その先にある従業員エンゲージメントの向上に対する一つの「手段」であり「機能」です。
ただ、社内の人と人を「より広く」「より深く」「より立体的」につなげるに際して、その手段や機能による効果は、現時点ではまだまだ計り知れません。
さらに、今後も働き方や社員の価値観の多様化の進展や、バックボーンの広がりが予測されるなかで、動画の可能性は、今よりももっと広がっていくと考えられます。
そのような、今後に向けて期待が膨らむ動画ですが、動画を取り入れることによる成果や効果は、他のツールと同じように、一朝一夕で得られるものではなく、継続的にコツコツと進めていくことが必要です。
まずは「完璧さ」よりも、「取り組みやすさ」や「続けやすさ」をもとにスタートして、少しずつ改善、改良を進めていくことが、動画社内報を成功させる鍵と言えます。

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
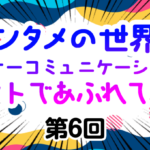
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
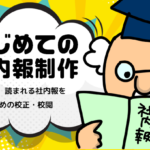
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
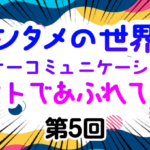
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

