QRコードのリスクと対策
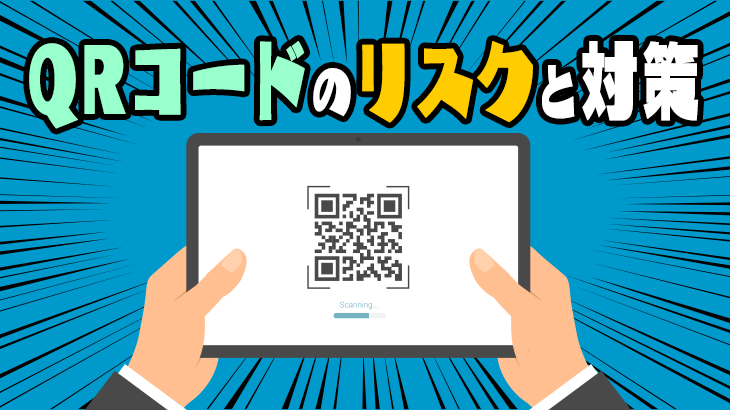
QRコードは、手軽に情報へアクセスできる手段として、企業や個人の間で広く活用されています。
アクセスしたいURLや連絡先情報、店舗情報などを簡単に共有できることから、顧客向けプロモーションや社内資料など、さまざまなシーンで利用されています。
しかし、QRコードの手軽さの裏には、悪意のある第三者が不正に利用するリスクも潜んでいます。
特に、企業や団体がQRコードを共有する場合は、意図しない形でユーザーが不正なサイトに誘導されてしまうなどのトラブルが発生することも少なくありません。
この記事では、実際の事例を交えて、QRコード利用時の失敗例とその原因、そして安全にQRコードを生成・共有するための具体的な対策について解説します。
QRコードの共有によるリスク事例
最近では、QRコードを悪用した事件がいくつか報告されています。
ここでは、その一部の事例をご紹介し、どのようなトラブルが起きているのかを具体的に見ていきましょう。
ケース1:いなげや
関東地方を中心に展開するスーパーマーケットチェーン「いなげや」では、一部店舗のチラシに記載したQRコードが、偽のWebサイトに誘導される事件が発生しました。
この偽サイトにアクセスしたユーザーは、個人情報を入力させられ、データが不正に取得される危険にさらされました。
ケース2:オートバックス
カー用品店「オートバックス」でも、公式のQRコードに見せかけた不正なQRコードが拡散され、ユーザーが偽サイトへアクセスしてしまう事態が起こりました。
公式サイトだと思い込んでアクセスしたユーザーが被害に遭うという、企業イメージにも影響を与える深刻なトラブルに繋がりました。
ケース3:学習院大学
学習院大学では、キャンパス内に設置したQRコードが不正に操作され、不正なサイトへ誘導される事案が確認されました。
学生や来訪者にとっても安心して利用できるはずの場所で発生したことが、さらなる問題を引き起こしました。
なぜ失敗が起きたのか?原因と分析
これらの事例を通じて明らかになったのは、QRコードの運用管理が徹底されていなかったことや、セキュリティ対策が不十分だった点です。具体的な失敗の原因をいくつか見ていきましょう。
要因1:QRコードの生成の甘さ
どのケースも、QRコードそのものの問題というより、作成された2次元バーコードの元となったURLに問題があると推察されます。自社で管理していない外部の「短縮URL作成プログラム」を利用してQRコードを発行すると、意図しないページ(URL)を経由させられたり、全く別のページ(URL)にジャンプさせられたりするリスクがあります。
要因2:セキュリティチェックの不十分さ
QRコードの生成後に放置してしまうと、何年も使い続けられてしまうことがあります。これにより、古いQRコードのURLが不正に改ざんされても気づかないまま、使用されるリスクが高まります。
また、印刷物など更新が難しい媒体で使用されたQRコードも、長期間そのまま利用されることが少なくありません。これにより、不正なアクセスが発生した場合にも気づかず、そのまま使用され続ける可能性があります。
安全なQRコードの生成方法と共有時の対策
QRコードの不正利用を防ぐためには、以下のような対策が有効です。
対策1:信頼性の高いQRコード生成ツールの活用
無料のQRコード生成ツールも多く存在しますが、セキュリティに配慮されていないものもあります。Google QRコードジェネレーターや信頼性の高い業者のツールを利用することで、生成したQRコードが第三者に改ざんされるリスクを低減できます。
また、短縮URLは、スペースを節約できる利点がある一方で、URLの内容が見えないためにフィッシングやマルウェアの温床になりやすいというデメリットがあります。QRコードを利用する際は、できるだけ短縮URLを避け、フルURLを使用するのが理想的です。
QRコードを安全に生成できるサイト
Google QRコードジェネレーター
Googleが提供するChromeブラウザの機能拡張。
クルクルManager
QRコードを開発したデンソーウェーブが携わるQRコード生成サイト
Adobe Express
Adobeが提供するオンラインデザインツール内の機能。
対策2:コード生成後のURL確認
QRコードを使用する際は、必ずリンク先のURLが正しいか確認しましょう。できれば、QRコードの案内を終了後も定期的にチェックできると、さらに良いのですが難易度が高くなるため、使用期限を設定して、期限内のチェックを徹底すると良いでしょう。
また、アクセス解析によるモニタリングを導入しても良いでしょう。不正アクセスがあればすぐに気づき、対応することが可能です。Googleが提供する「キャンペーンURLビルダー」でUTMパラメータを付与することで、効果測定にも利用できます。
急にアクセス数が増加したり、アクセス元が特定の地域に偏った場合は、リスクが高まっている兆候かもしれません。こうした異常が発生した際に迅速に対応できる体制を整えることで、不正アクセスを早期に発見し、対処できます。
WEBのセキュリティ対策やお困りごとは、りえぞん企画へお問い合わせください
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/inquiry/
対策3:適切な掲示と管理方法
公共の場や誰でもアクセスできるオープンな場にQRコードを掲示する場合は、利用期限や掲示期間を明確にし、管理責任者を決めて更新・監視を行うことが重要です。
また、印刷物に掲載する際には、QRコードが不正利用されないよう、企業ロゴや使用目的を明示したデザインを採用することも効果的です。

おわりに
QRコードは、利便性の高さから日常生活のあらゆる場面で活用されていますが、その反面、適切な管理と対策が不十分だと、悪意ある第三者に悪用されるリスクも潜んでいます。本稿で紹介した事例や対策を参考に、QRコード利用の際には常にセキュリティ意識を持ち、安全な運用を心がけましょう。企業としても、顧客や社員に安心してQRコードを利用してもらうために、情報管理体制を強化し、リスク軽減に努めることが重要です。
→広報担当者が見落としがちなWebフォームの盲点とその対策はこちらから
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h02_10082/3564
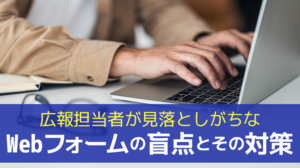

関連記事
-
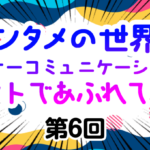
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
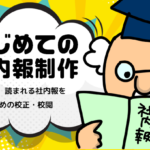
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
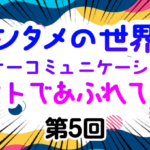
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...
-
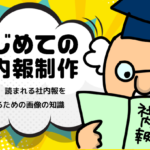
【はじめての社内報制作】 第10回 読まれる社内報をつくるための画像の知識
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-

社内報は内容が同じでも、「読まれる社内報」と「読まれない社内報」に分かれますが、その違いが ...

