【はじめての社内報制作】 第6回 読まれる社内報の原稿の作り方
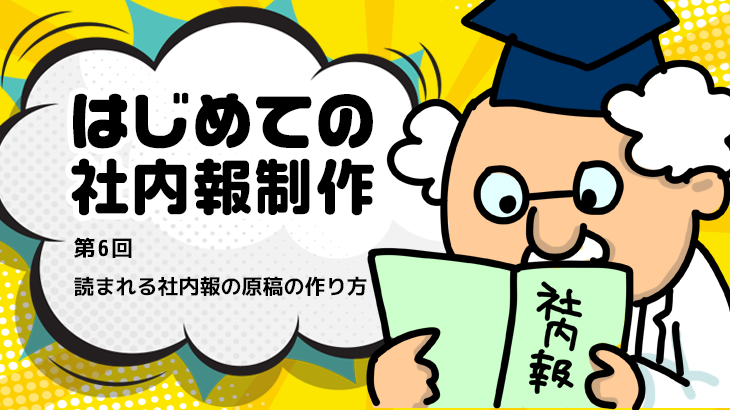
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。
シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが楽しく自信を持って社内報制作に取り組めるようサポートすることを目的に、社内報制作の基本から、読まれる社内報にする秘訣までを、できる限りわかりやすく解説してまいります。
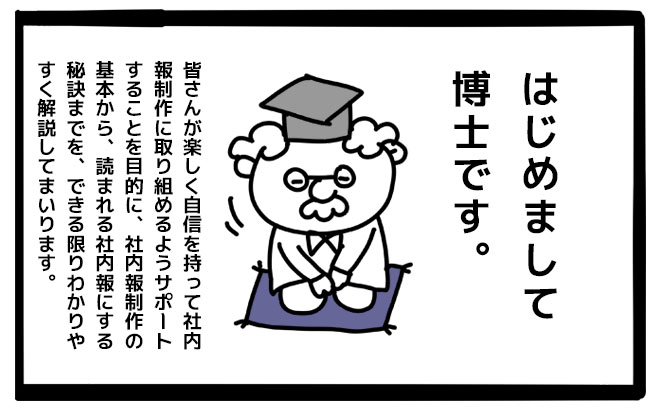
目次
記事を読み終えた後に「また読みたい」と思うような原稿を作る
<上司>社内報づくりがずいぶん板についてきたな。
<山田>ありがとうございます!
(確かにそれなりには作れるようになったけど、もっと良いものを作りたい・・・)

読み続けてもらえる原稿とは
<博士>最近は社内報づくりに燃えておるようじゃのう!
<山田>博士! そうですね。
社内報づくりに慣れてきたことで、やる気も湧いてきました。
<博士>ほう!ますます頑張れよ!
じゃあな。
<山田>ありがとうございますって、博士!ちょっと待ってください!!!
<博士>ん?
まだ何か問題があるのかい?
<山田>はい。
慣れれば慣れるほど、もっと良いものを作りたいと思うようになってきたんです。
特に、文章のレベルを高めたいというか、もっと読まれる文章にできないかと考えているんです。
<博士>ほう。
どうしてそんなふうに考えておるんじゃ?
<山田>はい。
今のレベルのままでは、みんなに興味を持って読み続けてもらえなくなるというか、いつか飽きられてしまうんじゃないかと感じるんです。
それに、発行後に改めて読んでみると、どの文章も説明的で、面白みがない気がするんですよね。
<博士>なるほど。
そもそも、興味を持って読み続けてもらう原稿を作るためには、何をすれば良いと考えておるんじゃ?

<山田>えーっと…、読者の関心ごとに沿った内容の原稿を書くことですかね?
<博士>パッとしない答え方じゃがその通りじゃ。
それと、興味を持って読み続けてもらうために何よりも大切なことは、読んでくれた人が、記事を読み終えた後に「また読みたい」と思うような原稿を作ることじゃぞ。
<山田>なんだか禅問答のように感じるのですが・・・
<博士>いやいや、そうではないぞ。
よし、それじゃここからは、読んでくれた人がまた読みたいと感じるようにするための、原稿への取り組み方について話していこうかのう。
<山田>ぜひお願いしたいです!
<博士>読まれる文章を書くために大切なことは、「誰に向けて書くのか」を明確にすることじゃよ。
「最も読んでほしい人」をターゲットにする
<山田>あ!ターゲットの明確化ですね!
(確か、企画のことを聞いたときに教わったような・・・)
<博士>そのとおりじゃ。
社内報は社内の人が読むものじゃが、一口に「社員」と言っても、興味関心は人それぞれ違う。
例えば、工場のスタッフと本社の社員では知りたい情報が違うこともあるじゃろう。

<山田>そうですよね。
記事のテーマを決めるといった、企画を考えるときにも、どの読者層に向けて書くのかを意識することが重要だと言っていましたよね。
<博士>そのとおりじゃ。
<山田>けど、ターゲットって何を基準に決めれば良いのかが難しいなって思うんですが。
<博士>そんなに難しく考える必要はないんじゃよ。
ターゲットは、「この記事を誰に最も読んでもらいたいか」で決めれば良い。

<山田>なるほど。
つまり、書こうとしている記事が誰に響けば最も効果的なのかを考えて決めるということですね?
<博士>その通りじゃ。
<山田>でも博士、関心ごとと関連する内容や、興味のある内容でも、その記事を読むのが大変だったら途中で読むのをやめちゃいますよね?
<博士>なかなか鋭いのう。
読者は読むことに負担を感じたり、興味を持った記事でも、読むのがしんどそうだと感じると、その瞬間に読むのをやめてしまうんじゃよ。
読む負担を感じさせない原稿づくり
<山田>つまり、原稿は興味だけでなく、読む負担を感じないように書くことが大事だということですよね?
<博士>そのとおりじゃ。
<山田>読む負担を減らすためには、文章の量を減らせば良いといったことは想像できるんですけど、読みやすさってどうすればいいんですか?
<博士>そうじゃな。
例えば、一つひとつの文章を短く区切ったり、適度に改行を加えたりすることも効果的じゃよ。
あとは、パラグラフを適切な分量で区切り、小見出しを加えることで、その文章はぐっと読みやすくなる。
<山田>なるほど!
つまり文章を整理したり、小見出しでまとめることで、読みやすくなるということですね?
<博士>そうじゃ。
特に小見出しは、目線の流れをスムーズに誘導したり、リズムよく読めるようにするために、欠かすことができない要素なんじゃよ。
記事の冒頭で「匂い」を持たせる
<山田>ありがとうございます!
なんとなく、読んでもらえる原稿を書けそうな気になってきました。
<博士>おいおい、それはまだ早いぞ。
<山田>え? そうなんですか?
<博士>そもそも文章というのは、読み進めなければ何が書いてあるかわからんものじゃ。
たとえターゲットを定めたり、そのターゲットが関心を持っている内容や、興味のある内容だったりしても、その前にまず、読者がこの記事を読み進めたいと思わなければ、たとえ関心や興味がある内容でも、最後までは読まんじゃろ?

<山田>確かにそうですね…。
でも、どうすれば読者が「読み進めたい!」って思うような原稿にすることができるんですか?

<博士>そうじゃな。
記事に「匂い」を持たせるんじゃよ。
<山田>「匂い」?
<博士>そうじゃ。
もう少しわかりやすく言うと、その記事を読み進めていくことで得られるお得感を、読者ができるだけ早い段階で察知できるようにすることじゃ。
<山田>それって、記事の冒頭に内容の要約や、読むメリットを書けばいいってことですか?
<博士>それができれば良いんじゃが、読むメリットは人によって違うじゃろ?
なので、あくまでも「匂い」といった、読者が「おっ? これはなんだか気になるぞ」と思えるようなことを、記事の冒頭で醸し出すようにするんじゃよ。
<山田>ああ!
つまり、最初にこの文章を読み進めれば、こんなことが得られるんじゃないかな?ということや、これは面白そうだぞ?と感じられる、魅力のようなものを感じさせるということですね?
<博士>例えば、ある研修制度について語る記事でも、
社員のスキルアップを目指して、当社では新たに「〇〇研修制度」を導入しました。これにより、社員が専門スキルを身につけ、より成長できる機会を提供してまいります。といった語り口よりも、参加した社員から「もっと早くに取り入れてほしかった」と嬉しいクレームが出ている、新たにスタートした「〇〇研修制度」とは、どのような効果が得られるのか?その秘密に迫ります。
とした方が、何かただならぬ匂いを感じるじゃろ?

<山田>確かに!
そうやって、説明的な文章ではなくって、「匂い」のような無意識的な感覚で期待を感じ取ってもらえるような書き振りにすれば、最後まで読んでみようという気持ちを持ち続けてもらえそうに感じます。

<博士>さらに言うと、原稿はその匂いである期待を最後まで裏切らないことも重要じゃ。
そして、記事を読み終わったあとに、期待通り「役に立った!」「面白かった!」「意外だった!」と思わせることができれば、「また読みたい」と思うってもらえて、次回の社内報も手に取ってもらいやすくなる。
<山田>それって読後感ですね?
つまり、記事の冒頭の期待という匂いと、読み終えたあとの読後感を一致させることが大切だということですね?
<博士>その通りじゃ。
<山田>記事を最後まで読んでもらって、「また読みたい」と思ってもらえるように、期待感と読後感を考えて文章を書くということはわかりました。
けど、それって見出しとも関係しますよね?
<博士>今日はなかなか鋭いのう。
まさに見出しやリード文も、期待感や読後感に大きく影響する要素じゃが、その話をすると長くなるので、それはまたの機会に話すとしようかのう。

<山田>え?!ま、待って!!!
これで終わりですか??博士ー!
博士と山田くんの社内報作りの物語はまだまだ続いていく・・・・

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
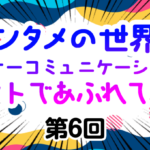
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
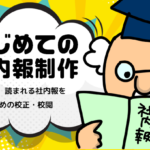
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
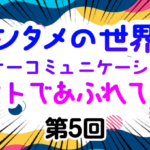
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

