【Gmail新ガイドライン対応】eメール社内報完全ガイド
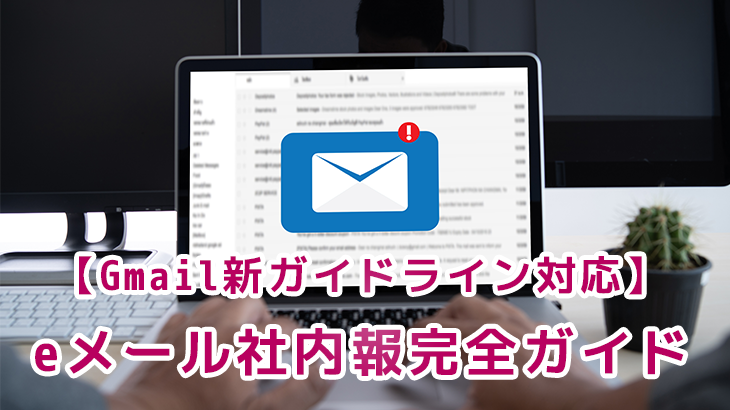
2024年のGmailガイドライン改訂で、eメール社内報(社内報メールマガジン)の配信に悩まれている方も多いのではないでしょうか?
「いつも通り送信したのに、届いていないと言われた…」
「迷惑メールフォルダに振り分けられているみたい」
「対応しなければと思いつつ、何から始めればいいか分からない」
「せっかく作った記事が読まれないのは勿体ない」
本記事では、このような悩みを抱える社内報担当者の皆さんに向けて、具体的な対応方法をご紹介します。
目次
なぜ今、対応が必要なのか?
2024年、Gmailは迷惑メール対策を強化するため、メール送信者向けのガイドラインを大幅に改訂しました。この変更により、これまで問題なく届いていたeメール社内報(社内報メールマガジン)にも影響が出始めています。想定される影響として、以下のようなケースが考えられます。
- メールが受信トレイではなく、迷惑メールフォルダに振り分けられる
- 最悪の場合、メールが完全にブロックされ、届かなくなる
- 重要な社内情報が適切にメンバーに届かず、業務に支障をきたす
- 社内コミュニケーションの質が低下する
- 情報伝達の遅延により、業務効率が悪化する
近年、主要なメールサービスは軒並み迷惑メール対策を強化しており、企業のメール配信に大きな影響を与えています。
社内報の配信停止や、重要な情報伝達の遅延といった事態を避けるためにも、全社的な対応が急務です。
Yahoo!も同様の厳格な迷惑メール対策を実施しており、GmailやYahoo!を利用する社員が多い企業では、早急な対策を検討しましょう。
早期にガイドラインに沿った対策を実施することで、迷惑メールと誤認識されるリスクを減らし、安定した情報配信を実現できます。
また、企業の信頼性向上にもつながります。
対応の3つのステップ
Step 1:技術面の対応を確認する
まずは、IT部門に以下の3つの認証設定が完了しているか確認しましょう。
1,SPF設定
メールの送信元を証明する仕組み ・なりすましメールの防止に効果的 ・送信サーバーのIPアドレスを登録 ・複数のサーバーから送信する場合は、すべてのIPアドレスを登録する必要あり
2,DKIM設定
メールに電子署名を付与 ・送信元ドメインの正当性を証明 ・秘密鍵と公開鍵のペアを使用 ・定期的な鍵の更新が推奨
3.DMARC設定
上記2つの認証結果を確認 ・不正なメールへの対処方法を指定 ・段階的な導入が推奨(監視→隔離→拒否) ・レポート機能による追跡が可能※これらの設定には、専門的な知識が必要です。必ずIT部門と相談しながら進めましょう。
Step 2:メール配信の実務改善
①メール配信ツールの活用を検討
以下のツールは、いずれもGmailの新ガイドラインに対応しており、無料トライアルが可能です。
▼Benchmark Email
50万社以上が利用する実績 ・デザイン性の高いテンプレートが豊富 ・直感的な操作性が特徴 ・A/Bテスト機能搭載 ・詳細な配信レポートあり
▼配配メール
日本企業向けの使いやすい機能 ・リーズナブルな料金設定 ・初心者でも扱いやすい ・きめ細かなサポート体制 ・日本語マニュアル完備
▼ブラストメール
シンプルな操作性 ・充実した分析機能 ・豊富なテンプレート ・配信スケジュール管理が便利 ・モバイル対応が充実

②メールの品質向上のポイント
Gmailの送信ガイドラインは、単に技術的な要件ではなく、受信者に価値ある情報を届けるためのマナーでもあります。メール内容を工夫することで、ガイドラインに沿った質の高いメールを作成し、より効果的なメールマーケティングを実現することができます。
件名の工夫
わかりやすく、興味を引く件名にしましょう。一般的に、件名は20文字以内が良いとされています。また、メールを開いてみたくなるキーワード(トップメッセージ、重要)を含めると良いでしょう。
あまり過度な装飾(「!!!」の多用など)は避け、実用的な内容を端的に表現することを心がけましょう
本文作成のコツ
重要な情報を冒頭に配置し、箇条書きを効果的に活用すると良いでしょう。
また適切な文章量を意識(1記事500文字程度)したうえで、その段落の内容が端的にわかる見出しを効果的につけます。
また、1メールにつき1トピックにすると読者の負担が減り、開封率が向上します
画像使用のルール
画像の容量は最小限に(1枚当たり100KB以下推奨)にしましょう。外出先でひらく場合もあり、通信速度が遅いと表示に時間がかかってしまいます。また画像にはalt属性(画像の説明文)を必ず設定しましょう。
信認性やアクセシビリティの観点から、画像内にテキストを配置することはできるだけ避け、やむを得ない場合でもテキストとして記載しておくことをお勧めします。
Step 3:継続的な改善
古くなったアドレスや、退職された方のアドレスを定期的に削除することで、配信効率を上げることができます。
定期的なメンテナンス
・配信リストの整理(月1回推奨)
・不達アドレスの確認と対応
・開封率、クリック率の分析
・バウンスメールの管理、配信頻度の最適化
・読者のフィードバック収集、A/Bテストの実施、ベストプラクティスの文書化
運用のポイント
eメール社内報(社内報メールマガジン)は、単なる情報発信ツールではなく、社員一人ひとりにとって価値ある情報を届けるための重要なコミュニケーションツールです。
そのため、受信者視点に立ち、必要な情報を必要なタイミングで、読みやすく分かりやすい形で配信することが求められます。
定期的に配信効果を測定し、開封率やクリック率の変化を分析することで、より効果的なeメール社内報(社内報メールマガジン)へと改善していくことが重要です。
具体的には、コンテンツ別の反応や時間帯、デバイス別の閲覧状況などを詳細に分析し、改善点を見つけることが必要です。
また、eメール社内報(社内報メールマガジン)配信にはIT部門との連携が不可欠です。
月次での状況確認会議を定期的に実施し、新技術導入やセキュリティ対策の見直し、システムパフォーマンスの確認など、技術的な側面からも継続的な改善を図る必要があります。
さらに、社員向けのツール使用方法の勉強会や、トラブル対応フローの整備も重要です。
さいごに
Gmailガイドラインの変更は、一見すると負担に感じるかもしれません。
しかし、これを機にeメール社内報(社内報メールマガジン)の質を向上させ、より効果的な社内コミュニケーションを実現するチャンスと捉えましょう。
本記事で紹介した対策を一つずつ実施することで、確実にメールが届く環境を整えることができます。
まずは自社の現状を確認し、優先順位の高い項目から着手することをお勧めします。
分からないことがあれば、一人で抱え込まず、IT部門に相談してください。
チームで協力しながら、より良い社内コミュニケーションの実現を目指しましょう。

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
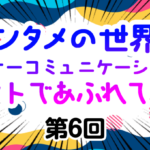
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
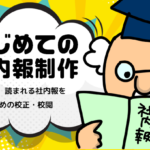
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
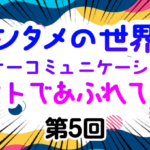
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

