生成AIの登場で、社内報担当者が会社の「顔」を創る時代に

生成AIの登場によりWebサイトからの検索流入が減少し、企業のWebコンテンツは、これまでの自己紹介型や課題解決型から大きな変化が求められています。このような状況で、社内報担当者の力が、会社の対外的な「顔」を形作る上で、かつてないほど重要になってくるのではないかと、考えています。
目次
Webサイトは「関係構築」の場へ
「最近、Webサイトからの問い合わせが減った」
「SEOの費用対効果が見合わなくなってきた」
そんな声を最近よく耳にします。
かつてのWebサイトは、会社の「自己紹介」の場であり、検索エンジンからの流入が最大の集客源でした。
しかし、生成AIは、ユーザーの質問に対し、Web上の膨大な情報を瞬時に解析し、要約して直接回答を提示します。
これにより、ユーザーはサイトを訪問することなく疑問を解決できるため、結果としてサイトへの検索流入が減少してしまいます。
この変化は、企業にとって、Webサイトの役割そのものを再定義する必要があることを突きつけています。もはや、単に会社概要や製品情報を並べるだけの「自己紹介サイト」では、競合との差別化も、顧客との深い関係構築も難しくなっています。

「AI最適化」の先に求めるもの
では、私たちは生成AIの時代に、Webコンテンツとどう向き合えばいいのでしょうか? AIに「選ばれる」ためのコンテンツ最適化、いわゆる「AI向けコンテンツ最適化」や非公式ながら「GSEO(Generative AI Search Optimization)」と呼ばれる取り組みは確かに存在します。これは、AIが正確に情報を抽出し、回答に利用しやすいよう、E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を極限まで高め、独自性や構造化されたデータを提供する、非常に労力のいる作業です。
しかし、たとえその労力を投じてAIに参照されたとしても、ユーザーが直接サイトを訪れることなく情報だけを得てしまう「ゼロクリック検索」が増える現状では、「かけた労力に見合う成果が得られないのでは?」と感じるのも無理はありません。
ここで、私たちが立ち返るべきは、Webサイトの「本質的な役割」です。
企業活動が利益追求だけでなく、社会課題解決へと重心を移し、顧客やパートナーとの「協働」が不可欠となる現代において、Webサイトは、「人と深い関係を築き、共感を呼び、共に未来を創るためのプラットフォーム」へと進化する必要があります。
社内報の真価
この視点に立った時、私たち社内報担当者が日頃から紡ぎ出しているコンテンツの価値が、かつてなく輝きを放ちます。なぜなら、社内報が持つ最大の強みは、「らしさ」「ストーリー」「共感」だからです。
社内報は、社員一人ひとりの情熱や挑戦、チームの絆、企業の文化、社会貢献への取り組みなど、データや製品スペックだけでは伝えきれない「生きた情報」で溢れています。これらは、AIが提供する事実情報だけでは満たせない、人の心を動かす情報です。
考えてみてください。皆さんが取材し、書き起こしている社員の奮闘記、部署の温かい雰囲気、社内イベントの盛り上がり、これらすべてが、外部の潜在顧客、未来の仲間(採用候補者)、大切なパートナー、そして株主の方々にとって、その企業を「知る」だけでなく「好きになる」「信頼する」きっかけとなるのです。
「コンテンツ共創」のハブとしての社内報
従来のWebコンテンツは、マーケティング部門や広報部門が主導し、いかに「検索エンジンに評価されるか」に注力しがちでした。しかし、これからのWebサイトは、もっと多様なタッチポイントから興味を持ってくれた「人」が、より深く会社を知り、共感し、最終的に「この会社と繋がりたい」「この会社で働きたい」と感じるための採用サイトのようなアプローチへと変わっていくべきです。
その際、社内報担当者は、まさにその「らしさ」をWebサイトに注入する最前線に立つことになります。
例えば、
「社員の挑戦」シリーズ
社内報で紹介した社員のストーリーをWebサイトで公開することで、採用候補者が「この会社でなら、私もこんな風に挑戦できるかも」と具体的にイメージできるようになります。
社会貢献活動レポート
社内報で報告したNGOとの協働やボランティア活動の様子を社員の思いと意義にフォーカスすることで、企業の社会的責任(CSR/ESG)への真摯な取り組みを示す強力なコンテンツとなり、共感する顧客やパートナーを惹きつけます。
パートナーシップ最前線
社内報で取り上げたパートナー企業との協業事例や、プロジェクトを成功に導いた対談記事は、Webサイト上で「共に未来を創造する協働」の具体例として輝きます。また、定番企画である経営層と専門家との対談も良いでしょう。対談を通じて、深い洞察や業界への影響力を示すことで、新たなパートナーシップの扉を開く可能性があります。
これらのコンテンツは、決して「SEOのため」だけにつくるものではありません。
「対面で出会ったお客様が、もっと会社を知りたいと思った時に見る場所」
「広告やSNSで会社の存在を知った人が、本当に信頼できる会社か確かめる場所」
「パートナー企業が、協業の可能性を探る場所」
「株主が、企業の持続的成長の源泉を探る場所」
「従業員やその家族が、自身の会社を誇りに思う場所」
これらの多様な目的を持つ人々に対して、社内報が持つ「生の温かさ」をWebサイトで届けること。
これこそが、これからのWebコンテンツの重要な役割となるのではないでしょうか。

新たな挑戦への第一歩
生成AIは、私たちの情報収集の方法を変えましたが、人々の「共感したい」「信頼したい」「物語に触れたい」という根本的な欲求は変わりません。むしろ、AIが事実を効率的に提供する時代だからこそ、人間味あふれる「心」を伝えるコンテンツの価値が際立つのです。
社内報担当者の皆さん、皆さんが日々見つめている「会社のリアル」には、Webサイトの「顔」を刷新し、企業とステークホルダーの間に真の「関係性」を築くための、無限の可能性が秘められています。
ぜひ、日々の社内報制作の中で、
「これは、Webサイトでどんな風に伝えられるだろう?」
「この社員の情熱は、外部の誰の心に響くだろう?」
そんな視点を加えてみてください。
私たち社内報担当者がWebサイトの「心」を創り、会社の新しい「顔」を形作る。そんなワクワクする時代が、今、まさに訪れようとしているのではないでしょうか。

関連記事
-
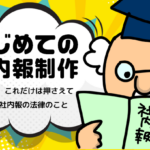
【はじめての社内報制作】 第12回 これだけは押さえておきたい社内報の法律のこと
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
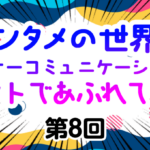
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第8回 “静かなる革命”の予感
皆さんは、藤原ヒロシ氏が2024年12月にスタートさせた『QUIET』というYouTube ...
-
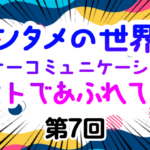
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
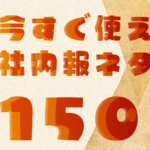
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...

