【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
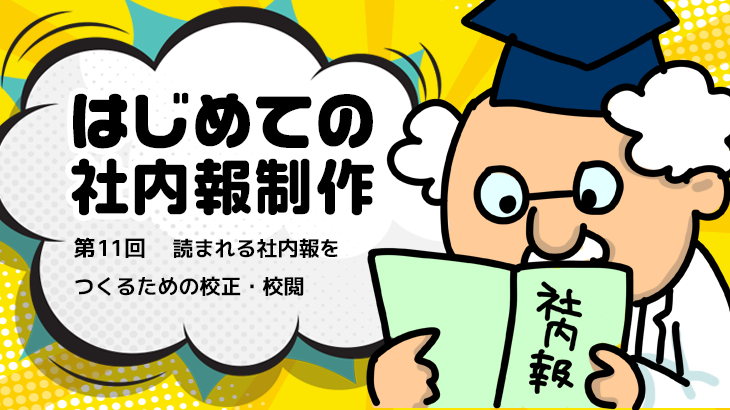
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。
シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが楽しく自信を持って社内報制作に取り組めるようサポートすることを目的に、社内報制作の基本から、読まれる社内報にする秘訣までを、できる限りわかりやすく解説してまいります。
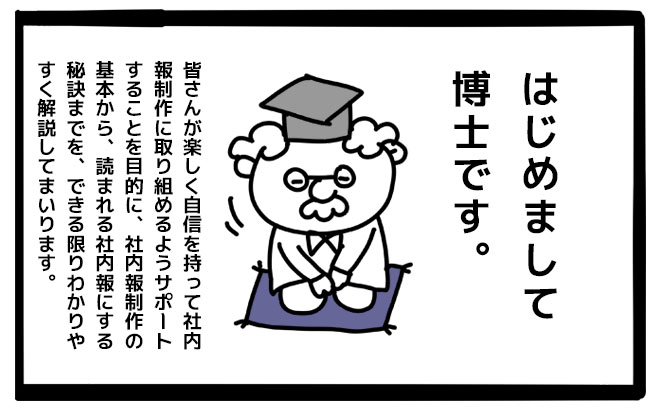
目次
校正・校閲は社内報の信頼性を守る最後の砦
<上司>校了したんだな?今回もお疲れさん!
<山田>ありがとうございます・・・。


校正・校閲は単なる文字の確認作業ではない
<博士>どうした?
顔色が曇っておるぞ?
<山田>あ、博士。
実はさっき、今回の号が校了を迎えたんですけど、誤字や脱字がないか心配で・・・。
<博士>なんじゃ?
ちゃんと校正しておらんのか?
<山田>いえ、校正はしっかりやりました。
けれども、校了のタイミングになると、「これで本当に大丈夫かな……」って。
いつもこんな感じで印刷された社内報を確認するまで不安が残るんですよね。
<博士>それは多くの担当者が抱える悩みじゃな。
<山田>やっぱりそうですよね?
<博士>こればかりは仕方がない。
と言うのも、「校正・校閲」は単なる文字の確認作業ではなく、社内報というメディアの信頼性を守る最後の砦なのじゃからな。
<山田>信頼性を守る最後の砦ですか?
<博士>そうじゃ。
誤字脱字を直すことは手段で、校正や校閲の本当の目的は、社内報というツールの信頼を守ることなんじゃよ。
校正・校閲は「信頼を守る」ための行為
<山田>信頼を守ること?
<博士>そうじゃ。
社内報は、会社としての公式なメッセージを伝えるメディアじゃからな。
<山田>なるほど。
確かに小さな誤りでも、「これ間違っているんじゃない?」と感じさせてしまえば、その記事の情報に対する信頼が損なわれてしまいますね。
<博士>記事だけではなく、社内報に対する信頼も損なわれてしまい、さらには会社が発信する情報やメッセージに対する信頼も揺らぎかねんのじゃよ。
<山田>そう考えると社内報の校正や校閲って、会社にとってものすごく重要な業務なんですね。
<博士>その通りじゃ。

<山田>ところで、そもそもの疑問なんですけど、校正と校閲って何が違うんですか?
校正・校閲の違いと役割
<博士>「校正」と「校閲」の違いは確かに混同しがちじゃが、この違いをしっかり理解しておくことも、校正や校閲をする上で、極めて重要なことなんじゃよ。
校正:文字や表記の誤りを正す作業(例:誤字・脱字・表記揺れ)
校閲:内容の正しさや論理性を確認する作業(例:事実確認・整合性・語句の適切さ)
<山田>つまり、校正は見た目の整合性、校閲は中身の妥当性を整えるってことですね。
<博士>その通り。
両者を意識的に切り分けることで、確認の精度がぐんと高まるぞ。
「型」を持って効率と精度を両立させる
<山田>あと、社内報の校正・校閲を効率化する方法があればなって思うんですが。
<博士>毎号ゼロから完璧を目指すと負担が大きくなりすぎてしまう。
そうならないようにするためには、ある程度の「型」を持つことが重要なんじゃ。

<山田>「型」ですか?
<博士>そうじゃ。
例えば校正の手順を決めておくというのも一つの手なんじゃよ。
<山田>手順を決めておくってどういうことですか?
<博士>一つの例をあげると、「人名」「肩書き」「部署名」のチェックから始めるという方法じゃ。
これらは、情報の信頼性はもちろん、社内報に出ていただく方の信頼とも関係する最も重要な要素と言える。
<山田>つまり、効率化だけではなく品質を考える上では、そういった重要度の高いものから先に進めることが効果的だということですね?
<博士>その通りじゃ。
そのあと、表記統一表を使って、揺れや語彙の重複を避け、全体のトーンを整える。
そして記事で伝えたいことが伝わるかどうかといったことや、わかりやすく伝えることができているかといった視点で校閲を進め、最後に数値や日付、事実が間違えていないかをチェックするんじゃよ。
記事の安定性を高める「表記統一表」
<山田>表記の揺れって、毎回なんとなく気づいたら直してるんですけど、なんだか場当たり的で……。
<博士>そうならないようにするために、社内専用の「表記統一表」を作っておくと良いぞ。

<山田>表記のルールを予め決めて、まとめておくということですね?
<博士>そうじゃ。
たとえば以下のような項目を記載しておくと、校正作業が格段に効率化される。
表記統一表の主な項目例
年数表記:2025年・・・「令和」など元号は使わない
日付の書き方:7月1日(月)・・・7/1(月)などは不可
数字の表記:数字は半角で統一・・・「3」(全角)ではなく「3」(半角)
言い回し:「〜しています」・・・丁寧な語尾に統一
外来語・カタカナ語:「リーダーシップ」・・・一部略語は使用可(例:DX)
<山田>なるほど、こういうリストがあるだけで、迷いも手戻りも減らせて、記事の安定性も高められそうですね!
<博士>表記の揺れやバラツキがなくなるだけでも、読み手にとって格段に読みやすく、安心して読めるようになるんじゃよ。
<山田>表記統一表を作るときに、何を基準にすると良いんですか?
<博士>一般的には共同通信社の『記者ハンドブック』や、朝日新聞社の『用語の手引き』じゃ。
これらは表記ルールが網羅的にまとめられていて、言葉の使い方や送り仮名、略語や敬称の判断などにも対応しておる。
例えば
・「下さい」か「ください」か迷ったら?
・「ホームページ」と「Webサイト」はどちらが適切?
・数値の単位表記(%・km・人)に統一ルールはあるか?
など、ちょっとした言語の「迷い」をすぐに解決できる、まさに校正者のバイブルじゃな。
校正の精度を高める3つの習慣
<山田>他にも何か便利なテクニックとかってあったりしますか?
<博士>そうじゃな。
校正や校閲をするときの習慣を持つことも効果的じゃ。
<山田>習慣ですか?
<博士>校正や校閲といった技術は、習慣によって磨かれるんじゃ。
例えばこの3つを意識するだけでも効果は抜群じゃよ。
① 一度声に出して読む
黙読では気づけないズレや読み進める際の違和感を捉える。
② サイズを変えて印刷して読む
いつもと違うサイズやフォーマットにすることで「見慣れ」を防ぐ。
③ 他者の目を入れる
第三者校正を取り入れて客観的かつ新鮮な目で見てもらう。
心配や不安を活かして取り組む
<山田>博士、今回もありがとうございました。
校正や校閲の大切さが改めてわかったので、やる気が出てきました!
<博士>それは良かった。
校正・校閲という仕事は、原稿を完璧に仕上げることではない。
社内報を読者に安心して読んでもらう準備を整えることなんじゃよ。
<山田>どんな想いで書かれた記事なのか。
読む人にどう届いてほしいのか。
「信頼される媒体」であるために、どこまでやるべきか。
作業じゃなく、読者との信頼関係を築いていく仕事。
そして、それを守っていくための仕事ということですね?

<博士>何度も言うが、校正・校閲は社内報の信頼を守るの最後の砦じゃ。
そういった意味では、校了後の心配や不安は決してなくならない。
むしろ、心配や不安を感じるということが、社内報と読者である社員との関係づくりにしっかり向き合っている証拠だとも言えるんじゃよ。
<山田>確かにそうですね!
その考え方や気持ちを大切にして取り組んでいこうと思います!


関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
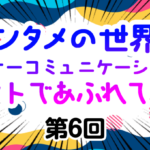
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
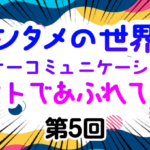
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...
-
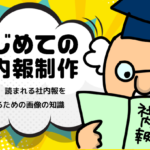
【はじめての社内報制作】 第10回 読まれる社内報をつくるための画像の知識
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...

