Web社内報デザイン成功のカギ
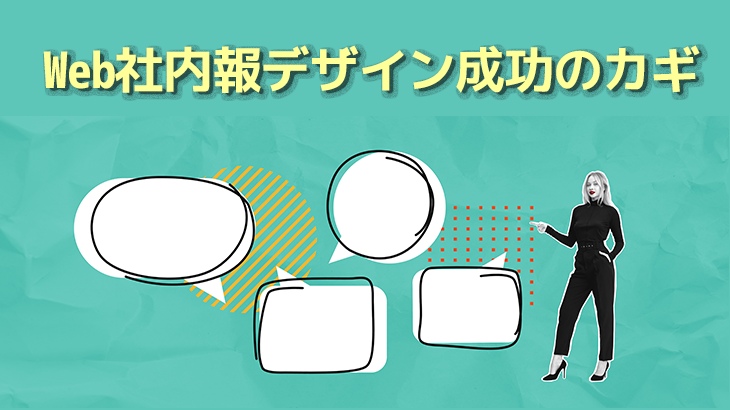
Web社内報は「見やすい」や「おしゃれ」だけでは見てもらえません。
本当に大切なのは、「読者との関係性」をどう設計するかという、デザインの本来の役割に立ち返って考えることです。
この記事では、Web社内報のデザインを考える上で大切な、デザインの本来の役割といった本質的な出発点と、見られるWeb社内報にするための具体的な考え方をお伝えします。
目次
読者との関係性から始めるWeb社内報デザイン
Web 社内報のデザインを考える際に、最初から「見栄えを良くするためにはどうすれば良いか」といった考えや、「どうすれば読みやすいデザインにできるのか」といった考えから出発していませんか?
実はこの考え方から始めても、その答えは見つかりません。
では、どうすれば良いのか。
何から考えれば良いのか。
それは、Web社内報と読者の間に「どのような関係を築くことができれば成功と言えるのか」を考えることです。
出発点は会社の「企業ブランド」から
Web社内報も会社の一つの「メディア」ですので、出発点は会社の企業ブランド。つまり、「この会社らしさ」を視覚的に表している企業ブランドのデザインマニュアルや、VIマニュアルをもとに考えることから始めます。
このブランドの軸を無視して、見てもらえるWeb社内報にするために、「親しみやすいデザイン」にしようとしたり、「柔らかい印象のデザインにしよう」と考えてしまうと、社内報だけが浮いてしまったり、会社と関係のないものに見えてしまうといった危険性があります。
ですので、Web社内報のデザインを考えるときはまず、自社のブランドがどのような価値観に基づいているかを丁寧に読み解いた上で、Web社内報は読者との間に「どのような関係を築くことができれば成功と言えるのか」を考えて、デザインの方向性のアタリをつけます。
ただ、Web社内報は他の外部向けツールと比べて、ある程度の柔軟性を持たせる必要があります。
その理由としては、社員の皆さまに親しみを持って見てもらえるツールにする必要があるからです。
イメージマップで方向性を定める
ここからは、会社のブランドイメージに対して、どの程度の近似性を持たせつつ、違いを作っていくのかについてお伝えします。
ここで役立つのが、タテ軸がWarmとCool、ヨコ軸がSoftとHardで構成された四象限のマトリクスです。
これは、企業ブランドや文化を視覚的なイメージを定める際によく用いられるマトリクス。
まずはこのマトリクスに対して、ブランドマニュアル等をもとにしながら、自社の企業イメージの位置を探ります。
そして次に、同じマトリクス上にWeb社内報のデザインの位置を設定します
ただ仮に、自社のイメージが「Cool×Hard」だった場合、Web社内報の位置も同じ位置に設定してしまうと、他のツールとの整合性は保てるのですが、少し硬い印象のデザインになってしまうので、社員に見てもらえるかどうか、不安になります。
そこで、自社のイメージは「Cool×Hard」だけれども、Web社内報は社員のみんなに親しみを持ってもらうため、自社のイメージの位置よりも少し「Warm×Soft」寄りの位置に置いて、デザインを考えると、会社としてのイメージの一貫性を保ちつつ、読者である社員にとって、親しみやすさや共感が得られやすいデザインにすることができます。
企業ブランドの位置をもとにデザインの幅を考える
また、仮に自社のイメージが「Warm×Soft」に位置する場合も、トップメッセージなどのデザインは「Cool×Hard」に寄せるといった調整や、職場紹介などの「人の温度感」が感じられるようにするために、現在の位置よりもさらに「Warm×Soft」寄りにするなど、ゾーンの幅を広げて、デザインを検討することも大切です。
このように、Web社内報のデザインは、ブランドと日常の「ちょうどよい交差点」を見つけることが、見られるWeb社内報にするためのカギになります。
さらに、社員の皆さまにとって「読んでよかった」と思えるように、情報を詰め込みすぎない「物理的な余白」や、読み手が自由に考えたり、共感するための「心理的な余白」をつくることも、デザインを考えるうえでの大切なポイントです。
このような点を考慮しながら、ブランドイメージからどの程度の逸脱を許容範囲にするかといったことや、親しまれるWeb社内報にするために、どこまでアソビを加えるかといったことを、あらかじめ定めるといったことが、見られるWeb社内報にするためのデザインとしての、重要な考え方です。
これによって、それぞれの記事のデザインも決めやすくなります。

読まれるWeb社内報にするもう一つのカギ
もう一つ、意外と見落とされがちなのが、デザインのトーンと「文章のトーン」の整合性です。
たとえば、洗練されたモノトーン調のデザインに対して、文章がカジュアルな語り口になっていると、読者に違和感を持たれてしまいます。
逆に、柔らかい印象で親しみあるデザインに、固いビジネス調の文章を当てはめた記事が並んでいたら、少し裏切られた気持ちを生み出してしまうリスクもあります。
そのため、Web社内報のデザインを考える際には、全体として統一感のあるトーンを設定しつつ、さまざまなコンテンツテーマや記事の内容、文章のトーンの幅を想定しながら、デザインの幅をどの程度広げると、Web社内報と読者との関係が築きやすくなります。
そして、その結果として文章の書き方もブレにくくなり、社内報全体に芯の通った印象を与えることができ、記事作成などの編集業務の効率化にもつながります。
Yes・Noチャートでデザインの範囲の幅を考える
最後に、うちのWeb社内報の場合、デザインの位置をどの程度ずらしたり、範囲をどの程度広げても良いのかを検討する際に役立つ、シンプルなチャートをご紹介します。
Q1. あなたの会社のブランドイメージは、どの軸が強いですか?
フォーマル・硬い・冷たい・・・Aへ
カジュアル・柔らかい・あたたかい・・・Bへ
AとBの中間・・・Cへ
Aを選んだ方
Q2. そのイメージを社内報でも基本的に守るべきだと感じますか?
YES →ブランドイメージの位置と幅を守る
NO → Q3へ
Q3. 社内向けには「親しみ」や「温度感」をプラスしたい要望がありますか?
YES → 位置や幅をWarm×Soft寄りにずらしたり広げたりする
NO → ブランドイメージの位置と幅を守る
Bを選んだ方
Q4. そのカジュアルさを社内報でも存分に活かしたいですか?
YES → ブランドの位置を中心に幅を広げる
NO →Q5へ
Q5. 社内報は真面目な内容を多く取り入れますか?
YES → 位置と幅をCool×Hard寄りにずらしたり広げたりする
NO → ブランドの位置を中心に幅を広げる
Cを選んだ方
Q6. ブランドイメージよりも「親しみ」のあるWeb社内報にしたいですか?
YES → 位置や幅をWarm×Soft寄りにずらしたり広げたりする
NO → ブランドの位置を中心に幅を広げる
このチャートは、Web社内報のリニューアル時や、デザインコンセプトを考えるといったときだけ活用するのでなく、考えたことを上司に説明や相談をする際のタタキ台にするといった活用もできます。
まとめ
Web社内報のデザインは、社内報らしく親しみやすいデザインにするといった考え方で進めるのではなく、読者である社員の皆さまとWeb社内報の関係をいかに築いていくかといった考え方で、「企業らしさ」と「親しみやすさ」のバランスを調整するように検討していくことがポイントです。

関連記事
-
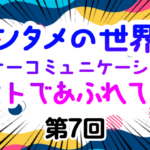
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
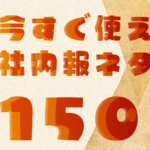
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
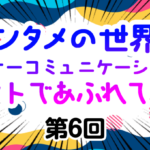
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

