【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第4回 多様性と一体感。有無を言わせぬ引力はどこからやってくるのか?
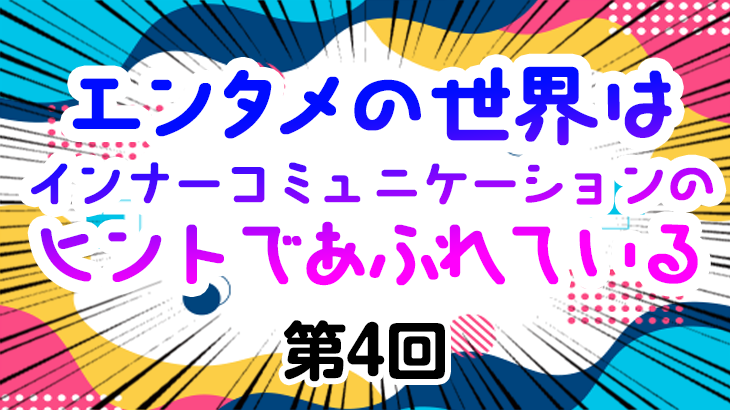
目次
感情を共有する体験を創出し続ける“BABYMETAL”と“新しい学校のリーダーズ”という現象
“BABYMETAL”と“新しい学校のリーダーズ”。共に国内より海外において人気が高いのではないかと思えるほど、グローバルな活躍を見せています。
今年で結成15周年を迎える“BABYMETAL”。5月30日にはロンドンのO2アリーナで日本人グループ史上初となる単独公演をソールドアウトで完遂しました。
今年、結成10周年を迎える“新しい学校のリーダーズ”は、昨年のコーチェラフェスティバル2024において、GOBIステージの大トリを飾りました。
このように2つの女性ユニットは、共に10代半ばから活動を続け、一過性の流行りでは終わらず、長きに亘り活躍し、世界中を魅了し続けています。
そんな彼女たちの活躍からは、インナーコミュニケーションにおいても耳にする機会が多い「多様性」「一体感」といったキーワードが持つ本質のヒントが垣間見えくるかもしれません。

異質な要素の融合、個性の共鳴がもたらす多様性の交錯
“BABYMETAL”は他に類を見ない独自の磁場を生み出し、世界中の多くのファンを引きつけて止みません。ご存知の方も多いと思いますが、そこには「アイドルとメタルの融合」という結成当時から一貫しているテーマがあります。
そして、海外で生まれたメタルという「様式美」に、「kawaii」という日本独特の文化を融合させ、独自の世界観を生み出しているというポイントが、おそらく、海外で絶大な人気を誇っている要因になっていると思われます。
この異質な要素の融合は、他に類を見ない独自の磁場となり、強力な引力を生み出しているのではないでしょうか。もちろん、バックメンバーの異常なまでの演奏テクニックが、“BABYMETAL”を世界ツアーに耐えうるユニットとしての屋台骨を支えている点も考慮すべきですが。
一方、同じく世界中で人気を博している“新しい学校のリーダーズ”は、基本的にセーラー服に上履きという共通のアイコンをまといながらも、その理由を「如何にルールから逸脱せずにはみ出せるか」「同じ服を着ていても個性が出る」を体現し、具現化するためとしています。
ここには、ユニットを構成する4人の、一見するとバラバラに見える個性が互いにぶつかり合い、共鳴し合いながら融合し、さながら「個性の共鳴」がもたらす独自のパワーが圧倒的な引力を生み出していると言えるでしょう。
メンバーの個性というと、特にメディアにおいてはリードボーカル・MC担当のSUZUKAが際立って見えますが、それぞれの言動やルックス(特にヘアスタイル)に、よく現れています。
少し話はそれますが、両ユニットとも面白いことに、世界中にファンが多いにもかかわらず、そのリリック(歌詞)がほとんど日本語で書かれているという点は、特筆に値するでしょう。そしてそれは、エンターテイメントの輸出への貢献度の高さに繋がっている要因のひとつになっているという点も見逃せません。
共通の体験、感情の共有、そして「共に何かを成し遂げている」という感覚
“BABYMETAL”と“新しい学校のリーダーズ”は、共にライブにおける圧倒的なステージパフォーマンスも人気の要因になっていて、そこには毎回熱狂の渦が巻き起こります。
“BABYMETAL”の魂を揺さぶる歌声とパフォーマンス。“新しい学校のリーダーズ”のパワフルなボーカルと自由奔放なパフォーマンス。
そこには、音楽とパフォーマンスによるプリミティブな興奮と高揚感があり、「皆で一緒に、この瞬間を楽しもう!」という(「無邪気な連帯感」とも言えるかもしれませんが)、唯一無二の引力があります。
そんなライブは、オーディエンスに「共通の体験」をもたらします。そして、そこに集まるオーディエンスたちは皆、同じユニットのファンです。つまり、「感情の共有」がもたらされ、心地良い疲労と共に「共に何かを成し遂げている」という達成感が生まれます。
これこそが、それぞれのユニットの多様性がもたらす、プリミティブな「一体感」かもしれません。
感情を共有する体験の創出は生み出せるか?
ここまで、駆け足で“BABYMETAL”と“新しい学校のリーダーズ”における多様性と一体感を考察してきましたが、「異質な要素の融合」「個性の共鳴」「共通の体験」「感情の共有」という4つのキーワードが見えてきました。もはや彼女たちの活動は、ひとつの“現象”と言っても過言ではないでしょう。
多様な才能が輝き、異質なアイデアが交錯する、活気あふれるカオスが生み出す「多様性」。「私たち」という意識の醸成による「一体感」。それらを導き出すヒントが、そこにはありそうです。
経験豊富なベテランには、若手にはない視点を提供してもらう。若手の斬新な発想は、既成概念を打ち破る力となる。それぞれの「らしさ」を認め、尊重し、その力を最大限に引き出す。それこそが、多様性を真に活かすということではなでしょうか?
部署対抗の運動会。成功したプロジェクトの打ち上げ。社内SNSで、熱く語り合う趣味の話題。もしかしたら、一見すると業務とは関係のないような活動の中にこそ、真の一体感が生み出されるのではないでしょうか?
明日から、いや、今この瞬間から、皆さんのインナーコミュニケーションを、もっと多様な才能が輝き、異質なアイデアが交錯する、活気あふれるカオスに変えていけるとすれば、ワクワクしてきませんか?

「多様性」と「一体感」については、インナーコミュニケーションにおいて、永遠のテーマと言えるかもしれません。今後もさまざまなエンタメの世界から、そのヒントを探っていければと思います。

関連記事
-
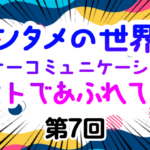
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
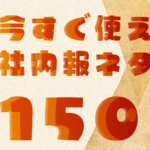
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
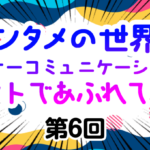
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

