社内報デザインの基礎知識

社内報は内容が同じでも、「読まれる社内報」と「読まれない社内報」に分かれますが、その違いが出る大きなポイントの一つがデザインです。
本記事では、はじめて社内報を担当する方や、既存の誌面を改善したい方、Web社内報のリニューアルや、もっと読まれるWeb社内報に向けて、何を改善すれば良いのかを考えている方に、社内報デザインの基本原則と制作ポイントをお伝えし、紙でもWebでも役立つノウハウを盛り込み、さらに実践に落とし込めるよう、細部に踏み込んで解説していきます。
目次
デザインの重要性が高まっている
社内報の目的は、企業の理念やビジョン、目指す姿、経営の方針や戦略、経営者の想いを社員に届けたり、組織の垣根を越えた社員同士の絆やつながりを育むことで、会社の今と未来に向けて、組織内の「関係性」や「雰囲気」をより良くしたり、社員一人ひとりのモチベーションやエンゲージメントを高めることにあります。
このような、社内の関係性や雰囲気を良くする装置である社内報は今、働き方の多様化や情報発信のデジタル化が進む中で、紙の社内報からWeb社内報への移行、あるいは動画社内報の導入など、媒体の形が大きく変化する過渡期にあります。
さらに、Webサイトの立ち上げや記事の更新、高品質な動画づくりなど、情報を発信するためのツールづくりや運用が容易に行えるようになり、社内SNSやチャットツールなどの導入がしやすくなったことにより、さまざまな部門や部署で多種多様な情報ツールを活用する頻度が高まる傾向が加速しています。
こうした変化や動きを受けて、社員が受け取る情報量は以前よりも飛躍的に増加しています。
その結果、せっかく作った社内報が「数ある情報ツールのひとつ」として、埋もれる社内報になってしまうかもしれません。
このように、社内報を取り巻く状況や環境が著しく変容するなか、より多くの情報を伝えようとして、発信する情報を増やしたり、ページに文字を詰め込んだりすると、それらの情報が、他のツールの中に埋もれてしまい、伝えたいメッセージが社員に届かなくなったり、社内報の存在感を弱めたりしてしまいかねない今、デザインはこれまで以上に重要度を増してきています。
社内報デザインの重要な役割
社内報が他のツールの中に埋もれてしまい、伝えたいメッセージが社員に届かなくなるなどの状況に対して、なぜデザインの重要度が高まってきているのか。
その理由は、デザインが単なる見た目の装飾ではないことや、情報を整理して読みやすくするといった役割だけではないという点にあります。
では、デザインにはどのような役割があるのか。
注目の喚起
誌面や画面を開いた瞬間に「読みたい」という気持ちになるきっかけや入口を作る。
興味の発掘
読者自身が気づいていないけれども潜在的に持っている興味や関心と記事をつなぐ。
理解の促進
さまざまな立場の人に情報をわかりやすく見せて理解の流れをサポートする。
感情の設計
情報やメッセージの意図に沿った「読後感」を作ったり、それをフォローしたりする。
認識の定着
記事を読んだ人の意識や知識に残るようにして新たな行動への足がかりをつくる。
このように、社内報のデザインは単なる見た目の装飾や、情報を整理して読みやすくするためだけの手段ではなく、読者の目を伝えたい情報やメッセージに瞬時に惹きつけることにはじまり、読者に興味を持たせ、理解を促し、感情に響かせて、情報やメッセージを読者が「自分ごと化」するところまで引っ張っていくことにあります。

社内報デザインの基本原則
では、どうすればそのような役割を果たすデザインにすることができるのか。
ここからは、読者の目を伝えたい情報やメッセージに瞬時に惹きつけることにはじまり、読者に興味を持たせ、理解を促し、感情に響かせて、情報やメッセージを読者が「自分ごと化」するところまで引っ張っていくための、デザインの基本原則についてお伝えします。
可読性
可読性とは、読者がストレスなく文章を読み進められるかどうかを指します。フォントサイズ、行間、段落の余白などは、わずかな違いでも印象が大きく変わります。
例えば、本文を10pt以下の小さな文字にしてしまうと、忙しい社員は「読む気」を失いやすくなります。逆に12〜13pt程度の標準的なサイズを採用し、行間も1.4〜1.5倍程度に設定するだけで、文章が格段に読みやすくなります。
また、紙社内報では「印刷したときに読みやすいか」、Web社内報では「スマホの小さな画面でも負担なく読めるか」を意識することが、デザインの制作ポイントとなります。
視認性
視認性とは、誌面を一目見ただけで「どんな記事なのか」「どこから読めばよいのか」が直感的にわかる状態を指します。
見出しのデザインを工夫する、色を効果的に使う、図解やアイコンを配置する――こうしたレイアウトの工夫は、記事の全体像を短時間で把握する助けになります。
特にWeb社内報では、冒頭のアイキャッチ画像やサムネイルがクリック率を大きく左右します。つまり、視認性の高さは、記事を“読んでもらう入口”をつくる大切な要素なのです。
統一感
社内報デザインに統一感がないと、記事ごとに雰囲気がバラバラになり、読み手に混乱を与えてしまいます。そこで重要なのが「ブランドトーン」との一貫性です。
- コーポレートカラーを基調とする
- 見出しのフォントやサイズを統一する
- 写真のトーンやフィルターをそろえる
こうした工夫によって、社内報全体に「自社らしさ」がにじみ出ます。
社内報は単なる情報発信の媒体ではなく、会社の文化や価値観を映すメディアでもあるため、統一感のあるデザインは組織のアイデンティティを強める役割を果たします。
アクセシビリティ
デザインを考えるときには、「誰が読むか」を想定することも欠かせません。
紙社内報の場合、幅広い年代の社員が読むため、シニア層でも読みやすい文字サイズや色使いが求められます。
Web社内報では、スマホで読む人が大半を占めるため、モバイル画面に最適化されたレイアウト設計が必要です。
また、色覚多様性に配慮した配色を意識することも、近年の社内報デザイン制作ポイントの一つです。たとえば、赤と緑の組み合わせは避け、コントラストを十分に確保するなどの工夫が有効です。
速度
速度とは、その誌面や画面を見た際に、読者である社員にたくさんの情報が瞬時に伝わることです。
この点はデザインを専門的に学んだ人でなければイメージしづらいことなのですが、実はこの点こそがデザインのチカラが活きる、最も大きなポイントと言えます。
どんなイメージかというと、初対面の人と会う場面を想像してみてください。
その人のご経験や知識といった情報は会話や、経歴書のような書面からしか読み取ることはできないのですが、その人がどんな人なのかという点は、会った瞬間の雰囲気や印象によって、膨大な想像が膨らむと思います。
これを非言語的コミュニケーションやノンバーバルコミュニケーションと言いますが、社内報のデザインも同じで、誌面やページのデザインを見た瞬間に、その記事が何を語ろうとしている記事なのかを、瞬時にコミュニケーションする役割を担います。
これらのデザインの5つの基本原則を意識することで、社内報は「なんとなく作るもの」から「読者に届く社内報」へと進化します。
紙とWebで異なるデザインの視点
続いて、紙の社内報とWeb社内報のデザインの違いについてお伝えします。
社内報のデザインにおいて、紙とWebではデザインに求められる視点が大きく異なります。
同じ記事でも、紙に掲載するのか、Webで公開するのかによって「伝わり方」が変わるため、それぞれの特徴を理解し、最適な社内報レイアウトを選ぶことが重要です。
紙社内報のデザイン
紙の社内報は、触れることや保存性、拡張性の高さが最大の魅力です。
紙社内報のデザインは、このような点も意識することで、より効果の高い社内報にすることができます。
豊かさのある誌面設計
先ほど「社内報デザインの基本原則」の5つ目で「速度」についてお伝えした際、非言語コミュニケーションに触れましたが、非言語のコミュニケーションは言語によるコミュニケーションより豊かだとされています。
それを表すものとして「メラビアンの法則」が有名ですが、メラビアンの法則では、人がメッセージを受け取るとき、視覚情報55%、聴覚情報38%、言語情報7%の割合で影響するとされています。
この法則からも分かる通り、社内報の視覚情報であるデザインが社員に与える影響は、文字情報をはるかに超える可能性を秘めています。
つまり、社内報のデザインを考えるときは、用意された原稿の量や素材といった言語的な情報を基準に割り付けるのではなく、届けたいメッセージや情報で、文字では伝えきれない印象や雰囲気を醸し出す誌面にするためにはどうすれば良いのかを考えることから始める方が、よりコミュニケーション効果の高い豊かな誌面にすることができるようになります。
特別感と継続感の両立
特集や連載コーナーのデザインにメリハリをつけることで、特集は「大切なテーマが扱われている」と読者に印象づけます。
逆に連載コーナーは「連載」だということを認識できるように、号ごとにデザインを変えるのではなく、一定の基準である「フォーマット」を用います。フォーマットを用いることで、読者はその記事に何が掲載されているのかを瞬時に理解し、その号に掲載されている内容について、前号や前々号との違いといった視点を持ちながら読み進めていきます。
モノとしての魅力と価値
紙質や紙厚といった、「モノ」として手で感じることも重要な情報の一つであり、社内報が何のための媒体なのかを読者に伝えるための、社内報のデザインとしての重要な要素。
情報のオンライン化が進むいまとなっては、こうした「物質的な手触り」も、貴重な情報資源であり、紙社内報ならではの価値といえます。
保存性と拡張性
社員が「残しておこう」と思えるようなデザインの社内報は、時間が空いたタイミングで開かれ、読み返される機会が増えることが期待できます。また、自宅に持ち帰ることに抵抗を感じない社内報は、社員のみならず、ご家族の目にも留まりやすくなり、伝えるメッセージや情報がより広く伝わる可能性が高まる、拡張性の高いものになります。

Web社内報のデザイン
一方、Web社内報は「タイムリーな情報発信」と「アクセスのしやすさ」に強みがあり、在宅勤務をはじめ、多様な働き方や柔軟な働き方が定着する中で、多くの企業が導入を進めています。
ただし、Web社内報は紙の社内報とは異なり、社員が意識的に「見よう」と思わなければ、社員の目に止まることはありません。
Web社内報のデザインを考える際には、このようなWeb社内報ならではのメリットとデメリットをしっかり押さえて取り組む必要があります。
シンプルなUI設計
以前はPCの画面で閲覧することが多かったWeb社内報ですが、最近はPC閲覧だけではなくスマホで閲覧できるようにする企業が増えています。
その際、PCが主体となっていたときのような、複数のカラムで設計されたデザインではなく、縦スクロールで読み進めやすいレイアウトにすることがポイントとなります。
また、Web社内報は紙社内報よりも更新が容易な反面、情報過多になりやすいというリスクを持っています。
そこで、重要な記事が埋もれないよう、トップページは「特集」や「おすすめ記事」といったエリアに社員の目が集まるようなデザインにすることがポイントです。
クリックしたくなるサムネイル
先にもお伝えしました通り、デザインには「コミュニケーションの速度を高める」という重要な役割があり、この点は特にWeb社内報で顕著に現れます。
具体的には、最初の画面を開いたとき、社員の目は記事の見出しではなく、いくつかのサムネイルを極めて短い時間で目を通し、興味を感じた記事をクリックするという行動を取ります。
その行動に応えるためにはサムネイルを、記事と読者の関心ごととを結びつけるような、クリックしたくなるデザインにすることが大切です。
社員の関心の導線をサポート
Web社内報のメリットの一つとして、紙の社内報では難しい「タグ付け」や「カテゴリ分類」、「レコメンド」があります。
これらの機能を画面やそれぞれの記事に組み込み、それらのデザインの視認性や識別性を高めることで、一つの記事から他の記事への遷移をしやすくしたり、社員が「必要」だと感じる情報に素早くたどり着けるようにするなど、社員の関心の導線を視覚的にサポートします。
リアクションボタンやコメント欄のアソビ
社内報は社内コミュニケーションの活性化や促進を促すツールという点に立ち返ると、社内報として取り扱うべき情報は、記事に記した情報のみならず、社員の反応もまた重要な情報と言えます。そのためには「リアクションボタン」や「コメント欄」のデザインも、Web社内報をより充実したツールにするために欠かせないポイント。
単に「いいね」だけのリアクションボタンや、ログ的に記すだけのコメント欄ではなく、「面白かった」「役に立った」「共感した」といったような「アソビ」を感じるようなリアクションボタンや、写真なども掲載できるコメント欄にすることも有効です。

デザイン制作の実践ポイント
社内報のデザインを「なんとなく整える」だけでは、読者の心には届きません。
ここからは、実際に誌面をつくる際に役立つ具体的な制作ポイントを紹介します。
目と心を動かすレイアウト
社内報レイアウトを考える際に大切なのは、「情報を並べる」のではなく、読者に「読みたくなるゆらぎ」と「読むリズム」を提供し、読者が心地よく、自然に最後まで読み進められる流れを作ることがポイントです。
そのなかで、紙社内報で特に意識すると効果的なことが「読みたくなるゆらぎ」を作ること。
具体的には、記事の始まりやページの上部分に「重心」を感じるようにして、視覚的に無意識な不安定感を醸し出すことです。
Web社内報では、文章を読みやすくしたり、画面をスクロールしても飽きないようにするために、改行を増やしたり、パラグラフごとに写真や小見出しを挿入することが効果的です。
読むきっかけを作る写真
社員の写真をたくさん取り入れている「顔が見える社内報」は、読まれる社内報の共通項ですが、ただ顔を載せるという意図だけではなく、写真は文章よりも圧倒的にコミュニケーションが速いという観点を取り入れたデザインは、読まれる社内報づくりに欠かせないポイントです。
そのなかでも特に圧倒的なコミュニケーションの速度を持つ要素が、社員の顔と表情、仕草を大きく写した写真なのですが、これは個人の写真だけではなく集合写真でも、笑顔や会話の瞬間を切り取ると臨場感が生まれ、「ただ並んでいる」だけのものよりも、コミュニケーションの速度は格段に上がります。
テーマ性のある配色
色は視覚的な印象を決定づける大きな要素です。
特集記事では健康特集は緑、未来ビジョン特集は青などを基調色として、テーマに合わせた配色をすることが効果的です。
そのほかのテーマの場合は、色彩心理学を応用するのも有効です。
色彩心理学では、青は信頼感、赤は情熱、緑は安心感を象徴すると言われていますが、社内報のデザインにこうした知識を組み込むと、情報の受け取られ方が、より豊かになります。
また、定期的に発行する紙社内報の配色は、季節感を取り入れることも効果的で、春はピンク系、夏はブルー系、秋はオレンジ系、冬は発行する月に合わせて、例えばクリスマスやお正月にちなんだ配色を取り入れます。
そのほか、企業のコーポレートカラーを基本に据えると、社内報全体に統一感が生まれます。
なお、基調色をもとにした配色を考える場合は、配色例を紹介しているWebサイトを見て、それを参考にすると、テーマ性のある配色を効率的に決めることができるようになります。
意味を瞬時に伝えて定着させる図解
まずは図解についてですが、図解は文章では伝えきれない「イメージ」や「世界観」といった情報や意味を瞬時に伝えて記憶に定着させるといった効果があります。
そのような図解にする上で最も大切なことは、文字情報を極限まで減らし、ビジュアルでその情報の全体像や主旨を、社員が一瞬で捉えられるようにすることがポイントです。
コミュニケーションとしての余白
余白は「余りの白場」ではなく、情報の整理や視線の誘導、特定の要素の強調、洗練された印象の演出など、情報を正しく効果的に伝えるための機能的な役割を果たす、情報やメッセージを適切に伝えるために欠かせない要素の一つです。
例えば、企業のビジョンなど、未来に広がるフィールドや可能性を経営トップが語る記事の誌面やWebページが、たくさんの文字で埋め尽くされている状態をイメージしてみてください。
そのような窮屈なデザインを見て、経営トップの想い描く未来や可能性に共感できるでしょうか?
このようなメッセージ性の高い記事の場合は、そのメッセージに込められた意図や世界観をいかに魅力的に伝えるかがポイントですが、その鍵を握る大きな要素が余白なのです。
デザインでよくある失敗と改善策
ここまでは、デザインの大切な考え方や方法など、読まれる社内報のデザインで「何をすべきか」お伝えしてきましたが、ここからは「何をしてはいけないか」についてお伝えします。
情報が埋めつくされたデザイン
<失敗例>
大切な情報だからといった意図で、文字や写真、図などの情報を可能な限り詰め込む。
そのような誌面は敬遠されがちで、情報の取得に意欲的な社員も「後でじっくり読もう」とするなど、読まれずに終わってしまう可能性が高まります。
<改善策>
- 1ページあたりの文字量を多くても1000字以内に抑える。
- 長い文章は見出しや小見出しで分割して、見出しを追うだけでも凡その内容を掴めるようにする。
- 重要なフレーズは太字や色文字、マーカー処理といったデザインを取り入れる。
- 写真や図解を差し込んで、視線をリセットできる誌面に。
これだけでも圧迫感が減り、読むハードルが下がって伝わりやすくなります。
統一感のないフォントや色使い
<失敗例>
フォントや色がバラバラで、全体に統一感がないと、全体的に粗く「チープ」な印象になり、読む気持ちが低下します。
<改善策>
- デザインガイドラインを作成し、フォント・色・見出しのデザインに基準を持つ
- テンプレートやフォーマットを作成して、その範囲でデザインを考える
- コーポレートカラーをベースに据えることで「自社らしさ」を演出する
- Web社内報では、CSSやテンプレートを整備することで再現性を確保する
デザインのテンプレートやフォーマットは、統一感のある社内報にして、読者に安心感と信頼感を与えるばかりでなく、そのような基準を持つことで、業務の効率性が格段に高まります。
なんとなくゴチャついた誌面
<失敗例>
ページにあれこれと入れすぎて、何を伝えたい記事なのかがわからなくなる。
<改善策>
- 「何を伝えるか」ではなく「何を伝えないか」を決めて情報を適切に取捨選択する
- 「余白」を他の情報と同じように、重要なデザイン要素として意識的に活用する
- 必要以上の余白やスペースを作らないようにするための整理と工夫を行う
デザインは、限られたスペースや読者が読む時間を制約条件として、掲載する情報や要素を取捨選択するといった、伝えたい情報やメッセージを確実に伝えるために、情報を整理整頓することでもあります。
また、余白は「無駄」ではなく、「読みやすさ」を高めると同時に、「上質さ」や「信頼感」などを生む要素です。
一方で、罫線で四方を囲うようなデザインの場合、罫線の周辺に持たせる余白は、無駄なスペースとなる場合があり、その結果として誌面が窮屈でゴチャついた印象になっている場合もあるので、注意が必要です。
何を読めば良いのかわからない導線設計
<失敗例>
Web社内報にたくさんの記事を掲載したために、重要な記事が素通りされてしまう。
<改善策>
- サムネイル画像やバナーで記事の特徴を視覚的に伝える
- 「おすすめ記事」枠を設けて、読んでほしい記事に誘導する
- 「注目」や「必読」といったアイコンをサムネイルにつける
Web社内報のデザインは、重要な情報に読者をいかに誘導するかが成否を分けます。
社員参加型のコンテンツは定着すれば、Web社内報に社員を呼び込み、Web社内報を開く習慣のきっかけになる場合がありますが、その反面、重要な情報やしっかり読み込む必要がある記事が、素通りされてしまうことにもつながります。
このような問題は、記事の内容を工夫しても、そもそもその記事を開いてもらえないため、トップページやサムネイルのデザインの工夫によって解決することが有効です。
仕組みでデザインの改善を進める
社内報デザインは、一度きれいに整えれば完成というものではありません。
むしろ大切なのは、社員の反応を見ながら改善を繰り返し、継続的に進化させることです。
読者のニーズは常に変化しており、それに応じてデザインやレイアウトも調整していく必要があります。
ここでは、改善を続けるための仕組みを具体的に整理します。

社内報アンケートで社員と誌面の関わり方を探る
社内報アンケートでは、デザインの良し悪しを直接聞いても適切な答えが返ってくることは少ないため、社員が誌面をどのように見ているのかを探ります。
それを聞くための設問と選択肢の例としては、
- 社内報を読む理由を教えてください。
□ 社員として必要な情報を幅広く知るため
□ 知っておくべき情報をかみ砕いて理解するため
□ いろいろなことに興味を持つきっかけにするため
□ 普段接することのない部署や人のことを知るため
□ モチベーションを高めたり働きがいを感じたりするため
□ 仕事の息抜きやリフレッシュをするため
□ 社内や外部の人との会話のネタを見つけるため
□ ものの見方や考え方、行動の参考や気づきを得るため
□ 業務に必要な知識やノウハウを得るため
となります。
この設問や選択肢は社員に社内報を読む目的や理由、社内報に期待していることを問う内容になっており、デザインとは関係しないもののように感じると思います。
けれども、この設問と選択肢は、そういったことを問うと同時に、社員の閲読行動を読み取るものになっているのです。
例えば、「社員として必要な情報を幅広く知るため」との回答が多い場合、デザインはビジネス誌のようなものが好まれると読み取ることができます。
一方で「仕事の息抜きやリフレッシュをするため」の回答が多い場合、ビジネス誌のようなデザインは敬遠される可能性が高く、できるだけゆとりのあるカジュアルな雰囲気のデザインにすることが必要となります。
社内報アンケートの設問設計などについてはこちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
社内報のデザインの改善は、担当者個人の主観ではなく、このような設問や選択肢をもとにして得られた読者の閲覧行動をもとに見直すと、より読まれやすい社内報にすることが可能となります。
Web社内報はアクセスデータを活用する
Web社内報の強みは、アクセスログや行動データを簡単に取得できることです。
- PV(閲覧数)を見て、どの記事がよく読まれているかを測る
- 平均滞在時間を見て、誌面レイアウトがどのくらい読ませているかを測る
- 直帰率や離脱率を見て、サイトや記事の導線設計が適切かどうかを測る
例えば、平均滞在時間が極端に短い記事は「文字が多すぎて離脱された」「写真が少なくて読みにくい」などの改善余地がある可能性があります。
データを読み解きながら、レイアウト設計や記事デザインを最適化していくことが大切です。
社員の生の声や本音を聞く
アンケートやアクセスデータでわかることは、読まれている、あるいは読まれていない理由の「答え」ではなく「可能性」です。
社内報の改善は、その可能性をもとに何をすれば効果が出るかを考えて、実践で試してみて、再びアンケートやアクセスデータを見て、その可能性の真偽を検証します。
ただし、可能性の真偽を検証するために、一定の知見や経験、スキルといった能力が必要になります。
そういった能力に依存することなく、可能性を検証するためには、読者である社員の「生の声」を聞くことです。
広報委員や編集委員、通信員といった体制や仕組みがある会社の場合は、その方からフィードバックをいただきますが、そういった体制や仕組みがない会社の場合は、取材などで社員と会う機会を活かして、アンケートやアクセスデータをもとに導き出した可能性を仮説として、取材の合間などに取材対象者から声や本音をいただきます。
こうした声や本音を定期的に聞き、それらを反映することで、社内報レイアウトが実際の読者に寄り添ったものになります。
トレンドのアンテナを張る
社内報のデザインは時代に左右されないモノではなく、実はそのときどきのトレンドがあることをご存知でしょうか?
それを知るためには、例えば10年前の社内報と今の社内報を見比べたり、10年前の雑誌と今の雑誌を見比べてみてください。
そうするとデザインのトレンドが、時代とともに変化していることに気づくことができます。
雑誌だと分かりづらい場合は、Webサイトを思い浮かべてみてください。
Webサイトのデザインは、雑誌などの紙媒体よりもはるかに速いスピードで、デザインが大きく変化してきていることを見てとることができます。
社内報はあくまで「社内向けメディア」ですが、読者である社員も日々、市販の雑誌や外部のWeb記事、SNS、YouTubeに触れています。
そのため、社内報も外部のトレンドを意識した「今っぽさ」を反映したものにしていくことで、読者に寄り添っていくことが大切です。
この「今っぽさ」というのは、教科書があるわけではありませんが、定期的に雑誌やニュースサイトのレイアウトから「見出しデザイン」や「余白の使い方」を学びとることや、SNSの人気記事やYouTubeの人気チャンネルから、人が開きたくなるサムネイルのデザインなどを学ぶことができます。

最後に
本記事では、社内報デザインの重要性と、実際に誌面を制作・改善していくための具体的なポイントを整理してご紹介してきました。
改めて強調したいのは、社内報の成果は「内容」と「デザイン」の両輪によって決まるということです。
社内報は「単なる情報共有ツール」ではなく、会社の文化や価値観を映し出す経営資源です。
その価値を最大限に発揮するために、社内報デザインは装飾ではなく「伝わる仕組み」として位置づけるべきだと考えます。
ぜひ本記事で紹介した制作ポイントを実践し、デザインを通して「読まれる社内報」「社員が楽しみにする社内報」へと進化させてください。

関連記事
-
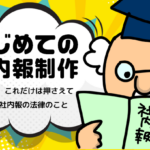
【はじめての社内報制作】 第12回 これだけは押さえておきたい社内報の法律のこと
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
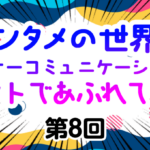
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第8回 “静かなる革命”の予感
皆さんは、藤原ヒロシ氏が2024年12月にスタートさせた『QUIET』というYouTube ...
-
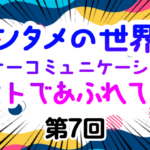
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
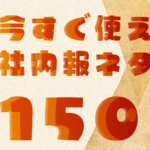
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...


