【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
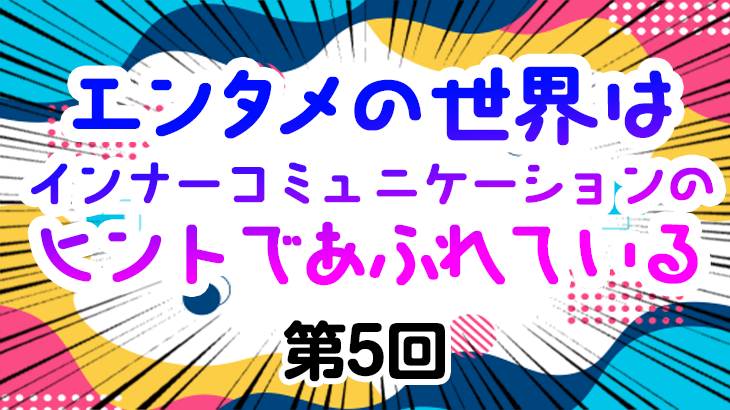
目次
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界
皆さんはTikTokのショートムービー群『ハル学園』をご存知でしょうか? 2023年からスタートし、瞬く間に支持を得た作品群です。
これらは1本あたり、およそ30秒〜90秒くらいで展開していて(120秒くらいの作品も若干ありますが)、手軽に視聴できるのですが、引き込み度がかなり高いので気が付けば10本20本と続けて観てしまいます。
一体、そこには何があるのでしょうか? ショートムービーの可能性、そしてヒントを『ハル学園』から紐解いてみたいと思います。
過剰なまでの日常性が生み出すメタフィジカルな共感
多くの人々が持っているであろう10代の頃の記憶。そこには、「そんなようなこと、あったなぁ」「もし、そうだったら良かったなぁ」「ああすれば良かったなぁ」といった、現実と理想と後悔が渦巻く、何とも言えない、甘い味わいがあります。
『ハル学園』はそんな記憶を呼び起こし、潜在意識・顕在意識を問わず、刺激し、共感するストーリーが展開していきます。もちろんフィクションですから、そこにあるのは、実はメタフィジカルな共感でしかありません。ゆえに過剰な日常性、すなわち“超日常性”がもたらす共感と言い換えることもできますし、日常性の巧妙な偽装とも言えます。
しかし、そこにあるのはユーザー自身が脳内変換して生まれる、バーチャル体験によるフィジカルな共感でもあります。他愛もない表現をしてしまえば「あるある」だったり、「それはないでしょう」だったり、「そうだったらいいな」だったりと、同じ1本のストーリーでもユーザーによって共感ベクトルは多彩な顔つきに変化します。

効率的な情報伝達手段
一方で、短い尺の中に込められた多くの情報は、タイパが求められる秒単位の情報過多な現代社会において、極めて効率的な情報伝達手段として機能している点も見逃せません。
一例を挙げるならば、あるストーリーでは主人公を悩ませる、いわゆる敵キャラが登場しますが、何も語らずとも瞬時にユーザーに「この人、絶対に敵役だよね」と分からせる仕掛けがあります。それは、そのキャラだけが赤いベストを着用しているという、分かりやすく、巧妙な演出にあります。
そういった視覚的なアイコンのみならず、キャラクター(出演者)の表情やジェスチャーも含めたさまざまな要素が圧縮され、凝縮された情報としてユーザーの脳に直接刷り込まれる高密度な情報シャワーは、思考する間もなく感情を喚起し、共感を強制的に引き出す。まさに、情報伝達における究極のショートカットと言えるのではないでしょうか。
ユーザー自身が脳内で再構築する快感
この虚構の学園のストーリーの真髄とも言えるポイントは、超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”にありますが、先にも述べた「ユーザーによって共感ベクトルは多彩な顔つきに変化」するところにありますが、それはどういったところにあるのでしょうか。
キャラクターたちの会話はしばしば断片的であり、感情やノリ、あるいは『ハル学園』内のみでの共通認識で繋がっているように見えることもあります。また、起承転結といったベーシックな物語の枠組みはそこには存在せず、そこにあるのは、脈絡のない断片的なシーンの連続で、それらをユーザー自身の記憶や理想や後悔を元に、ユーザー自身が脳内で再構築するところにポイントがあります。
そして、実際のストーリーがユーザーの思惑通りに進んでも、あるいはそうでなくても、ユーザーは心地よさやもどかしさを覚え、それは、ある種の快感をもたらしてくれるのです。
だからこそ、『ハル学園』が多くのユーザーを引きつけて止まず、次々と画面をタップさせてしまうのです。

“感覚的な共感”はインナーコミュニケーションに不可欠な要素
『ハル学園』の超日常性がもたらすさまざまなポイントは、言葉による説明がなくとも、感情やニュアンスを強烈に伝達する力を持つ“超言語性”と置き換えることができるかもしれません。
ショートムービーという、インナーコミュニケーションにも活用されるシーンが多い媒体において、“感覚的な共感”をもたらすためのヒントは、短く、インパクトがあり、凝縮された情報が短時間で脳に刺激を与えるところにありそうです。もちろん、ユーモアも忘れずに。
また、ユーザー自身が脳内で再構築する快感も盛り込めることができれば、ショートムービーといえども、タイパ重視という考え方が横行する現代における「思考停止や理解力の低下を招いてしまうのではないか」といった危惧に対抗する手段にもなりえるのではないかとも思います。
ここまで述べてきたヒントが全てではありませんが、ショートムービーというツールをインナーコミュニケーションにおける、“感覚的な共感”をもたらす有効な手段として活用されるシーンが、各所で見られることを期待しています。
もしかしたら、既にヒントを見つけ、活用されていますか?

関連記事
-
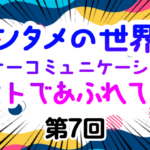
【エンタメの世界はインナーコミュニケーョンのヒントであふれている】第7回 「4番サード長嶋」という魔術
スポーツエンタテインメントがもたらす、擬似共同体の物語と“まだ何も起きていないのに盛り上が ...
-
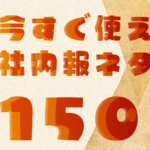
「社内報のネタが思いつかない」。 担当者の方からよく聞く悩みですが、実はネタ不足ではなく、 ...
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
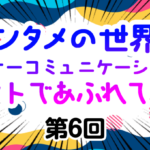
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...

