成功事例から紐解く読まれる社内報の企画づくり

「社内報がなかなか読まれない」「すぐにマンネリ化してしまう」といった悩みは、社内報のご担当者が避けて通ることができない共通の悩みです。
一方で、数多くの社員の方にしっかり読まれ、愛され、親しまれている社内報もたくさんあります。
本コラムでは、社内報の改善に悩んでいる方にとって、実践のヒントとして役立つことを目指して、「うまくいっている社内報」の事例をテーマ別に紹介しながら、注目すべき成功ポイントや企画アイデアを抽出し、お伝えしてまいります。
紙の社内報やWeb社内報など、媒体の種類はさまざまですが、多様な成功事例を通じて、自社に合ったコンテンツや運用のヒントを見つけていただければ幸いです。
目次
読まれる社内報にするための鉄則
社内報が成功するか否かは、何を伝えるかといった「コンテンツ」と、どう届けるかといった「コミュニケーション」の『両輪』を捉えた取り組みが非常に重要なポイントとなります。
では、どのようなポイントを押さえることで、その両輪、つまり「読まれる社内報」にすることができるのでしょうか?
それは、以前お伝えした「見られる!読まれる!WEB社内報の成功事例21選」に記しており、今回はその記事から特に重要となるポイントをピックアップしてお伝えします。

◾️見られる!読まれる!WEB社内報の成功事例21選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h11_10059/3061/
・顔が見える・・・写真、名前、コメントが揃っている社内報
・1分で読める・・・短文・簡潔・要点明快な記事構成
・身近に感じる社長メッセージ・・・トップの人柄や考えが感じられる仕掛け
・更新頻度がわかりやすい・・・全社メールでプロモーション
・読後感を大事にしている・・・「読んでよかった」と思わせる余韻づくり
・編集後記や裏話がある・・・作り手とのコミュニケーション
・リアクションできる・・・アンケート、コメント欄などを設置
これらのポイントはいずれも、単に情報を届けるだけでなく、「双方向性」「読み手の感情」「参加」など、記事のテーマやコンテンツの内容だけではなく、記事と社員のコミュニケーションを視野に入れて作るといったことを示しています。
この考え方をもとに、社内報における成功の共通点をまとめると、以下のような観点が見えてきます。
人が見える企画・編集
実名・顔写真・コメントを載せることで、「誰の話か」が明確になり、読む側の関心が高まります。
参加できるコンテンツ
仕事に直接関係ないような、緩やかなテーマは、他者への関心や共感を促し、社内コミュニケーションのきっかけとなります。
読後感や体験価値の提供
記事そのものに物語性や余韻を持たせることで、ただ「読んだ」という体験ではなく、「読んで何かを得た」といった体験を社員に提供することができます。
つまり、読まれる社内報にする鉄則をまとめると、コンテンツといった視点に加えて、コミュニケーションという視点を持って、その両輪をバランスよく回すこと。
そして、社内報を情報提供の手段としてだけではなく、記事を通じて社内のつながりや関係を育んだり、読んで何かを得るといった体験を提供するための媒介ツールとして、本当の意味での「メディア」にする内容や設計を考えたり、工夫したりします。
そして、それらを実践した際には必ず検証し、良かった結果は他のコンテンツなどにも活用したり、うまくいかなかったことは、なぜうまくいかなかったのかを見直して、改善や改良をし続けながら、社内報をアップデートしていくといった取り組みを繰り返していくこととなります。
読まれて役に立つ社内報にする成功事例
社内報を成功させる、つまりはたくさんの社員の方に読んでいただき、役に立つと実感していただける社内報を作るためには、ひとつのテーマや形式にこだわらず、読者の興味や関心といった読者の視点を持ちながら、さまざまな軸や切り口を検討し、それらを組み合わせることで、コンテンツのバリエーションを豊かにすることがポイントです。
ここからは、それらを実践していくためのアイデアとして、あるいはマンネリ化防止を意図して、定番ではない社内報のコンテンツ企画のいくつかの成功事例を、元の企画から少しアレンジを加えながら、4つのタイプに分けてご紹介していきます。
1.ノウハウ共有系
社内にはさまざまな「ノウハウ」が無数に点在しています。
それらの中には、その業務でしか活かされないノウハウばかりではなく、他の業務や職種の方にも活きるノウハウもたくさんあります。
社内報を成功に導く方法の一つとしては、社内に点在している役立つノウハウを、広く伝えて届けるメディアとして機能させていくことが、一つの有力な方法です。
工場のノウハウを全社に波及する企画
製造業をはじめとする現場職場では、日々の改善活動や5S、QCサークルなどの成果が蓄積されています。
ある企業では、その工場ごとの小さな改善ノウハウを、写真とセットで記事化し、「これは他部署でも応用できる」といった声を集めました。
この企画で紹介した工場のノウハウは、
・整理整頓の工夫、工具の置き場の見える化
・動線の改善や準備時間の短縮術
・チェックリストのデジタル化
など。
これらを紙の社内報で特集し、その後Web社内報で連載コンテンツとして定期的に掲載し、読者は他部署の工夫や知恵を知るだけでなく、自部署にも役立てようという意識を持ったり、実際に行動したりするといった「体験」を提供しています。
続いて、同じような企画ですが、もう少し職種の幅を持たせた企画の事例をご紹介します。
「職場内名人」がいつも使っている裏技
この企画では、営業・開発・経理・人事など、職種ごとに必要なスキルや、活用するテクニックは異なりますが、その中には他の職種にも役に立つテクニックはたくさん埋もれています。社内報ではこれらを編集という取り組みを通じて掘り起こしていき、全社に広げていきます。
例えば、
・人を動かすプレゼン資料の作り方
・仕事に活きる数字と会計の知識
・提携業務を自動化するエクセル活用法
この企画のポイントは、業務内容ではなく「やり方」に焦点を当てること。
そして、タイトルも「裏技」といった、なんとなく得しそうなニュアンスを含んだものにすることです。
こうすることで読者層を問わず、「ちょっとやってみよう」といった反応を得ることができ、さらには登場していただいた、優れた技能を持っている方の、社内での存在感を高めたりすることができます。
2.インタビュー・対談系
社内報の記事を作るための情報収集の方法を大きく区分けすると、インタビューや対談といった方法、役員や社員に依頼して寄稿や投稿をしていただく方法、ニュースのような編集サイドが情報を集めて集約する方法に分かれます。
その中でも特に社内報を成功に導くための有効な方法が、インタビューや対談といった、五感を使って情報を集める方法です。
特にこの方法は、全社に関係するツールとしては、社内報にしかできない方法ですので、社員の期待も大きく、さらには社内報の「格」を高めることにもつながると言えます。
先輩×後輩の対談
社内報の編集は、組織の垣根を越えるコミュニケーションを実現するための手段としても有効です。
その一例がこの「先輩×後輩」の対談。
このコンテンツ企画は、職場内の先輩と後輩ではなく、異動によって別々の仕事をすることになった先輩と後輩が、一緒に仕事をしていたときのことや、今の仕事について語り合う企画です。
このような企画は、登場していただく方と直接関わりのない方にとっては興味を持ちづらい部分もあるため、そういった傾向を払拭するための工夫が必要となります。
例えばある企業の社内報では、「問いかけ」式の記事構成にして、その問いかけを読者との共感の接点にすることで、読もうといった気持ちを設計しています。
トップ×有識者の対談
社長メッセージをただ発信するのではなく、「社外の専門家」との対談として構成することで、風土改革等の経営課題や社内コミュニケーションに関する課題について、社員にとっての理解が進みやすくすることにつながる企画をご紹介します。
・人を育てる組織と話し方
・働きやすい職場環境の作り方
・生成AIパートナー化計画
たとえば「働きやすい職場環境の作り方」では、職場の人間関係に関する有識者にお越しいただき、人間関係に活かせる理論を語っていただきます。
そのなかでも「今日から使える」という点を、記事としての価値にして、職場内の挨拶をテーマに、人間関係づくりにおける挨拶の効果や効能をアドバイスしていただきます。
それを受けてトップには、自社の課題やご自身の望み、社員への期待を語っていただくことで、社内の課題と解決策を一体化して伝えます。
このようにして、社員が客観的な視点を持ちつつ、トップの意向や想いに触れることができ、目指す方向に対して具体的なアクションができるように設計します。
3.現場体験・中の人系
これは編集部が「行ってみた」「やってみた」といった企画。
ある企業では、広報担当が自ら工場見学を体験したり、研修に潜入した様子をレポートする「やってみた」形式の記事が人気を集めています。
紙の社内報ではカジュアルなタッチのデザインにして、Web社内報ではたくさんの写真で「どんな現場で」「どんな工夫がされているか」をリアルな目線で紹介し、他拠点の社員にも臨場感をもって伝わるコンテンツにしています。
この方法は、部署間での相互理解を促進し、他拠点へのリスペクトや共通認識の醸成につなぐことをねらいにして、連載コンテンツで運用すると効果的です。
・〇〇の裏側大公開!
・びっくり!〇〇の仕事
・のぞきみ〇〇プロジェクト
といったようなコーナータイトルで展開します。
特に最後の「のぞきみ〇〇プロジェクト」は、全社で部署ごとに取り組んでいるプロジェクトや施策を共有するコンテンツとして運用します。
そうすることで、他部署の取り組み方や取り組む上でのコツなどを共有することができると同時に、全社の取り組みへの意識の向上や取り組みの活性化を図ることができます。
編集こぼれ話
読まれる社内報づくりを目指すにあたっては、社内報の編集サイドと社員との距離感を常に意識することも大切です。
そこで有効な方法が、社内報に社内報の編集や制作工程にある、ちょっとした「こぼれ話」の共有や演出です。
たとえば「この取材でお話を伺っていると・・・といったことを感じました」といったような、臨場感のある体験談を載せることで、記事に「人の気配」を加えることができます。

4.参加型・アンケート系
たくさんの人が載っているということも、成功している社内報の特徴の一つ。
そして、たくさんの社員に登場していただけるテーマや切り口を考えることは、社内報担当者としての腕の見せ所でもあります。
あなたはどっち派?
あるお菓子メーカーが取り組んだプロモーションで、「きのこ派?たけのこ派?」といったものをご記憶されている方は多いと思います。
このような軽めの二択アンケートを定期的に掲載する事例は、社員の投稿・反応を促すための第一歩としてたくさんの企業が社内報に取り入れており、大きな効果が得られています。
この企画では、「なぜそちらを選んだか?」というコメント付きで紹介するなど、単なる投票結果で終わらせずに、社員に出ていただく工夫が重要です。
そのためには、連載コンテンツにして、「次号は〇〇派?△△派?」といった感じで、次号のお題を案内して投稿者を募り、それを連ねていくことが成功のポイントとなります。
この企画では、お題の作り方に気を配る必要があります。
まずは、どちらを選んでも、選んだ人にとってネガティブにならない二択にすること。
次に、誰もが答えやすいような内容にして回答するハードルを下げること。
最後に、投稿や投票の導線をシンプルにしたり、PCやスマホを一人ひとりに支給されていない職場の方でも参加できるようにすることです。
わたしのイチ推し
このような社員参加型の企画は多くの企業が社内報に取り入れていますが、ここではたくさんの社員が参加しやすい工夫を行なっている例をご紹介します。
その方法は、投稿していただくテーマを複数のバリエーションの中から選んでいただくといったもの。
例えば
・愛読ブックレビュー
・職場のホットな話題
・快適ライフハック
・MY サステナブル
・お気に入りレシピ
・これがなければ!
・スマホ写真 奇跡の一枚
・まさかここまでハマるとは
など、おすすめ紹介から趣味の紹介など、さまざまな切り口で投稿テーマを設定しておき、その中から投稿者に選んでいただけるようにします。
こうすることで、記事としても読者の関心の幅を広げることができたり、アクティブな印象を演出することができたりします。
成功事例の共通点と実践のヒント
これまで紹介したコンテンツ企画には、いくつかの「成功の共通要素」があります。
単におもしろい、反応が良かったというだけではなく、長期的に見て社内報の信頼や存在価値である「格」を高めていくためにも、以下のような視点が重要です。
「人」を軸にする
成功している社内報は、情報の内容の前に「人」を軸にしています。
たとえば、「ノウハウ共有」も「現場レポート」も、「誰が」「どんな意図で」やっているかを掘り下げているからこそ、読者の共感を得たり、役に立ったりします。
「読後感」を設計する
読者が「読んでよかった」「なんか気持ちが軽くなった」と思えることが、社内報の価値になります。
成功事例の多くは、「役に立った」といった編集サイドからの発信の視点よりも、読者が「誰かに話したくなった」、あるいは「自分もやってみようと感じた」といった、読者が記事を自分のものとして見たり扱ったりすることを、コンテンツ設計の「ねらい」として作られています。
まずは実際にやってみる
多くの社内報の成功事例は、練りに練られた完璧な企画からでなく、チャレンジしてみるという姿勢や、スモールスタートで試してみるといった勢いから生まれています。
現在は製品開発などで「アジャイル」といった考え方が重要視されていますが、社内報も同じで、完成度の高さを初回から求めるよりも、「読者と育てる」という発想で、まずはやってみて「改善を繰り返して良くしていく」「読者の本当のニーズを探る」という意識とスピード感をもって取り組んでいくことが、本当の意味での「双方向」であり、社内報に対する期待や信頼を築いていくポイントになります。
成功への課題と解決のステップ
成功する企画について考えることは、言い換えると「成功するための『仮説』を持つ」ということに他なりません。
社内報の課題について考えるとき、「読まれていない」ということや、「マンネリ化している」ということを課題として認識してしまいがちですが、それらは課題ではなく状態や現状なのです。
課題とは本来、「何を改善するか」「どこを改善するか」といった、成功や目指していることに対して、いま満たされていないことが何なのかを具体化したものです。
さらにもう一歩踏み込むと、「何を改善するか」「どこを改善するか」に対する根拠が不明確な状態では、それは課題ではなく、「きっとうまくいく」といった『想定』や『推察』です。
成功する企画を考えるためには、この『想定』や『推察』をより確かなものである『仮説』にして取り組むことがカギとなるわけです。
つまり課題とは、成功に向けて何をすれば良いのかに関する『想定』や『推察』を、『仮説』にすることになります。
実はこの点を認識したり意識したりすることが、成功に向けた大きな第一歩なのですが、ここからは、その仮説を立てるためのポイントをご紹介します。

成功への仮説をつくる5つのポイント
1.読者の視点に立って現状を問い直す
「読まれない理由」ではなく「読まれるときはどんなときか」を考えます。
そのためにもまずは読者の感情や行動を観察し、読者アンケートやヒアリングを通して、社員の社内報に対する期待を探ります。
情報を「関係ツール」として再定義する
社内報のコンテンツを単なる情報発信のツールではなく、「人と人との関係をつなぐ接点」として見直します。
その際、一つ目のポイントとも関連しますが、社員を「情報の受け手」ではなく、「関係の担い手」として捉えることで、企画の幅を広げたり、内容をより深くすることができるようになります。
3.発掘可能な宝物に目を向ける
社内で言語化されていない想いや、個別に行われている取り組みなどを探り、丁寧にすくい上げて、それらを全社に波及させることを社内報の役割として位置づけて、新たな試みができないかを考えます。
4.「対話」の視点でコンテンツを見直す
一方的な伝達で終わらせず、社員の参加や社員と編集サイドのコミュニケーションなど、「双方向」の仕組みや仕掛けがなされているかを問い直すことで、社員にとって充実度の高いツールへと成長させていきます。
5.社内報を社員と一緒に育てていく
社員のニーズは多種多様で、日々変化するため、「確実に読まれるもの」を作ることはできませんが、「より読まれるもの」にしていくことは可能です。
そのためには読者である社員と一緒に社内報を育てていくといった姿勢で、現在の社内報や、社内報づくりの取り組み方を見直して、社員と一緒に育てるために、何をすれば良いのかを考えていきます。
社内報の企画事例のご紹介
社内報ラボではこれまでに、たくさんの社内報企画の事例やアイデアをご紹介してきました。
最後にそれらをご紹介します。
→合わせて読みたいおすすめ記事はこちら
◾️社内報リニューアルの成功事例7選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h10_10018/2567/
◾️社内報の新入社員紹介 アンケート項目100選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/12/08/1675/
◾️社内報で困る ネタの見つけ方と企画・テーマ例をご紹介
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2020/08/17/346/
◾️家族にも読んでもらえる社内報のネタ24選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2022/03/18/1845/
◾️見られる!読まれる!WEB社内報の成功事例21選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h11_10059/3061/
◾️Web社内報 お楽しみ企画・箸休め企画45選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h09_10051/3009/
◾️Web版社内報 「いいね!」「コメント」の活性化アイデア9選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/h11_10021/2607/
◾️【事例紹介】仕事に役立つ社内報企画の成功事例
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2020/05/18/261/
◾️【事例紹介】外部の視点を取り入れ、企画のバリエーションを増やそう
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2020/06/15/242/
◾️【社内報のネタ】職場間の壁や垣根を取り除くネタ9選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/11/24/1392/
◾️【社内報のネタ】成長やスキルアップに役立つネタ9選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/11/22/1388/
◾️【社内報のネタ】社内報のファンをつくる箸休め企画9選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/10/26/1401/
◾️【社内報のネタ】部署内コミュニケーションを活性化させるネタ8選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/10/22/1405/
◾️【社内報の季節ネタ】毎月の企画12カ月分!季節や年中行事にちなんだ社内報ネタ12選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/09/29/1384/
◾️【社内報のネタ】みんなでお互いの健康と元気を支えあうネタ9選
https://labo.liaison-kikaku.co.jp/column/2021/07/07/1242/
まとめ
社内報での「成功」とは本来、人と人との関係を「タテ・ヨコ・ナナメにつなぐ」ことを適切に実現できているかどうかだと言われています。
それを可能にするのが、情報による「関係づくり」としての編集設計です。
社内報は「情報の発信ツール」ではなく、コンテンツとコミュニケーションの両輪で情報を編集して、社員にとって「つながるきっかけをつくる」「人同士の関係を育む」「何かの体験を得る」ことができるメディアと位置づけることの重要性がお分かりいただけたかと思います。
今回ご紹介した事例はいずれも、社内報をそのように位置づけることを出発点に考案された事例です。
そして、成功への仮説を立てて実践し、その結果をきっちり検証して、改善するといったことを繰り返す中で生み出された企画です。
さらに、検証と改善に当たっては、社内報の内容や見せ方だけではなく、最初に立てた仮説そのものも改善し続けるといった考え方で取り組むことにより、企画の精度アップにもつながっています。今回お伝えした内容は、そのような考え方や取り組み方を進めていく際のヒントとしてご活用していただけると嬉しく思います。

関連記事
-

はじめに eメール社内報(社内報メールマガジン)は、社員間の情報共有を活性化し、会社の目標 ...
-

近年、社内報は内容や見せ方、ツールの連動といったことだけではなく、社内報の役割から大きく見 ...
-
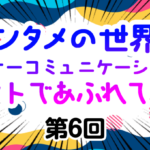
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第6回 ギャップと多角的な視点。意味の無意味化がもたらすもの
赤ちゃんが喜ぶTV番組『シナぷしゅ』は、プリミティブなコミュニケーションとギャップによる魅 ...
-
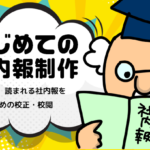
【はじめての社内報制作】 第11回 読まれる社内報をつくるための校正・校閲
はじめて社内報を担当することになった皆さんへ。 シリーズ はじめての社内報制作は、皆さんが ...
-
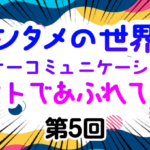
【エンタメの世界はインナーコミュニケーションのヒントであふれている】第5回 その超日常性が呼び起こす“感覚的な共感”と、究極のショートカット
直感的に、そして感覚的にその世界観に引き込まれる、ショートムービー群『ハル学園』の世界 皆 ...

